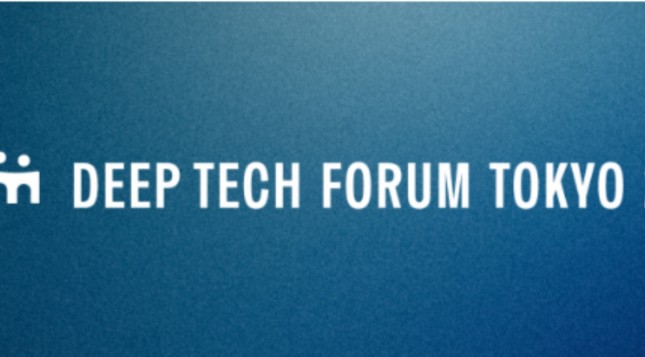変容し続ける時代の中で学ぶには。東大Weekが導く、令和時代のアカデミア【東大Week@Marunouchi DAY3】
読了時間:約 12 分
This article can be read in 12 minutes
昭和から平成、平成から令和へ、時代の移ろいとともに私たちの暮らしも大きく変化している。アカデミアの世界においても同様に、これまでの技術や常識を大きく超越した研究やデータ解析が進む中、MEC-UTokyo Labが主催する「東大Week」の第3回目が盛況のうちに幕を閉じた。
東京大学から専門家を招いて大手町・丸の内・有楽町エリアのカフェ・レストランで講演を行うこのイベントでは、この日、4名の教員が登壇。令和の時代を生き抜く子どもたちの発達と保育のあり方について考える野澤祥子准教授、古生代の脊椎動物に焦点を当てて進化と発生を探求し続ける平沢達矢准教授、環境と人の双方が健康な未来の可能性を示す古賀千絵助教授、これからの時代に求められる組織と働き方について新たな提言を行う稲水伸行准教授と、各々の専門分野のもつ魅力や喫緊の課題について講演を行った。
変革の中で、東大ではどのような研究が行われているのか?私たちの社会は、どのような未来に向かっているのか? 本記事では、キャンパスを飛び出した4名の教員の“知”に触れながら、最新の研究動向を紹介する。
INDEX
・これから必要とされる、新しい子育てと保育
・戦略的な最先端研究で紐解く、大昔の動物
・都市と人の持続可能なまちづくりを実現するために
・ハイブリッド・ワークの分析から見る、時間展望と創造性
これから必要とされる、新しい子育てと保育

東大WEEK3️日目。丸の内の「GARB Tokyo」にまず登壇したのは、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(通称Cedep)准教授の野澤祥子氏。野澤氏は2013年に東京大学大学院教育学研究科博士課程を修了し、東京家政学院大学准教授を経て2016年から現職を努めている。内閣府「子ども・子育て会議」委員、厚生労働省「保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」委員等を歴任。また、野澤氏が所属するCedepは乳幼児期の発達と保育の実践、政策について研究するセンターとして2015年に設立されている。
本講話では、「これからの時代の子育て・保育」をテーマに、「非認知」「アタッチメント」の考え方を紹介し、人が育つ・人を育てる営みとはどのようなものかが話された。
野澤「Cedepでは、自治体や教育機関との共同事業として5歳から小学校4年生までの追跡調査を行ったり、ベネッセと共同で実施している『乳幼児の生活と育ち』研究プロジェクトなどに取り組んでいます。
まずは子ども政策の動向についてです。最近は『こども未来戦略』や『こども基本法』の制定、さらにはこども家庭庁の設立など、子どもに関する政策が大きく変化しています。とくに子どもの育ちにおいては、誕生前から100カ月間がウェルビーイングの基礎を築くとされており、この期間に何をすべきかというビジョンがこのたび明確に示されたことで、さまざまな政策の基本的な方向性に影響を与えているところです。
保育環境についても触れておきたいと思います。待機児童数の減少や1〜2歳児の保育利用率が飛躍的に増加している現状から、共働き家庭が増え、保育園を利用することが当たり前となっている社会の変化が見て取れます。こうした背景から、子どもを社会全体で育てようという動きも加速しており、子ども政策もその方向にシフトしています。
しかし、保護者の意識はどうでしょうか。データによれば、保護者の不安感は増しており、子育てに否定的な感情も増えていることが明らかになっています。制度が整えば保護者が満足するかと言えば、必ずしもそうではないかもしれません。重要なのは、配偶者だけでなく、周囲の人々からの『ソーシャル・サポート』が、保育を肯定的に捉える上で大きな影響を与えるという点です」

野澤「私たち人間の子育てには、祖父母や親戚、さらには血縁関係のない他者も関わってきました。これが人間の社会性の進化を促してきたと言えます。また、ジョン・ボウルビィの『アタッチメント理論』によれば、人は不安や恐怖を感じたときに、誰か特定の人に頼りたいという強い欲求を持つ傾向のことを「アタッチメント」と呼んでいます。
さらには『泣いたら抱っこしてもらえる』という理解が『いざとなったら助けてもらえる』という見通しにつながります。この見通しがあるからこそ、子どもは自発的に世界を探索できるようになり、成長していくのです。これは不安なことがあればあの人に会いたくなる、この人がいなくなったら深い喪失感を感じる、といった、私たち大人がもつ感情も同様です。実際に抱っこされなくても、そのイメージで安心感や心理的安全性を獲得できるようになります」
野澤氏は、乳幼児期に極めて大切なのは、乳幼児の学習の特徴である「発見学習」を大事にすることだと言う。発見学習とは、できるだけたくさんの可能性について、できるだけ幅広く調べることで世界の基本原則を学ぶことである。たとえば、子どもたちは、公園に出かけ、草の色や形、匂いなどを自らの目で確かめ、発見することによって学ぶ。「中でも、社会に関わる心の力や自己に関わる心の力といった『非認知能力』の育成が、子どもの成長には欠かせません」と続けた。保護者はどうしても読み書き計算など「頭の良さ」や「IQ」で表される心の力を示す認知能力を伸ばすことに関心が向くが、粘り強さや自尊心、社会性や協同性といった非認知能力を育むことが、生涯の発達にとって重要であるという。

野澤「私たちCedepでは、こうした力を育むための環境整備や保育の現場での支援のため、2021年に文部科学省委託調査として78例を収録している事例集をまとめました。その中でCedepセンター長の遠藤は『子どもが様々感情の当事者である時、それをいかに温かくかつしっかりと向き合い、共感的に受け止めて安心感を与えてやるかが重要』だと話しています。子どもが泣いているとき、その感情にラベリング(名付け)をしてあげたり、感情が生じた理由を解明・代弁してあげると、子どもは理解を深めていき、ひいては他者の感情も理解して思いやりを持てるようにもなります。遠藤は『非認知能力の発達の鍵は、自発的な活動や人との相互作用を、いかに豊かに展開できるかというところにある』とも話しています。この事例集にご興味がある方は、Webからのダウンロードも可能です。
子どもは周囲の人々や環境との相互作用を通じて学び、成長する存在です。乳幼児期には、遊びや生活の中で自ら物理的・社会的世界の原則を発見していくことが欠かせません。令和の時代に適した集団共同型子育ての在り方を探求し、子どもたちが日々充実した生活を送れるよう支援していくことが、私たちの使命だと考えています」
戦略的な最先端研究で紐解く、大昔の動物

続けて登壇したのは、東京大学大学院理学系研究科 准教授の平沢達矢氏。平沢氏は2010年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了し、理化学研究所基礎科学特別研究員・生命機能科学研究センター研究員等を経て2020年より現職を務めている。専門は古生物学と進化発生学の統合領域で、特に脊椎動物の形態進化について解明を進めている。
講話では「大むかしの動物の謎」をテーマに、過去に起こった進化を「どのようなアプローチで研究するのか」 「過去の動物とその進化過程について解明を進めることで何が理解できていくのか」などについて、実際の研究例を紹介しながら語られた。
平沢「幼い頃から図鑑に夢中だった私は、中でも『大むかしの動物』という図鑑に強く惹かれていました。その後は東京大学理学部地学科に進み、地球惑星科学を専攻。その後、発生学の研究をして、現在は東京大学大学院理学系研究科の准教授として研究室を持つに至りました。小学校6年生の頃、自室に掲げていた手書き看板の『古生物学研究所』が実際の研究室として実現したことに、自分でも感慨深いものがあります」

平沢「私の研究室には、かつての私と同じように恐竜の研究に情熱を燃やす学生も多く集まります。一方で、恐竜よりもっと古い時代の古生物の研究にはさらにおもしろい世界があります。従来の古生物学の世界では『現在は過去を解く鍵である』と言われますが、私の研究室ではむしろ『過去は現在を解く鍵である』という考え方を重視しています。現在は見られないかたちを持っていた生物のことや、大量絶滅のような実験ができない現象を調べないと、進化のメカニズムの解明、そしてその先にある未来予測はできないからです。
さて、脊椎動物の進化は、5億2000万年前から4億年前にかけて急激に進みました。骨、顎、そして手足という特徴は、この期間の進化で獲得されたものです」
平沢氏は、この進化の黎明期には、それまでなかった顎や手足が新たにでき、今日の私たちの体の基盤が築かれ、進化の過程で特に重要な局面だったと語った。

平沢「近年、私たちの研究室では、その進化の黎明期、約3億9000万年前のデボン紀に生息していたパレオスポンディルスという動物に注目しました。スコットランドの湖だった地層から発見された化石に基づいて研究が進められてきたパレオスポンディルスですが、その正体は長らく不明でした。パレオスポンディルスには歯がなく、鰭の痕跡も見られない一方で、背骨を持っているという、一見ちぐはぐな特徴を持っています。このため、他の脊椎動物との比較が難しく、正体解明は困難を極めていました。
私たちは、まず最適な化石標本を見つけ出すことから研究を始めました。2000点以上の化石を探してようやく2点だけ見つけることができ、次に『SPring-8』という放射光施設で、シンクロトロン放射光X線マイクロCTを使って詳細な観察を行いました。この技術により、パレオスポンディルスの骨格の微細な特徴を初めて正確に捉えることができ、それをもとに系統解析をすると、この動物がヒレから手足への進化を遂げた系統に属することが明らかになりました。この研究成果は『ネイチャー』にも掲載され、私たちの研究が国際的に高く評価されることとなりました」

出典:理化学研究所 https://www.riken.jp/press/2022/20220526_1/index.html
平沢「先月、カナダで開催された国際初期脊椎動物シンポジウムでは、私たちの研究成果を発表し、世界中の専門家とのディスカッションやコラボレーションの機会を得ました。これらの活動は、研究室での仕事と同じくらいか、あるいはそれ以上に科学の進展に寄与しています。学会の前後に行われる研究者同士の交流やディスカッションが新たな発見を促すことも頻繁にあり、それぞれが自国に帰ったあとはコラボレーションについてチャットアプリなどを活用して、カジュアルなコミュニケーションの中で約束を取り付けたりもしています。
最後に、私たちの研究は単に学術的な意義をもつだけでなく、一般の人々、特に子どもたちにも興味を持ってもらえるよう発信していく必要があると考えています。最近はNHK Eテレの「サイエンスZERO」にも出演し、パレオスポンディルスについてお話ししました。科学とエンターテイメントを結びつけることで、もっと多くの人々に進化研究の面白さを知ってもらいたいと考えています。
また、私の研究室を世界最高水準に引き上げることも一つの目標です。先日カナダで行われた国際学会は、次回はモロッコ、その次はスウェーデンで開催されますが、その次、5年後の2029年。日本で私が主催して、さらに多くの研究者と協力して進化の謎を解き明かすことができるよう取り組んでいきたいと思っています」
都市と人の持続可能なまちづくりを実現するために

もう一つの会場「ADRIFT by David Myers」で登壇したのは、東京大学先端科学技術研究センター共創まちづくり分野 特任助教の古賀千絵氏。千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専攻を修了し、シャリテ医科大学(ベルリン)研究員、千葉大学予防医学センター特任研究員を経て、2022年より現職を務めている。専門は社会疫学で、都市とウェルビーイングや暴力・ストレスとの関連について研究を展開している。古賀氏は、「都市と人の持続可能なまちづくり」をテーマに、環境と健康の関連についてどこまで明らかにされているのか、環境と人の双方が健康な未来の可能性について、社会疫学の視点で講話を行った。
古賀「私が研究している社会疫学という分野は、健康が個人の遺伝的要因だけでなく、その人のライフスタイル、社会的ネットワーク、経済状況、さらには住んでいる環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合って決定されるという考え方に基づいています。産業革命期のロンドンで劣悪な住環境が生まれたという歴史的史実からも、都市計画と公衆衛生がどれほど密接に関わっているか、おわかりいただけることでしょう。イギリスの医師であったジョン・スノウが行ったコレラマップの研究においても、コレラの発生源を地図上に示していくと、その感染源は井戸の給水ポンプであったと判明しました。これも、公衆衛生と都市づくりの関係を理解する上で非常に示唆に富んだ事例です」

古賀「続いて、どのようなまちが人々の健康とウェルビーイングに寄与するかについてお話しします。ヨーロッパでは近年、ウォーカブル(歩きやすい・歩きたくなる)なまちづくりが進んでおり、これが人々に良い影響を与えていることが科学的に証明されています。また、イギリスのソルテアという街が、ゼロ次予防の成功例として紹介できるでしょう。この街では、住民が意識的に健康を保つ努力をしなくても、住むだけで疾病リスクが軽減される環境が整えられています。このような『環境を改善することによる予防』は、現代においても非常に重要です。日本でも、『健康日本21』の第三次計画が2024年4月から施行されており、個人の努力に依存することなく暮らしているだけで自然に健康になれるような環境づくりが進められています。
この『健康日本21』の第三次計画に寄与している可能性が高い研究の一つが、私が参画するJAGESプロジェクトです。このプロジェクトは、日本全国の65歳以上の高齢者を対象に、介護ニーズを明らかにすることを主軸に、彼らの健康状態や生活環境などの関係が検証可能なデータで、認知症や要介護リスクの低減に寄与する要因を検証できるデータを収集しています。特に、ウォーカブルな環境や緑豊かな地域に住むことが健康に寄与することが明らかになっています。これらのデータは、日本の団地のような近隣に配慮しながら計画された居住環境が、健康に良い影響を与える可能性を示しています」

講話では、都市計画の効果を検証した事例として、バルセロナのスーパーブロックプロジェクトについても紹介された。このプロジェクトでは、街全体が歩行者優先の設計となり、交通量の減少や大気汚染の改善、パブリックスペースの増加が実現された。このような取り組みは、健康と環境の両方に良い影響を与えることが確認されているという。古賀氏は最後に今後の展望で締めくくった。
古賀「今後の展望として、人間が都市にどのような影響を及ぼしているのか、そしてその逆も含めて考えることが重要だと考えています。近年ではとくに『プラネタリーヘルス』という概念が注目されています。これは人間の健康だけでなく、地球環境全体の健康を考慮する必要があるという考え方です。
私たち研究者には、持続可能なまちづくりを実現するために、データを基にした政策を推進し、次世代に良い環境を引き継いでいく責任があります。さらには、研究から得られた結果を人が行動しやすい数値目標などに示し直す作業も必要不可欠だろうと考えています。
国民全員に同じまちづくり政策を施しても、その根底にある格差にアプローチできなくては意味がありません。そういった政策に陥ることのないよう、複合的・継続的に収集したデータを活用しながら公衆衛生施策を踏まえたまちづくりを実行しないといけないと思っています。今後も地域の資源を最大限に生かすべく、産官学民が一体となってより多くの仮説を検証していく必要がありそうです」
ハイブリッド・ワークの分析から見る、時間展望と創造性

続いて登壇したのは、東京大学大学院経済学研究科 准教授の稲水伸行氏。稲水氏は2003年に東京大学経済学部卒業し、08年に同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。筑波大学ビジネスサイエンス系准教授を経て、2016年より現職を務める。専門は経営科学、組織行動論で、近年は特に職場の物理的環境や人事施策が、どのようにクリエイティビティにつながるのかを研究している。
今回は「時間展望と創造性:行動データによるハイブリッド・ワークの分析」をテーマに、どのような時間と場所の使い方がクリエイティビティにつながるのか、さらには、これからの時代に求められる時間展望と働き方、さらには組織マネジメントのあり方について考察した。
稲水「近年、日本企業の働き方が大きく変わりつつあります。コロナ禍や働き方改革の影響により、従来のオフィスでのフルタイム勤務から、在宅ワークと組み合わせたハイブリッド・ワークが普及しつつあります。
かつては新卒一括採用と終身雇用が日本企業の特徴とされていましたが、現在では人材が流動化し、プロジェクト型の働き方や副業も一般的になっています。これにより企業内の組織やチームのあり方が大きく変わり、時間や空間を超えて柔軟に働ける『ネットワーク型』の働き方が求められるようになりました。
私は博士課程の頃から、こうした変化を念頭に置いて研究を進めてきました。この10年間はとくに『オフィス学』に注力し、産学連携での研究を続けています。オフィスというと、デザインやレイアウトなどの物理的な側面が注目されがちですが、私はICTや人材管理(HRM)デザインなどと組み合わせたワークプレイスの総合的な研究が必要だと考えています」

稲水「オフィス形態の変遷についても触れます。従来の固定席に代わり、2000年代からはフリーアドレス、さらに2010年頃からはABW(Activity-Based Working)という、業務内容に応じてオフィスをゾーニングする方式が登場しました。例えば、カフェスペースや集中スペース、WEB会議専用個室などが設けられています。慶應大学の研究者と行った共同研究では、単なるフリーアドレスよりもABWの方がクリエイティビティを向上させることが明らかになりました」

稲水「次に、テレワークと自己決定度の関連についても研究しました。テレワーク勤務者からは、自由裁量性や自立性を実感しているとの声が多く寄せられ、この点が働き方にポジティブな影響を与えているとわかりました。今年は再びオフィス勤務が増えていますが、例えばApple社では新しいオフィスを導入しつつ、週3日のオフィス勤務を推奨しています。CEOのティム・クック氏は、対面でのコミュニケーションが生む活気やエネルギーを重視していますが、一方で従業員からは自由度の低下に対する不満が出ているのも事実です。このような状況下で、ハイブリッドワークの最適な配分を模索することが課題となっています」
稲水氏らがABWを取り入れている企業で従業員の行動データを収集し、オフィス内での移動と創造性の関係を調査したところ、移動が中程度である場合に最もクリエイティビティが高まることが判ったという。例えば、出社日数が少なく移動性が低かった従業員はクリエイティビティの自己評価が低く、逆に出社日数が多く様々な場所を利用していた従業員は自己評価が高かったという。最後に今後の研究の方向性を述べ締めくくった。
稲水「最後に今後の研究の方向性として、未来や過去に対する見通しをもつ『時間的展望』の重要性を強調したいと思います。ミンツバーグが『マネジャーの仕事』において『優れたマネージャーほど、多様かつ頻繁な対人接触がある忙しない働き方をしながら、次々と流入する情報を相互に関連づけながら細かな決定を下す』と謳い、コッターが『ビジネスリーダー論』において『優秀なビジネスリーダーは20年ほど先を見据えて、中期的・短期的なアジェンダを描いている』と結論づけているように、私自身も時間的展望を前提にした自律的かつネットワーク型の働き方が、今後の企業にとって必要不可欠であると考えています。今後も行動データを基に研究を進めて、より良い働き方の提案を目指していきたいと思っています」




 アカデミア
アカデミア