日米双方でのR&D経験者が語る、創薬シーズを社会実装へ導く「先導者」の重要性
NEW読了時間:約 10 分
This article can be read in 10 minutes
かつては創薬先進国と呼ばれていた日本。2008年時点ではアメリカに次ぐ医薬品創出数を誇っていたが、2022年には6位までランクダウンするなど、近年はその影を潜めている(※)。COVID-19ワクチンに代表されるように、海外ではスタートアップによる新薬開発が主流となってきているが、日本はその動きに後れを取っている形だ。
「日本は、基礎研究を得意とするアカデミアサイドと、応用研究を主に担う事業サイドをつなぐ橋渡し役がいないのが問題」と話すのは、Flox Bio 代表取締役の山本 憲幸氏。Flox Bioはアカデミア研究と事業応用を引き寄せ、事業化を加速させることを目的とした民間型研究所だ。
これから日本で、影響力のあるスタートアップを創出するには何が必要なのだろうか?アメリカ・日本両国で研究開発経験を持つ山本氏に語ってもらった。
(※)医薬産業政策研究所「世界売上高上位医薬品の創出企業の国籍-2023年の動向-」より

山本 憲幸
Flox Bio 代表取締役
国内大手製薬会社の本社R&D戦略部にて、フォーカスエリアの戦略立案・各R&D部門における実行リードを担当。ベンチャー外部案件の評価を担当し、USの複数のベンチャー企業のライセンス・買収を成功に導く。その後、米国マサチューセッツ州ケンブリッジのバイオベンチャーに出向。創薬研究プログラムの複数の創薬支援研究機関を活用したプロジェクトを推進する。2022年よりエンジェル投資のNewsight Tech Angelsの創業メンバー。同年、Flox Bio創業。2009年に京都大学大学院にて博士(薬学)取得。
ポイント
・臨床までに巨額の資金を要する創薬領域において、日米では調達額に1〜2桁の開きがあり、日本は小規模にとどまっている。またアメリカではシリアルアントレプレナーがスタートアップを牽引しているが、日本はその担い手が不足している。
・アメリカのスタートアップにおける研究は、基礎研究による新発見の探索ではなく「どのリスクを取るか」を判断する社会実装のための手段として機能している。
・基礎研究から応用研究・実証実験に至るまでのスキマを埋める人材の不在が、日本から創薬スタートアップが生まれにくい大きな要因。Flox Bioは、その役目を担うために立ち上がった民間型研究所である。
・日本において、アカデミアが持つ創薬シーズを社会実装に導く「橋渡し」に最も適しているのは、企業で長年の経験を培ってきた研究者たち。知見を活かした社会貢献が、イノベーションの鍵となりうる。
・最後に物事を動かすのは人間関係。民間企業の出身者がアカデミアと共に汗をかき、リスクを分かち合って創薬に挑む姿勢こそが、革新的な創薬スタートアップを生み出す。
INDEX
・日本の創薬におけるボトルネックは「橋渡し役」の不在
・同じリスクを背負って並走する、Flox Bio流の創薬支援
・創薬スタートアップの成功の鍵は、企業の研究者が握る
・事業者がアカデミアと一緒に汗をかくことで、革新は生まれる
日本の創薬におけるボトルネックは「橋渡し役」の不在
――創薬を取り巻く環境は、アメリカと日本でどのような違いがありますか?
山本:まず大きく違うのが資金調達力です。創薬には、着想を得てから臨床に入るまでに何十億円という資金が必要になります。アメリカの場合、初めの段階で数百億円規模の資金調達を達成する企業も出てきていますが、日本の場合はそれが数億円にとどまることもしばしば。金額が1〜2桁違うんです。
加えて、日本は創薬スタートアップを担える人材も不足しています。アメリカでは、スタートアップを連続して起業するシリアルアントレプレナーが、創薬の最前線を牽引しています。もはや「創薬はスタートアップが担い、大手製薬会社はそれを買収してポートフォリオを組む」という流れが通例になってきているんです。
また、渡米して実感したのが研究に対する考え方の違い。「薬(クスリ)の反対はリスク」なんて言葉もあるとおり、そもそも医薬品にはリスクがつきものです。研究というと、「今までにないものを発見するためのもの」という基礎研究のイメージが強いと思いますが、アメリカのスタートアップにおける研究は「どのリスクを取るかの判断材料を見つけること」が目的になっています。つまり、研究の照準が社会実装に向いているんですね。
何が言いたいかというと、0→1を作る基礎研究と、1→100を作る応用研究や実証実験は全く別物であるということ。アカデミアの方々は基礎研究は得意ですが、その先の研究や実験にはあまり明るくありません。1→100を支えるのがスタートアップの役目であり、それを担う人材が今の日本には非常に少ないのです。日本にも十分な量のシーズがありますが、それが社会実装されないままとなっています。
――創薬シーズがあるにも関わらず、うまく芽が出ない要因はどこにあるのでしょうか?
山本:0→1を担うアカデミアと、1→100を担う事業者の間を埋める人材がいないことが、大きな要因だと考えています。
アカデミアの机にはたくさんの論文が積み上げられていて、そこに多くのシーズが眠っています。企業で研究を行っている方々はその論文を読める状況にあり、かつ1→100を担うポテンシャルやノウハウも持っていますが、企業の中にとどまっていてはアカデミアの生の声や状況は把握できません。その結果、せっかくの論文も放置されたままとなってしまうのです。
アメリカは、ハーバード大学やMITのすぐ近くに巨大創薬クラスターがあるように、アカデミアと事業者の距離感が非常に近いのが特徴。1つのスタートアップが爆発的な成功を収めたことで、その周辺に新たな企業が連鎖的に生まれていき、クラスターとなった事例が多いようです。
とはいえ、日本のカルチャーを考えると、今後アメリカのようなクラスターが誕生する確率はそこまで高くないように思います。

――では、突出したスタートアップを日本から輩出するには何が必要だと考えますか?
山本:海外勤務を経験した後、「日本は社内の説得に時間がかかる」「アメリカの自由な環境が恋しい」と言って再び海外に戻ってしまう人の話を、皆さん一度は見聞きしたことがあると思います。スタートアップはそんな海外の労働環境とよく似ていて、いい意味で大きな責任・裁量を自らが背負うことになります。
研究者の方々が、そんな裁量の大きな仕事に挑戦したいと思える環境を作ること、そして、もし失敗して責任を負うことになっても安心なセーフティーネットを用意すること。この2点がとても重要ではないかと、私は考えています。
同じリスクを背負って並走する、Flox Bio流の創薬支援
――Flox Bioは、創薬領域でどのような役割を務めているのですか?
山本:アカデミア研究と応用研究の間にあるスキマを埋めて、効率的な事業化を促すアクセラレーターのような役目を担っています。アカデミアの先生方が持つシーズを、社会実装に至るまで育てるのが私たちのミッションです。
ビジネスモデルとしては、イノベーターとの接点を探している企業にアカデミアの方々を紹介したり、企業の研究者に当社へ出向いただいてノウハウを提供したりといった支援で対価をいただき、それをアカデミアに回す形です。
私たちが特に大切にしているのは、アカデミアや企業の研究者の方々と同じ目線で創薬に挑むこと。外野から口だけ出すようなサポートではなく、一緒に責任を背負う当事者として社会実装を目指すのです。アカデミアの先生方に代わって、応用研究のためのデータ取得を引き受けることもよくあります。伴走支援とも違う、“共創型支援”がFlox Bioの特徴です。

――先ほど「0→1を担うアカデミアと、1→100を担う事業者の間を埋める人材がいない」という話がありましたが、そうなるとFlox Bioの事業も拡大が難しいのではと感じました。
山本:そうですね。だからこそ、Flox Bioのコアメンバーだけでなく、企業から出向されている方々の存在が大きな力となっています。所属企業で培った経験や知識を、一部当社でのプロジェクトに割いていただいているんです。日本から創薬スタートアップを生み出すには、このやり方が最もフィットしているように思います。
――アカデミアサイドと並走して創薬するとなると、医薬品の系統も絞られてくるのでしょうか?
山本:ある程度系統は絞るようにしています。とはいえ、私たちもさまざまなネットワークを持っているので、足りないピースは各エキスパートと協業することで埋めるようにしています。
特にアカデミアの先生方に不足しがちなのが、資金調達のためのデータです。先生方は論文を書くためのデータ取得は得意ですが、投資家や企業を納得させるためのデータ取得は不得意なんですね。
資金調達のためのデータには、大きく2つあります。1つは再現性を証明するデータ、もう1つは競合との比較データです。競合比較については「現在は存在しない薬を作るのが創薬なのに、競合のデータは取れるのか?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。
ただ、まだ社会には出ていなくても、臨床試験中の医薬品や開発中の医薬品に、注目すべき競合が存在する場合があります。そういった水面下の情報は、アカデミアにはなかなか入ってこないんですね。私たちはその情報も踏まえた上で、ビジネスとして勝つための「刺さる」データをそろえるのです。
創薬スタートアップの成功の鍵は、企業の研究者が握る
――Flox Bioを創業した経緯について教えてください。
山本:私は、日本の製薬会社が、国内ではなくアメリカの企業ばかり買収している点に違和感を持っていました。海外企業が日本のエコシステムに全く貢献していないとは言いませんが、日本産業を発展させたいはずの企業が、なぜ国内企業と手を取れないのかとジレンマを感じていたんです。
その一方で、バイオベンチャーへの出向で滞在したアメリカでは、日本の研究者同士の交流が盛んに行われているのを目の当たりにしました。あるとき、アメリカの医学部に留学している方と話したことがあったのですが、たとえ医師であっても創薬となると分からないことがたくさんあるようで、少しアドバイスしただけですごく感謝されたんです。そこで「自分たちにもできることはまだたくさんある」と自覚したと同時に、研究者たちがお互いの垣根を越えて対話することが、いかにイノベーションの創出に不可欠か、ということも痛感しました。
異質なカルチャーにもっと触れてみたいという思いから、新卒から勤めた会社を退職。そしてFlox Bioの立ち上げに至りました。

――日本企業は、イノベーションの創出に向けてどう立ち回ればよいのでしょうか?
山本:埋もれたままになっている基礎研究を引っ張り上げる方の存在が、今後の鍵を握ります。アカデミアの研究者と手を取って、創薬を進めていける方ですね。そのノウハウや経験値を持っているのは、やはり大企業の研究者の方々だと思います。プロボノのような形で参画いただけたら、こんなにありがたいことはありません。特にPh.D.(博士号)を有している方は、非常に貴重です。
――アメリカではPh.D.を活かしてビジネス的成功を目指す人も多いと思いますが、日本だと「研究者がお金儲けをするなんて」と、難色を示される風潮もあるように思います。
山本:そうですね。そのような時代があったのは間違いないと思います。ただ、現在は流れが変わってきていて、若い研究者はむしろ「お金がなければ社会実装に至らないよね」という共通理解が広がってきているように思います。社会貢献と収益性を両立することが重要だと、皆さん感じているようです。
その一方で、やはりアカデミアの先生方が最も時間を費やしたいのは、やはり基礎研究の部分です。だからこそFlox Bioは、先生方が基礎研究に集中できるよう、応用研究や実証実験の過程に、責任を持って協創したいと考えています。
アカデミアの知の最前線と、とことん膝を突き合わせて議論ができる環境なので、「とにかく面白いサイエンスに触れたい」という方には堪らないと思います。少しでも興味がわいた企業の研究者の方がいらっしゃったら、ぜひ当社にご連絡いただきたいです。
――その他、Flox Bioとして今後どんな人と協業していきたいですか?
山本:創薬のプロジェクトをリードした経験を持っていて、各過程で「次にどんな失敗が待ち受けているか」をある程度予測できるような方々とぜひお話ししてみたいです。スタートアップを立ち上げた場合、CSO(最高科学責任者)やヘッド・オブ・リサーチといった役職に就く方々をイメージしています。
――「CSOレベルのハイクラス人材が、スタートアップを魅力的に思うのか?」という懸念を少し感じました。
山本:確かに、すべてのCSOレベルの人材に対して、魅力的なキャリアとは思ってもらえないかもしれません。ただ、大企業で積み重ねてきた経験値を最もフル活用できるのが、スタートアップだと私は強く思うのです。際限のない裁量権を持ち、自由な発想で創薬に挑める環境での創薬は、想像以上の面白さとやりがいを感じるはずです。
事業者がアカデミアと一緒に汗をかくことで、革新は生まれる
――将来的に、どんな社会の実現を目指されていますか?
山本:当社のような存在が、要らなくなる社会です。つまり基礎研究がごく自然に応用研究・実証実験へと展開されていく、エコシステムが真に根付いた社会を目指しています。
その実現のために不可欠なのが、組織に縛られず、もっと自由に「個」が動ける風土です。今の日本は、まだ個人で動くことへの心理的ハードルが高いように感じます。自己紹介する際も「◯◯会社のタナカです」といったように、必ず所属組織の名前が頭に来ますよね。組織の肩書きに頼らずに動ける人が増えれば、組織間に壁がある日本ならではの閉塞感も、少しずつ解消されていくはずです。
今後、注目のスタートアップが生まれていけば、そのプロジェクトに関わった「個人の名前」が広く知られるようになります。そうなれば、所属企業ではなく個人にもフォーカスが当たりやすくなるのではないでしょうか。
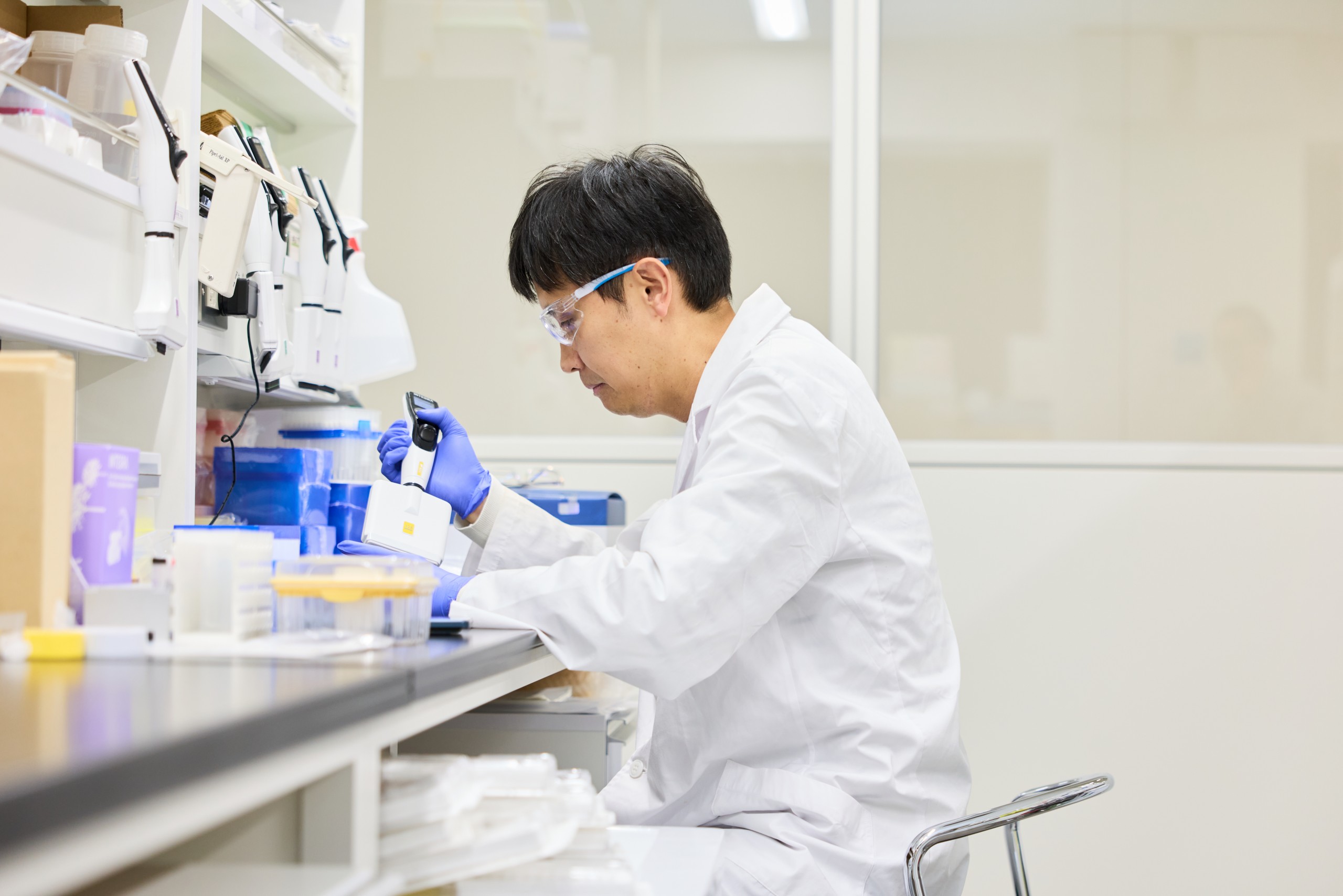
――日本の創薬領域が真に国際的な競争力を持ち、イノベーションを量産していくための、「決定的な鍵」は何だと思われますか?
山本:民間企業がアカデミアと共に汗をかき、リスクを分かち合って創薬に挑む。そうした「本気の姿勢」こそが、今最も必要なものだと私は考えています。
多くの企業がイノベーションを求め、LP出資やCVCの設立に動きますが、単に資金を投じるだけでは大きな見返りは期待できません。資金と共に、経験豊富な「人材」を現場に送り込むこと。これは、私がアメリカ時代に得た最大級の学びです。
アメリカはビジネス至上主義でドライなイメージがありますが、実際は案外ウェットです。当たり前な話ですが、魅力的なシーズを見つけたとき、人はまず誰に相談したいと思うでしょうか。きっと誰しもが、「同じ釜の飯を食った」信頼できる人の元に向かいますよね。なぜなら自分の志や経験を深く理解してくれている人と手を組むことが、成功への最短距離だからです。
結局のところ、最後に物事を動かすのは人間関係。何かを得たいのであれば、相応のギブが必要になります。Flox Bioがアカデミアの先生方と向き合う際も、「まず提供すべきはお金ではなく、社会実装に向けた情報やノウハウのインプットである」という考えを全社の共通認識としています。
そんな「信頼関係に基づくチームプレー」が当たり前になれば、日本から世界的なイノベーションが生まれる日も、そう遠くないと確信しています。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:できるくん
撮影:河合信幸




 TIP
TIP 








