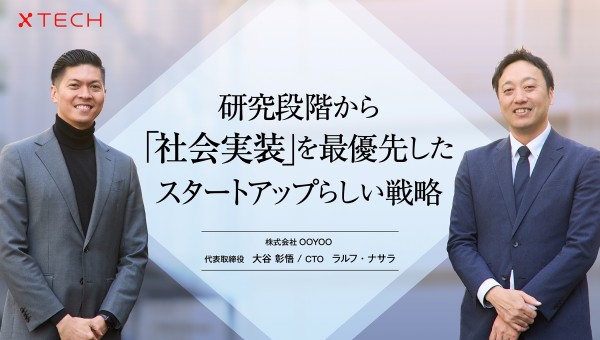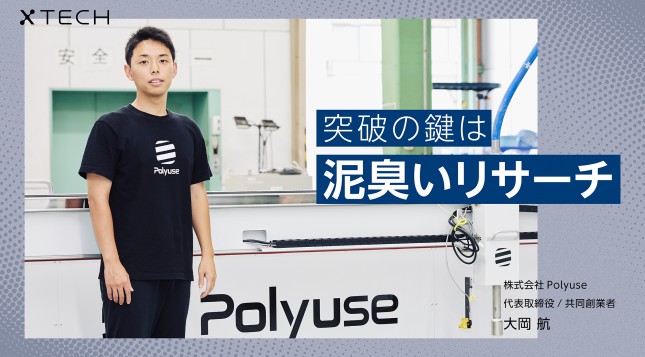0 Clubが丸の内で切り拓く日本のクライメートテックエコシステム――地域発のディープテック企業を大企業と世界に繋ぐ
読了時間:約 13 分
This article can be read in 13 minutes
2050年[1]のカーボンニュートラル実現に向け、世界中でクライメートテック分野への投資が加速している。しかし日本では、スタートアップの数も投資規模もグローバルで見ると相対的に小さく、成功事例も少ないのが現状だ。そうした状況では、スタートアップ、大企業、VC、研究者が有機的につながる“エコシステム”をどう構築するかが問われることとなる。
エコシステム構築の一助になることを目指すのが、三菱地所が手がけるクライメートテック特化型インキュベーション施設「0 Club(ゼロクラブ)」だ。大企業が集積する東京・丸の内を拠点に、技術を持つスタートアップと、それを求める企業や投資家をつなぎ、日本ならではの産業基盤を活かした市場形成を目指している。
今回取材したのは、0 Clubの仕掛け人である曽我氏、そして施設のパートナーVCであるArchetype Venturesの北原宏和氏、環境エネルギー投資の石田ともみ氏。エコシステム構築に挑む彼らに、日本のクライメートテック市場の現状と、0 Clubが果たそうとしている役割について話を聞いた。
[1]日本・EU・アメリカでは2050年、中国・ロシアは2060年にカーボンニュートラルの実現を目指している。

写真右)曽我真吾
三菱地所 イノベーション施設運営部
同中)石田ともみ
環境エネルギー投資 インパクト・オフィサー/キャピタリスト
新卒で電通に入社し、営業局にてグローバルのブランド変革等を担当。その後、国連開発計画にてSDGsビジネスやスタートアップ支援に携わる。英国留学後、EY本社ロンドンの戦略部門 ParthenonにてClimate tech等の案件を担当。2023年に環境エネルギー投資に参画し、インパクト戦略の構築とマネジメント、国内外の投資業務を担当。
同左)北原宏和
Archetype Ventures パートナー
東京大学法学部、Carnegie Mellon University Heinz College of Public Management, University of Southern California Gould School of Law卒業。総務省にて地域活性化、ボストン コンサルティング グループにて情報通信、金融、製造などの幅広い業種での中期経営計画策定、新規事業開発プロジェクト経験を経て、Archetype Venturesに参画。
ポイント
・現状では、日本のクライメートテック市場は世界に遅れを取っている。2050年カーボンニュートラル実現へ向け、三菱地所「0 Club」が丸の内からエコシステム構築に挑む。
・丸の内は大企業の集積地であり、GHG削減ニーズとスタートアップの技術実装を物理的距離で繋ぐ最適な場所。政府の2000億円予算も追い風となり、市場形成を加速させる。
・日本がグローバルで勝つためには、海外技術の導入だけでなく、素材化学などの既存産業基盤とノウハウを活かした独自の競争力を持つ新産業の確立が鍵となる。
・クライメートテックの成功には、起業前の綿密な準備と業界ネットワークの構築が不可欠。特に知財戦略の早期検討と、専門家による適切な支援がグローバル競争力を左右する。
・現状、日本にエコシステムは未確立だが、0 Clubは「マーケット創出」を役割としている。技術を持つスタートアップ、導入企業、投資家が集まる場を作り、人・モノ・金の循環を促すことを目指す。
INDEX
・「丸の内から未来を変える」三菱地所が挑むクライメートテック支援の最前線
・「共創」によるエコシステムづくり──0 Clubで行うパートナー制度の狙い
・エコシステムよりもまず“マーケット”を──0 Clubが担う土台づくりの役割
・知財が競争力を左右するクライメートテック。日本が解決すべき課題とは
「丸の内から未来を変える」三菱地所が挑むクライメートテック支援の最前線
――まずは0 Clubについて教えてください。
曽我:0 Clubは、クライメートテック領域のスタートアップ支援などを通じ、カーボンニュートラル達成に貢献するために設立されたインキュベーション施設です。スタートアップを中心に、VCをはじめとした金融機関、スタートアップとの協創を望む大企業、そしてルールメイキングに携わる行政機関など、クライメートテックに関わる全てのプレイヤーが集い交流することをきっかけに、この領域に次々と企業が増え、成長し、産業が発展していく、所謂“エコシステム”を構築することを目的としています。
スタートアップにはただオフィスを提供するだけではなく、顧客候補や金融機関との接点を提供するなど、彼らの売上や資本に貢献することを意識しています。現在、開業から半年ほどが経過し、まずはスタートアップの集積を進めながら、大企業との連携を深めることに注力しています。
――なぜ丸の内で、なぜこのタイミングなのでしょう。
曽我:丸の内に拠点を構えた理由は、多くの大企業が集積していることが要素として挙げられます。大企業は、相対的に多量のGHG(温室効果ガス)を排出する企業が多くなります。そのため、大企業にはGHGを削減する技術を持つスタートアップとつながりを持つ動機が生まれます。一方で、スタートアップの技術が社会に実装されるためには、大企業との協業が欠かせません。これらの要素に鑑み、物理的な距離が近く、自然と交流が生まれる丸の内は最適な場所だと考えました。
また、経済産業省が2024年4月から5年間で2000億円規模の予算を確保し、クライメートテック領域の活性化を進めるという動きがあったことも、タイミング的に重要な要素でした。政府の支援によって、クライメートテック分野の成長が加速すると期待されています。
――日本のクライメートテック市場の現状を聞かせてください。
曽我:世界のクライメートテック市場と比較すると、日本はまだ大きく遅れをとっています。北米や中国ではすでに巨額の投資が行われており、日本の投資規模はそれらの地域に比べると非常に小さいのが現状です。また、グローバルで影響力のあるクリーンテック企業のランキング(2025 Global Cleantech 100)においても、日本企業の存在感は薄く、ようやく今年「つばめBHB」という企業が1社選ばれたのみです。
しかし、日本の技術開発力自体は決して劣っているわけではありません。適切な支援があれば、グローバル市場で戦えるポテンシャルを持つ企業や技術は数多く存在します。そのため、日本市場の価値が薄れてしまう前に、スタートアップの成長を早期に支援し、競争力を高めることが不可欠だと考えています。

――そのような状況の中で、0 Clubはどのような取り組みをしていくのでしょう。
曽我:スタートアップと大企業の接点を増やすために、イベントなどマッチング機会を提供することから始めています。丸の内というエリアの特性を活かし、シード期のスタートアップが事業成長のきっかけを見つけられるような環境を整えています。
また、新たな試みとして東京大学の協力を得て「グリーンリスキリングプログラム」を開始しました。クライメートテック領域に関心を持つビジネスパーソンはまだ多くないため、このプログラムを通じて人材を育成し、スタートアップとの接点を増やすことを目指します。
――「グリーンリスキリングプログラム」は、どのようなプログラムなのでしょうか?
曽我:全13回のプログラムのうち、前半は各分野の専門家による講義とスタートアップによる取組み紹介を実施し、クライメートテック市場や技術トレンドについての基礎知識を身につけてもらう予定です。その後、ワークショップ形式でスタートアップの成長戦略を考える実践的な学習を行います。
特に、ビジネスパーソンだけでなく博士課程やポスドクの研究者もチームに加えることで、技術とビジネスの両面からアイデアを創出できる仕組みを構築していきます。技術的な視点を取り入れることで、新たな技術の組み合わせやプロダクトの価値向上など、多角的に検討できる場にしていきたいですね。
「共創」によるエコシステムづくり──0 Clubで行うパートナー制度の狙い
――0 Clubはパートナー制度を設けていますが、その背景を聞かせてください
曽我:0 Clubのパートナー制度は、クライメートテックのエコシステムをよりスピード感をもって構築するために設けました。私たちは不動産デベロッパーとして場所を提供できますが、それだけでエコシステムを構築することはできません。クライメートテック領域に取り組むスタートアップが増え、事業成長し、大企業と連携するためには、VCや業界の専門家、アカデミアとの協力が必要です。
特に、クライメートテックはまだ成功モデルが確立されておらず、この領域で投資活動を行うキャピタリストやスタートアップの数も限られています。そこで、異なるVCのキャピタリストが集まり、知見を共有する場を作ることが重要だと考えました。
具体的には、勉強会などのイベントを共催したり、スタートアップからの要請を受け資金調達の相談を受けて頂いたり、あるいはパートナーVCの投資先を0 Clubご紹介いただいたり、様々な取り組みを通じてパートナーと共にエコシステムを構築していきます。
――パートナーである北原さんは、キャピタリストとして日本のクライメートテック市場をどのように見ていますか?
北原:曽我さんの話にもありましたが、日本のクライメートテック市場は、カーボンニュートラル宣言から成長が加速したものの、アメリカやヨーロッパ、中国と比べるとまだ遅れています。グローバルではパリ協定の頃から投資が活発化し、日本よりも先行してきました。一方で、直近の気候変動対策への逆風は同市場への資金流入を細らせており、日本が追いつくチャンスでもあると感じています。
そして、事業という観点から日本が競争力を持つためには、単に海外の技術を導入するのではなく、独自の産業を生み出す必要があります。今、日本のクライメートテック市場は、新たな産業を確立できるかどうかの重要な局面にあると思います。

――日本の勝ち筋はどこにあるのでしょうか?
北原:日本が活路を見出すには、既存の産業基盤を活かし、グローバルで勝負できるレベルの新しい価値を生み出すことが鍵になると考えています。クライメートテックは日本市場だけでは成長の限界があり、自ずからグローバル展開が求められるからです。
たとえばですが、日本には素材化学などのものづくり領域で産業基盤とノウハウが残っています。これらを活用し、競争力を持つ領域を見つけることが、日本独自の戦い方になるでしょう。世界的なトレンドを踏まえ、日本企業が独自の強みを活かして市場に参入できれば、十分に勝機はあると思います。
――石田さんは、今の日本のクライメートテック市場をどう見ていますか?
石田:ヨーロッパでは規制と産業政策が結びつき、市場全体が大きく成長してきた一方で、日本では企業が脱炭素を開示義務のように受け止める傾向がありました。そのため、ビジネス機会として積極的に投資する企業が限られている面もありました。
ネットゼロの達成は事業によっては技術を導入すれば可能かもしれませんが、それだけでは新たな産業は生まれません。今後、日本市場が成長するためには、クライメートテックを環境対策だけではなく、経済成長のエンジンとして活用する視点が重要だと思います。
――石田さんが所属する「環境エネルギー投資」は、国内で長らくこの領域に投資していますよね。企業の姿勢も変わりつつあるのでしょうか?
石田:私たちは2006年から環境・エネルギー分野に特化した投資を行ってきましたが、当時に比べれば企業の姿勢も大きく変わったと思います。当時は『環境ビジネスで利益が出る』ことは主流ではなく、またクライメートテック(当時はクリーンテックと呼ばれた)市場が低迷した時期もありましたが、長期的な視点で投資を続けてきました。
電力や再生可能エネルギーのビジネスは規制の影響を強く受け、国内市場に閉じがちです。しかし、これからはよりグローバルな市場を視野に入れる必要があります。日本市場が活気づいているのは良い流れですが、企業が主体的にイノベーションを起こし、またグローバル市場も見据えて持続的に成長できる環境を整えることが、クライメートテック市場の発展には欠かせないでしょう。
エコシステムよりもまず“マーケット”を──0 Clubが担う土台づくりの役割
――日本にはクライメートテックのエコシステムが確立されつつあるのでしょうか?
北原:現状、日本にクライメートテックのエコシステムが確立されているとは言えません。グローバルでもまだ発展途上の分野であり、成功モデルが確立されたわけではないのが実情です。スウェーデンの「Northvolt」の例のように、高く評価されてきたものの、その後失敗するケースもあり、エコシステム以前にやっと選別が始まってきたというフェーズと言えるかもしれません。
エコシステムを構築するには成功モデルを生み出すことが不可欠ですが、過渡的にはその可能性を高めて行くためにもスタートアップや投資家だけでなく、大企業や大学が有機的に結びついていく必要があると感じています。グローバルな視点を持つ企業はシリコンバレーに入り込んでいて、日本のスタートアップよりも海外のスタートアップに目を向けており、国内の連携が十分に進んでいないという状況もあります。
また、クライメートテックは技術だけでは成功しづらく、どのようにビジネスを構築するかが重要になります。どの産業プレイヤーと連携し、どの市場でどのように展開するのか、戦略的に考える必要があります。そのため、若い起業家だけでなく、既存産業の知識、ネットワークを持つ人材の参画が成功の鍵となります。エコシステムを確立するためには、こうした人材がスタートアップに関わる仕組みづくりが必要だと思います。
石田:エコシステムの定義が難しいのですが、一つの要素として、シリアルアントレプレナー(連続起業家)の存在が挙げられます。例えばカリフォルニアでは、IPOやM&Aを経験した起業家が次のスタートアップを立ち上げたり、投資家として資金を供給したりすることで、エコシステムが活性化しています。しかし、日本ではこのような仕組みがまだ十分に確立されていません。
IT分野ではスタートアップエコシステムが少しずつ成長していますが、クライメートテックやディープテック分野ではまだプレイヤーが少なく、成功事例も限られています。ただし、日本でも新たなパートナーシップや試みが進んでおり、成功事例が増えればエコシステムが発展する可能性は十分にあるはずです。
ヨーロッパでもアメリカほどプレイヤーは多くありませんが、少しずつ市場が整ってきました。日本も現在は試行錯誤の段階にあり、様々なトライアルを繰り返すことが、次の成功につながると考えています。

――日本のエコシステム確立のために、0 Clubがどのような役割を果たすのか聞かせてください。
曽我:0 Clubが果たすべき役割は、日本におけるクライメートテックのマーケットを作ることだと考えています。なぜなら、作る人・売る人・買う人が集まり、取引が活発に行われる環境が整えば、自然と人・モノ・金が循環し、結果的にエコシステムが育つからです。
クライメートテック市場を成長させるには、技術を持つスタートアップ、大企業や自治体などの導入企業、投資家といったプレイヤーが増えることが必要です。0 Clubは、そうしたプレイヤーが集まり、互いに連携できる場を作ることを目指しています。
もちろん、私たちが直接事業をつくるわけではありませんし、すべての課題を解決する知見を持っているわけでもありません。しかし、市場が活性化し、多様なプレイヤーが関わることで、日本のクライメートテック産業全体が成長していくでしょう。そのための基盤を作ることが、0 Clubの使命だと思っています。
知財が競争力を左右するクライメートテック。日本が解決すべき課題とは
――クライメートテックスタートアップが成功するためのポイントを聞かせてください。
北原:クライメートテック領域で成功するためには、起業前の準備が非常に重要です。IT系スタートアップではスピードが鍵になりますが、クライメートテックでは業界ネットワークや知見の蓄積が成功の鍵になります。
たとえば起業の3年前から関連する業務に関わり、業界のキーパーソンとつながることで、スタート時にスムーズに事業展開ができるでしょう。投資家の立場から見ても、しっかり準備をした起業家は評価されやすく、資金調達の成功率も上がります。具体的に『こういう経験を積み、こういうチームで挑戦する』と説明できることが重要です。
一方で、勢いだけで起業しても、業界とのつながりが薄いと事業の立ち上げが難しくなります。クライメートテックは規制や産業構造の影響を強く受けるため、事前の準備と戦略的な動きが欠かせません。

――石田さんはどう思いますか?
石田:私も同じように、スタートアップの成功には技術だけでなく、起業家の求心力や業界とのつながりが重要だと考えています。特に、どれだけ業界のキーパーソンとネットワークを築けるかが事業の成長スピードを左右します。
私は以前、英国・ケンブリッジ大学に留学していましたが、そこには『シリコンフェン』と呼ばれるスタートアップのエコシステムがあり、大学・企業・起業家・投資家が密接に連携していました。ケンブリッジ大学には『ケンブリッジ・エンタープライズ』というスタートアップ支援組織があり、スタートアップの成長を促す仕組みが整っています。また、大学を中心としてエンジェル投資家からグロース投資家まで資金調達の流れが確立され、何か困ったときに頼れる環境があります。
――日本には、まだそのようなスタートアップ拠点が不十分だと。
石田:日本でも東大や京大を始め数々の大学が同様の仕組みを作り始めているので、期待しています。一方で、多くのディープテック系スタートアップは特許を持っていますが、それをどう活用し、特にグローバル市場で展開するかについての議論は不足しているように感じています。
ケンブリッジ大学でスタートアップ支援に携わっていた際には、早い段階で知財戦略について検討する機会がありました。大学と知財の権利関係を明確にし、適切に管理することが成長の鍵となるケースも少なくありません。歴史的には、大学が比較的寛容な知財戦略をとっていたために、多くのディープテック企業が活躍するエコシステムができたというレポートもあります。日本では、知財の取り扱いが後回しにされがちですが、企業にとってはどの技術を特許化し、どの技術をオープンにするかといった戦略が、長期的な競争力を決める要素になると考えています。また、大学などエコシステムを形成しているステークホルダーも長期的な産業政策、グローバルな企業を育成する視点で戦略を立てる必要があるかもしれません。

――北原さんは知財戦略について、どうお考えですか?
北原:日本では、研究者が特許を出願する際にビジネスの視点からの適切な支援が不足しています。たとえば国内で特許を取得しても、国際出願をしていなかったために、後から『これではグローバルでは戦えない』と気づくケースもあります。
当然ながら特許の取得にはコストがかかるため、大学側もどこまで対応すべきかの判断が難しく、戦略が明確でないと、必要な特許を逃してしまいます。グローバル市場といった際にも、どの国で特許を取得すべきか事業戦略に基づいて決めなければなりません。
欧米では、たとえばオックスフォード大学とロールス・ロイスが連携して、研究段階から事業人材を関与させ、技術の事業化を前提に戦略を立てています。また、各フェーズで異なる専門家が判断を行い、研究から事業化、ファイナンス、知財戦略まで役割を明確に分けています。日本でもこのような仕組みを整えることで、クライメートテックスタートアップがグローバル市場で競争できる環境が確立されていくはずです。
――どうすれば知財戦略の課題を解決できるのでしょう。
石田:知財の話をすべて起業家が自分で勉強し、対応するのは非効率です。欧米では、知財戦略に精通した専門家がいて、起業家が『この人に相談すれば、適切なアドバイスやつながりが得られる』という仕組みが確立されています。
クライメートテックのように技術が競争力の鍵を握る領域では、知財の扱い方が事業の成否に直結します。しかし、日本では適切なアドバイザーにたどり着けないことが課題となっています。
エコシステムとは、こうした問題を解決するための仕組みでもあると考えます。限られたリソースの中で、どこまで対応すべきかを判断できる専門家がいて、彼らとスムーズにつながれる環境があることが、エコシステムの本質的な価値ではないでしょうか。0 Clubには、そのような場になってもらうことを期待しています。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:鈴木光平
撮影:阿部拓朗




 0 Club
0 Club