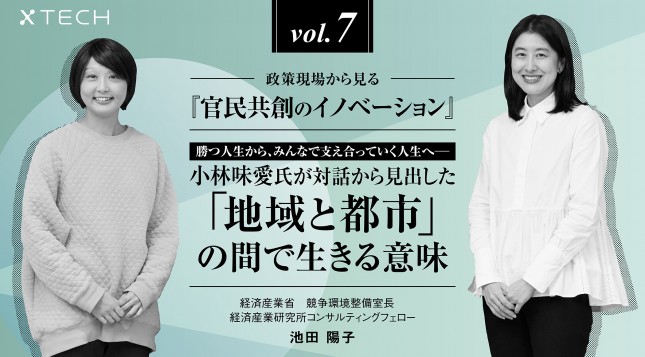発電効率が最大8倍になるケースも!バイオマス発電の常識を覆すライノフラックス
読了時間:約 8 分
This article can be read in 8 minutes
エネルギー分野における技術革新が進む中、動植物から生まれる生物資源(バイオマス)を原料として電気を生産する発電、バイオマス発電は環境負荷を軽減する「カーボンニュートラル」な解決策として注目されてきた。しかし、その潜在能力を最大限に引き出すには、従来の技術では解決できない効率性やコストの壁も存在する。
そんな中、京都大学と連携し、革新的なバイオマス発電技術を開発して注目を集めているのがライノフラックスだ。バイオマスを「燃焼させずに」電気に変えるというアプローチを実現し、小規模でも高効率な発電が可能にした。さらには、発電過程で発生するCO2を高純度で回収・再利用することで、バイオマスの新しい価値を創造している。
今回は同社代表の間澤敦氏にインタビューを実施。三菱商事のCVCでのキャリアを重ねていた同氏が起業を決意したのはなぜなのか。同社が目指す分散型エネルギー社会とは何なのか。ライノフラックスが切り拓く次世代のエネルギー革新、その最前線に迫る。

間澤敦
ライノフラックス株式会社 代表取締役CEO
大学卒業後、三菱商事に入社。金属資源グループに配属となり、ドイツ駐在を含む計5年間にわたりニッケルの貿易業務に従事。2019年10月からは三菱商事社内のベンチャーキャピタルに異動し、米国やイスラエルをはじめとする海外スタートアップ企業への投資実行・成長支援・エグジット、またスタートアップ企業との協業を通じた新規事業開発を遂行。2023年1月に三菱商事を退職し、同年2月から京都大学イノベーションキャピタルにて客員起業家(EIR)を経験。2024年4月にライノフラックス設立。
ポイント
・バイオマス発電は、動植物由来の資源(バイオマス)を活用して電気を生み出す発電方式。植物は光合成をして大気中のCO2を吸収するため、その後エネルギーとして利用しても、CO2の排出量が吸収量と相殺され「カーボンニュートラル」だとされる。
・従来のバイオマス発電は、大量のバイオマスを燃やさなければ十分な電力を得ることができず、コストが非常に高かった。対して、ライノフラックスの技術では、バイオマスが持つ化学エネルギーを極力熱に変えず、効率的に電気エネルギーへと変換するため、コストが抑えられる。
・現在は、食品工場や農業施設など、バイオマス資源が継続的に供給される現場において、エネルギーの地産地消モデルを確立を目指している。また、発電過程で生成される高純度のCO2を高付加価値で再利用する取り組みも進めている。
・間澤氏は、起業を「未来を創る権利」だと考えており、その権利を行使することには価値があると考えている。しかし、大企業にもそのチャンスは有るとも考えている。
INDEX
・バイオマス発電の「熱ロス問題」を克服し、経済性と環境性能を両立
・バイオマス発電革命!発電効率の飛躍的な向上とCO2の資源化でイノベーションを起こす
・1畳からはじまるバイオマス発電で分散型エネルギー社会を実現
・起業は「未来を作る権利」。トヨタの町で感じた「会社が人を支える」という理想像
バイオマス発電の「熱ロス問題」を克服し、経済性と環境性能を両立
――バイオマス発電がどういうものなのか教えてください。
間澤:バイオマス発電とは、動植物由来の資源、いわゆるバイオマスを活用して電気を生み出す発電方式です。たとえば木材や農作物の残渣、動物の糞尿など、再生可能な資源を燃やしたり、化学反応を利用したりしてエネルギーを取り出します。
従来の石炭や石油といった化石燃料は、掘り出した際に地中に埋蔵されていた炭素を大気中に放出するため、CO2排出の原因になっていました。一方でバイオマスは、植物が成長する過程で光合成をして大気中のCO2を吸収するため、その後エネルギーとして利用しても、CO2の排出量が吸収量と相殺されるため、「カーボンニュートラル」だと言われています。
資源として再生可能で、環境負荷が低いことから、クリーンエネルギーとして注目されてきました。
――以前から注目される発電方法だったのですね。なぜこれまで普及しなかったのでしょう。
間澤:発電効率が低く、発電コストが高かったからです。従来のバイオマス発電は、バイオマスを燃やして熱エネルギーを作り、その熱エネルギーを使ってタービンを回して電気を生み出すという古典的な手法でした。しかし、バイオマスは水分を多く含んでおり、石炭や石油のような高密度なエネルギー源に比べ、単位あたりの発熱量が小さくて。
その結果、大量のバイオマスを燃やさなければ十分な電力を得ることができず、コストが非常に高かったのです。また、バイオマスを収集・運搬する際のコストも課題となり、経済的な持続性に欠ける点も問題視されていました。

――環境によくても、経済合理性の面で課題があったのですね。
間澤:そうですね。その問題の根源は大量の熱が「熱ロス」として失われるためです。そもそも熱エネルギーは、電気エネルギーのように、効率よく利用するのが難しく、エネルギーとしての質が低いと言われています。
結果として、バイオマス発電は「クリーンだが非効率で高コスト」という評価となり、実用化には至りませんでした。しかし、私たちの技術はこの課題を根本から解決し、バイオマスのエネルギーを効率的に電力へと変換する革新をもたらす可能性を秘めています。
バイオマス発電革命!発電効率の飛躍的な向上とCO2の資源化でイノベーションを起こす
――ライノフラックスの技術について教えてください。
間澤:私たちの技術は、バイオマスが持つ化学エネルギーを極力熱に変えず効率的に電気エネルギーへと変換するというものです。これは従来の、バイオマスを燃焼させて熱を発生させる方法とは、一線を画します。
具体的には、金属イオンの酸化還元反応を利用します。まず、化学エネルギー変換プロセスでバイオマスと金属イオンを含んだ水溶液を反応させ、バイオマスが持つ化学エネルギーを液体に移します。その後、電気化学的変換プロセスに液体を流し込んで電気を取り出すという仕組みです。従来の燃焼方式ではバイオマスが持つエネルギーのうち10%から30%程度しか電気に変換できなかったのに対し、私たちの技術では55~80%のエネルギーを電気として回収することができます。

――ライノフラックスの技術は、発電の過程で発生したCO2を高純度に回収できるようですね。どのような仕組みなのでしょう。
間澤:従来の燃焼を伴うバイオマス発電では、燃焼時に他の気体が大量に混ざるため、高純度のCO2として回収するためにはCO2の分離プロセスが必要になり、結果的にコスト高になっていました。一方で私たちの発電プロセスは、バイオマスと水溶液が反応する際に純度99.9%以上のCO2を生成し、他の気体が混ざる余地もありません。高純度のCO2をそのまま回収できるため、ほとんどコストもかからず、再利用もしやすいのです。
回収したCO2は、飲料用の炭酸ガスや、温室栽培での植物の光合成促進用として活用できますし、合成燃料の原料や、化学工業における素材としての利用も視野に入れています。それにより「発電しながらCO2を回収し、価値のある資源として再利用する」という一石二鳥の仕組みを実現できたのです。
1畳からはじまるバイオマス発電で分散型エネルギー社会を実現
――現在の事業フェーズについて聞かせてください。
間澤:現在は実証実験フェーズで、今後複数の企業と小型の発電設備を用いて技術の安定性や効率性を検証しています。特に、食品工場や農業施設など、バイオマス資源が継続的に供給される現場において、エネルギーの地産地消モデルを確立する取り組みを進めています。
特徴的なのは、私たちの発電設備が最も小さいもので9㎡まで小型化できることです。これにより、限られたスペースでも導入しやすく、発電所のような大規模設備を必要としない分散型エネルギーとしての実用性が飛躍的に高まりました。

――今後はどのようにして商用化を実現させていくのでしょうか?
間澤:2025年中に、技術の実証と最適化を行います。小型実証機を用いて詳細なデータ収集と課題の洗い出しを行う予定です。現在はラボでの発電に成功していますが、ラボ以外の場所でも24時間365日安定して発電できるようにしなければなりません。
また、大型化の検討にも取り組んでおり、長時間の連続運転や耐久性の向上を目指しています。最終的には2028年の商用化を目指し、パートナー企業との連携や資金調達も進めながら、技術の普及を加速させていく考えです。
――これからどのように市場に浸透させていくのか、事業戦略についても教えてください。
間澤:まずは分散型エネルギーの需要が高い分野や地域に焦点を当てていきます。たとえば、食品・飲料工場や農業関連施設などは、バイオマス資源がその場で大量に発生します。そういった現場に小型の発電設備を導入することで、エネルギーの地産地消を実現できれば、バイオマスの収集・輸送コストがかからないため発電のコストを大幅に抑えられるでしょう。
私たちのバイオマス発電は、火力発電などの従来型の発電システムとは異なり、小規模でも発電効率がほとんど落ちません。そのため、分散型エネルギーシステムとして非常に適しており、バイオマスが発生する現場で発電できるのです。
――環境的にも経済的にも大きな利点があるのですね。
間澤:そうなんです。また、同時に発電過程で生成される高純度のCO2を、付加価値の高い形で再利用するビジネスも拡大していきます。飲料メーカーの炭酸ガス供給や、温室栽培における光合成促進など、複数の産業と連携することで、経済的なメリットを提供できるでしょう。
さらに、大型化に成功して発電効率や耐久性が向上すれば、地域分散型だけでなく、大規模な発電事業にも展開可能です。最終的には、バイオマス発電の革新的な技術とCO2回収・再利用の仕組みをパッケージ化し、国内外の市場に展開していきたいと考えています。
起業は「未来を作る権利」。トヨタの町で感じた「会社が人を支える」という理想像
――起業前のキャリアを聞かせてください。
間澤:起業前は三菱商事で金属資源のビジネスに携わっていました。ドイツに駐在しながら貿易業務をしたり、事業撤退の主任を経験したり。その後、CVC部門に移り、アメリカやイスラエルを中心に、スタートアップ投資や成長支援に従事していました。当時、再生可能エネルギーや環境技術に関連するプロジェクトに関わったことで、エネルギー分野における課題に気づいたのです。
その過程で、日本には優れた技術があるにもかかわらず、それが社会に実装されない現状に強い問題意識を抱きました。この課題を解決するために、技術とビジネスを結びつけるため、自ら起業しようと思ったのです。
――最初からエネルギー領域で起業しようとしていたのでしょうか。
間澤:いえ、エネルギー領域はビジネスとして形になるまで時間とお金がかかるため敬遠していました。当時はITサービスを考えており、事業アイディアを作っては投資家にピッチを繰り返していて。しかし、2年もピッチを続けていると、ITのビジネスアイディアが尽き、自分の強みを活かせるのはエネルギー領域だと気づきました。
それから、日本中の大学で研究されているエネルギー技術を見比べ、ライノフラックスの根幹となっている京都大学の反応工学チームが手掛けていた研究にチャンスを感じたのです。当時、京都大学は国が推進している「客員起業家(EIR)」制度を実施していたため、自分のビジネス経験を活かすため客員起業家になりました。

――社内で新規事業を立ち上げる選択肢もあったと思いますが、起業にこだわった理由があれば聞かせてください。
間澤:起業にこだわったのは、私の地元である豊田市での経験です。ご存知の通り、豊田市にはトヨタがあり、子供の頃からその偉大さを間近で見てきました。トヨタは単に車を作っている会社ではなく、病院をつくり、街をつくり、社員の暮らしを作っています。さらには、それを日本のみならず世界中で行っており、創業者が亡くなったあとも脈々と続いている。そういった間接的なものまで含め、トヨタという偉大な「箱」を作っていることをリスペクトしていました。私もそうした箱をつくることに挑戦してみたいと考えると、既存企業で従業員として働くのではだめで、自分で会社を創業する必要がありました。
――最後に、これから起業を考えている方へのメッセージをお願いします。
間澤:私は起業を「未来を創る権利」だと思っています。直接的であれ間接的であれ、起業してサービスを提供するということは、未来を創る仕事です。そして、それは誰もができることではありません。
私がこれまで寝る間も惜しんで勉強し、働いてきたのは、この権利を得るためだと考えています。たしかに起業はリスクを伴いますし、大企業で働いている時に比べたら給料は半分以下に抑えています。しかし、私はそれで直接的に未来を創る権利を行使していると思っています。
私は起業という形で未来を創る権利を取りに行きました。チャンスがあるなら権利を行使するのはおすすめです。ただ、必ずしも起業しなければ未来を創れない訳ではありません。大企業でも未来を創るチャンスは多々あるとも思っています。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:鈴木光平
撮影:河合信幸




 カーボンニュートラル
カーボンニュートラル