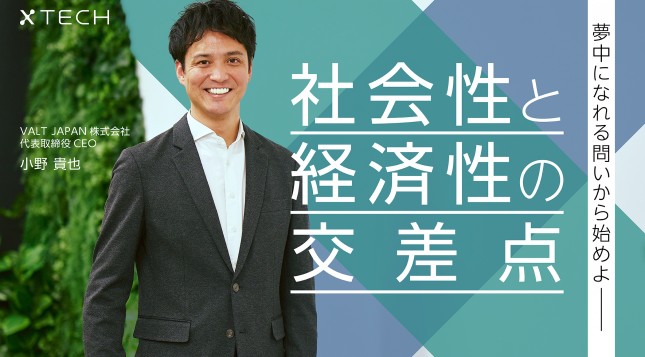革新的なガス分離膜技術でOOYOOが目指す脱炭素社会
読了時間:約 9 分
This article can be read in 9 minutes
脱炭素社会の実現に向け、世界的に注目を集めるCO2回収技術。その中で、ひときわ革新的なアプローチを打ち出しているのが、京都大学発スタートアップのOOYOO。
同社が開発する「ガス分離膜技術」は、小型かつ高効率でCO2を回収することを可能にする画期的なものだ。従来の大型で高コストな回収装置と異なり、量産性やコスト効率に優れており、環境問題解決の新たな可能性を切り開くと期待されている。
今回は代表の大谷彰悟氏とCTOのラルフ・ナサラ氏にインタビューを実施。18年間勤めた大手商社を辞め、DeepTechスタートアップに飛び込んだ背景には何があったのか。また、膜技術を開発し、OOYOOの戦略の礎を築いたシバニア教授のアントレプレナーシップにもフォーカスした。
世界を舞台に、脱炭素社会の実現に挑むOOYOOが描く未来に迫っていく。

大谷彰悟
株式会社OOYOO 代表取締役
2005年東北大学大学院建築学修了後、新卒で丸紅に入社。電力ビジネスに関わり18年間で3カ国の駐在を経験。その後スタートアップでの挑戦を志し、京都大学イノベーションキャピタルに転職。京都大学のシーズを探索していたところOOYOO創設者のイーサン・シバニア教授と出会い、意気投合。OOYOOの経営陣として参画することを決意。
ラルフ・ナサラ
株式会社OOYOO CTO
National Cheng Kung University PhD。京都大学の研究員を経て、OOYOOに参画。
ポイント
・OOYOOは、既存高分子の最適組合せで、新素材を要さず小型・高効率・低コストを両立。コンテナ型モジュールで拡張自在なCO2回収膜を武器に早期の社会実装を狙う。
・コア技術は自社、量産はTOPPANなどと連携するファブレスでスピード重視。製造・エンジをパートナー化し、コスト効率と立ち上げ速度を両立する体制。
・実証段階で量産再現性を確保中。まずは1日10トン回収を目標に、量産コスト最適化と安定運用を突破口にスケールを加速。
・欧米は先行も装置大型・高コストが課題。アジアで需要増、日本はGXを追い風に優位性を発揮し得る。膜×他手法のハイブリッドも視野に。
INDEX
・小型・高効率・低コスト!OOYOOのガス分離膜が加速するCO2回収市場
・モジュール戦略とパートナーシップで放つ、世界市場での大きな存在感
・死と隣り合わせの経験が転機に。エリート商社マンがスタートアップへの参画を選んだ理由とは
・「社会実装」こそが命題!シバニア教授の革新的な発想が創り出す未来
小型・高効率・低コスト!OOYOOのガス分離膜が加速するCO2回収市場
――「ガス分離膜」とは、どのような技術なのでしょう。
大谷:「ガス分離膜」とは、分子サイズや溶解度の違いを利用してガスを分離し、特定の気体を選択的に透過・分離する技術です。例えば、空気中の二酸化炭素(CO2)を膜に通して、効率的に回収することができます。
実は、ガス分離膜自体は40年以上前から存在しており、決して新しい技術ではありません。水処理膜のように浸透膜技術の一つとして長らく研究されてきました。ただし、CO2の分離・回収に経済価値があると認知されたのは、ここ数年のこと。従来の回収手法は装置が大きくコストがかさむため、よりコンパクトで低コストに回収するための研究が進められているのです。
――OOYOOの技術は、従来の技術と比べてどのように優れているのでしょうか?
ラルフ:OOYOOのガス分離膜は小型で、高効率・低コストという特徴があります。従来の化学吸収法[1]や固体吸着法は装置が大きく、導入・運用コストが高かったのですが、それらの課題を解決できます。
また、シバニア教授(京都大学教授/OOYOO取締役・創業者)の研究成果をベースに、既存の高分子素材を最適に組み合わせることで、膜の製造に新素材を必要としないのも大きな特徴です。新素材を作れば、回収効率は上げられるかもしれませんが、開発や製造にコストがかかるため、市場に広がるのに時間がかかります。素材を使えるようにすることで、スピーディな市場展開を狙えるのです。
スピードを上げるために、装置も「モジュール化」しました。20フィートコンテナサイズの装置を開発しており、その装置を組み合わせるだけで大規模なCO2回収も可能にしたのです。

――ビジネスモデルについても聞かせてください。
大谷:私達はコア技術の開発に集中するため、工場を持たない「ファブレス経営」を取り入れています。具体的には、私たちが開発するのは「ガス分離膜」のコア技術部分のみです。製造やシステム構築は、それぞれの分野で強みを持つパートナー企業と協力しながら進めています。
膜の製造に関しては、TOPPANホールディングス社のようなコーティング技術に優れた企業と提携し、既存の設備を活用することで、スピーディかつコスト効率よく量産化を実現しました。また、装置のシステム化やエンジニアリング部分についても専門の企業と連携し、社会実装を加速させる体制を整えています。
これらの戦略もまた、スタートアップらしく「スピード」を武器にするためです。
[1] 化学吸収法・・・ アミン吸収法とも呼ばれる、化学反応を利用して二酸化炭素を分離・回収する技術。
モジュール戦略とパートナーシップで放つ、世界市場での大きな存在感
――現在の事業フェーズを教えてください。
大谷:現在は実証実験フェーズです。ラボレベルではすでに高い性能を示す膜の開発に成功しており、それを量産レベルでも再現する段階にきています。膜自体の性能をさらに高める余地はありますが、まずは「量産可能な安定性能の膜」を軸に社会実装を進めることが優先です。
具体的には、1日あたり10トン(平均的な日本人1人が1年間に排出する量)のCO2を回収できる装置を作ることを目指しています。現在はエンジニアリング会社と連携し、試験設備を整えると同時に、工場や発電所と協力しながら現場レベルでの実証を進めているところです。社会実装に向けた最後の壁である「量産コストの最適化」と「システムの安定運用」をクリアすることで、スケールアップに向けた道筋を確立し、市場展開を加速させていきます。
――今後はどのように市場に展開していくのでしょうか?
大谷:今後は「スケーラブルなシステム構築」と「パートナーシップの強化」を軸に進めていきます。私たちが開発しているコンテナ型の装置は、その形状と仕組みから、複数台を組み合わせることで大規模なCO2回収が可能です。
たとえば初期は1台から導入し、効果を確認しながら必要に応じて台数を増やすという形で、柔軟かつ低リスクで導入できます。このアプローチにより、中小企業から大規模プラントまで幅広い市場に対応できるでしょう。
また、既存の大手エンジニアリング会社や製造パートナーと協力し、装置の製造・供給を効率化することで、導入コストを抑えつつスピーディに展開していきます。さらに、膜技術はCO2回収だけでなく、他のガス分離にも応用が可能です。CO2市場の需要動向を見極めながら、並行して酸素や有害ガスの分離といった新たな領域への展開も視野に入れています。

――世界の市況についても聞かせてください。
ラルフ:世界市場に目を向けると、CO2回収市場は急成長中であり、各国が脱炭素目標を掲げる中で技術革新が求められています。特に、アメリカやヨーロッパを中心にカーボンニュートラルへの取り組みが加速しており、CO2排出量の削減は産業界の必須課題になってきました。
例えば、アメリカでは既にCO2回収プラントの大規模な実証実験が行われており、MTR社などが膜技術を活用して市場を先行しています。しかし、従来の技術は装置の大きさやコスト面で課題が残っているのが現状です。
一方、アジア市場では産業の成長とともに排出削減の必要性が急務となっており、日本も「GX(グリーントランスフォーメーション)」戦略の一環としてCO2回収技術への投資が進んでいます。特に、日本はエネルギー効率や環境技術に強みを持つため、OOYOOの技術が大きな役割を果たせると考えています。
――世界の市場でも勝ち残っていける優位性があるのですね。
大谷:たしかに私たちの技術は、他社にないメリットを持っていますが、CO2回収は単に技術競争ではなく、市場全体での協調が重要だと考えています。なぜなら、膜技術にはメリットがある一方で、デメリットも存在するからです。
膜技術だけでなく、他のソリューションとの“ハイブリッド運用”も視野に入れることで、より大きな価値を生み出せます。そのため、市場での競争だけでなく“共創”も視野に入れながら事業を展開していきたいですね。
死と隣り合わせの経験が転機に。エリート商社マンがスタートアップへの参画を選んだ理由とは
――大谷さんはもともと商社に勤めていましたよね。スタートアップの道に進んだきっかけを聞かせてください。
大谷:私はもともと丸紅で18年間働き、電力事業を中心に事業開発をしていました。海外の子会社経営も任されていましたが、その中で「自分自身で新しい事業を立ち上げたい」「経営者として勝負したい」という思いが徐々に強くなっていって。
海外で働いていると、日本のものづくりや技術力が相対的に存在感を失っていくのを肌で感じました。かつて世界を席巻した日本の重厚長大な産業が、世界市場では徐々に押され始め「このままでは日本の技術が埋もれてしまう」という強い危機感から、起業を考えるようになったのです。
――直接的にアクションを起こすきっかけはあったのでしょうか。
大谷:決定的だったのは、転んで頭を打ったことで「死んでいたかもしれない」と思ったからです。「人生はいつ終わるかわからない」「後悔しない生き方をしよう」と強烈に感じたことで、安定したキャリアを捨てて後悔しない人生を歩もうと腹を括りました。
思い切って商社を退職し、転職したのが京都大学のVCです。そこで最先端のシーズ技術や研究者たちと触れる中で、シバニア教授の「膜技術」に出会い、その革新性と社会的意義に強く惹かれました。「これを事業化し、世界に広めることこそ、自分の使命だ」と勝手な使命感からOOYOOに飛び込むことを決意したんです。

――ラルフさんは、別の研究をしていたんですよね。なぜOOYOOにジョインしたのでしょう。
ラルフ:私はもともとリチウムイオン電池の研究をしていました。京都大学でエネルギー材料の開発に携わり、研究員として働いていたんです。しかし、シバニア教授に出会い、私の人生は大きく変わりました。
シバニア教授はただの研究者ではなく、社会実装まで見据えた突破力を持つ特別な存在だったのです。教授が持つ「膜技術」のアイデアは、単なる学問の成果ではなく、世界を変えうる実用的な技術でした。初めて話を聞いたとき「一緒にやろう、未来を作ろう」と誘われたんです。
その言葉に心を動かされました。それまでの私は、研究室にこもって自分だけの成果を追求する日々でしたが、教授の姿勢やビジョンに触れて「この技術を世の中に届けたい」という強い気持ちが芽生えたのです。
――技術の革新性はもちろんのこと、教授の人柄にも惹かれたのですね。
ラルフ:その通りです。シバニア教授は失敗を恐れず、柔軟に方向転換する方です。例えば、実験のデータが悪ければ180度方向転換することも厭いません。その姿勢を見て「この人とならどんな困難も乗り越えられる」と感じたんです。
当時は、昼は京都大学で研究員として働き、夜はシバニア教授のもとでスタートアップの準備に没頭する日々でした。正直、体力的にも厳しかったですが、「この技術で社会に貢献する」という使命感が、私を動かしてくれました。
「社会実装」こそが命題!シバニア教授の革新的な発想が創り出す未来
――大谷さんから見て、シバニア教授はどのような方ですか。
大谷:シバニア教授はただの研究者ではなく、起業家のような人です。多くの研究者がラボでの性能向上を目指し、理論を追い求めるのに対し、シバニア教授は「社会実装」を最初から見据えています。「どうすれば世の中で使える技術になるか」を逆算して研究を進める姿勢は、一般的な研究者の枠を超えています。
たとえば膜技術の開発でも「新しい高分子を作るのではなく、既存の素材を組み合わせることで量産可能な技術を作る」という考え方がその典型です。一般的な研究者なら、新しいものを作りますし、その方が評価されるでしょう。
しかし、新素材の研究は時間もコストもかかり量産が難しい。シバニア教授は「社会に出て使われなければ意味がない」と考え、現実的な解決策を追求してきました。
――たしかに研究者よりも起業家的な発想ですね。
大谷:戦略面でも、教授の影響は非常に大きいです。「ファブレス型ビジネスモデル」や「モジュール化によるスケールアップ」は、教授が持つ柔軟な発想とビジョンがベースにあります。
一般的にファブレス経営やパートナー戦略は、技術を模倣されるリスクも孕んでいます。しかし、教授はよく「真似されたら、次のことをやればいい」と言うんです。技術革新はスピードが命。研究成果に固執せず、データや市場の反応を見ながら柔軟に方向転換する姿勢は、スタートアップ経営そのものです。

――最後にこれからスタートアップを考えている方へのメッセージをお願いします。
大谷:多くの人が今の日本や世界に危機感を持っていると思いますが、そこから実際にアクションを起こすのは一握りです。私自身も、「何かしたい」と思いながら、アクションを起こすまでに長い時間がかかりました。
その決断の背中を押してくれたのは「後悔したくない」という気持ちです。「明日死ぬかもしれない」と感じた瞬間に、人生は一度きりであり、やりたいことをやらないまま終わりたくないと強烈に感じました。
スタートアップには不安やリスクがつきものです。しかし、「やりたい」と思った時が、挑戦するベストなタイミングだと信じています。最初からすべてが完璧に整うことはありません。大切なのは、目の前の課題に向き合い、柔軟に戦略を変えながら進んでいくことだと思います。
ラルフ:事業は決して一人では成し遂げられません。人との出会いや仲間の存在が、事業を加速させてくれます。私が今ここにいるのも、シバニア教授や大谷さん、そして技術やビジョンを信じて支えてくれるパートナー企業がいたからです。
「日本の技術を世界に届けたい」「社会を良くする一歩を踏み出したい」という使命感があれば、道は必ず開けます。失敗を恐れずに、まずは一歩を踏み出してください。挑戦することでしか見えない景色がきっとあるはずです。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
撮影:河合信幸



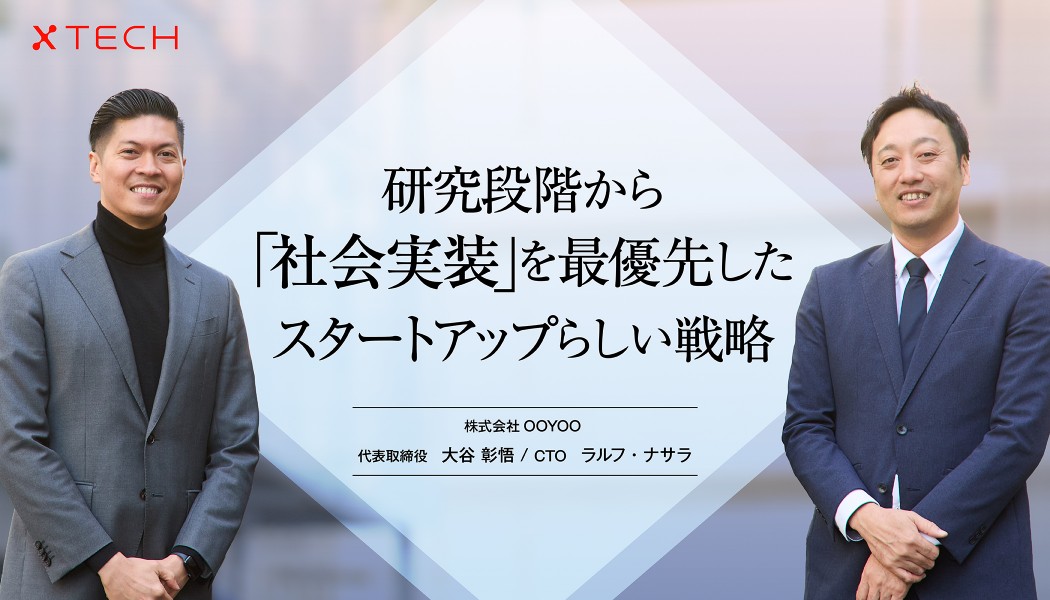
 カーボンニュートラル
カーボンニュートラル