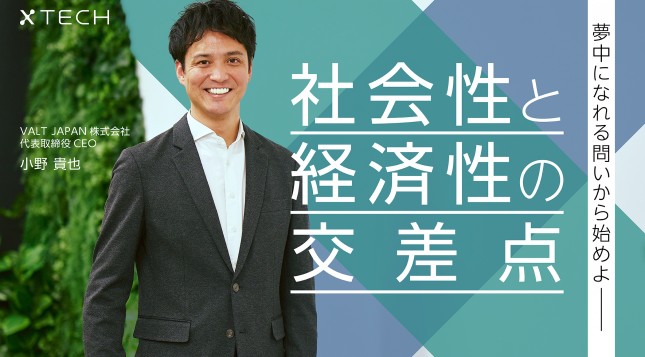強みを見つめ直しIPOを達成。マイクロ波化学が採用した、事業成長につながる自社の強みの使い方
読了時間:約 9 分
This article can be read in 9 minutes
革新的な素材が続々と登場して豊かな暮らしを支えているが、そうした素材を作る化学産業は石油や石炭などの資源に今でも依存している。100年前から今日に至るまで、製造法に大きな変革は生まれなかったことが環境に負荷を掛けつづけていると、マイクロ波化学の吉野巌氏は語る。
ゲームチェンジャーになると同氏が考えているのが、マイクロ波である。電子レンジなどに使われているマイクロ波はエネルギー効率を上昇させ、その利活用により二酸化炭素排出量の減少にも繋がるとのこと。しかし、マイクロ波は制御が難しく、産業実装には大きなハードルがあった。
同社は大阪大学発・ディープテック領域のスタートアップとしてマイクロ波装置の大型化に成功。2022年にはIPOも果たした。ビジネスを展開する上での同社の強みやIPOまでの取り組み、今後の展開についてお話を伺う。

吉野巌
マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長CEO
1990年、慶応義塾大学法学部法律学科卒、2002年UCバークレー経営学修士(MBA)。三井物産株式会社(化学品本部)を退職後、米国にてベンチャーやコンサルティングに従事。2007年8月、マイクロ波化学株式会社を設立、代表取締役就任。技術経営(MOT)日立フェロー。
ポイント
・マイクロ波化学は、電子レンジにも使われるマイクロ波のエネルギー効率の高さと直接加熱特性を活かし、これまで産業実装が困難とされた大規模化に成功。化学業界の常識を覆すゲームチェンジャーとして注目される。
・マイクロ波化学の強みは、化学と物理学の専門家を結集し、反応系と反応器の2つのデザインを駆使したこと。これにより、過去に多数の論文がありながらスケールアップが困難だったマイクロ波の産業利用を可能にした。
・かつて化学工場を所有していたものの、イノベーションと工場運営の対極性から、サイエンス・エンジニアリングの専門性を活かす技術提供型(アセットライト)へ転換。これがIPO達成に繋がった。
・マイクロ波の特性を活かし、熱伝導効率の悪さや物質特定の問題を解決。ケミカルリサイクルや鉱工業の精製プロセスで実績を積み、脱炭素化という不可逆な社会潮流が事業成長を後押ししている。
・事業成長の秘訣は、研究・エンジニアリング・事業開発を内製できる人材の集結と、投資家への説明責任を果たすパイプラインモデルの構築。日本はディープテック企業にとって大きなチャンスがある。
INDEX
・専門技術を活かして、「できなかったこと」を実現させた
・シーズとニーズの接合点を見つけ出す
・2022年にはIPOも達成 ディープテック領域で事業を成長させる秘訣とは
・ディープテックのスタートアップにとって、今の日本はチャンスである
専門技術を活かして、「できなかったこと」を実現させた
――貴社のビジネスについて教えてください。
吉野:当社は、マイクロ波を活用したソリューションを提供する企業です。マイクロ波といえば産業用途としては主に通信機器に使われていますが、たとえば電子レンジのように物質を温める用途にも使用されます。通常の加熱のように外部から間接的に熱を伝えるのではなく内部のターゲットにエネルギーを直接的に伝えられるので、ディスラプティブな存在です。この特性を利用して、産業用途向けに開発・実装を進めている形です。
――マイクロ波を産業的に実装させるところにポイントがあるのでしょうか?
吉野:はい、その通りです。化学業界では、1980年ごろからマイクロ波の実験はたくさん行われてきており、論文も蓄積されています。しかしマイクロ波はその性質上、反射や屈折が頻繁に起こることから制御が非常に難しく、「研究対象としては興味深いけれどもスケールアップは難しい」というのが常識でした。私たちが普段から話をさせていただいている化学メーカー様も、9割以上はマイクロ波の装置をラボに持っていて実験を繰り返しているのですが、商業用の大規模プラントは実現できていません。
我々は、大阪大学発のスタートアップとしてこの課題に取り組んでいます。世界初となる大規模なマイクロ波化学工場を2014年に立ち上げました。
――大型のマイクロ波工場建設は、これまでの常識では難しかったんですよね。なぜそれを実現できたのですか?
吉野:2つのデザインを駆使することで大型化を実現させました。1つ目が「反応系のデザイン」で、料理でいえばレシピのようなものです。マイクロ波は物質ごとに選択的に吸収されるので、狙ったものを温められる特性を持ちます。陶器のコップの中に入っている水だけを電子レンジで温めるイメージですね。通常の加熱であれば全体が温められてしまうのですが、マイクロ波であれば狙った物質だけを温められるわけです。何にマイクロ波を伝達させるかをデザインしました。
2つ目は「反応器のデザイン」で、調理器具をイメージしていただければよいかと思います。理科の実験でフラスコをバーナーで温めたことがあるかと思うのですが、その時には表面からエネルギーが伝わっていくので2次元的な熱伝導となります。一方のマイクロ波は空間を伝わっていくので3次元的な伝わり方です。この伝わり方を精密に制御することは難しいのですが、電磁波の精緻なコントロールに向けて反応器のデザインに注力しました。

――なぜ、こうした仕組みを実現させられたのでしょうか?
吉野:ひと言でいえば、物理学と化学を融合させたところに当社の強みがあると考えています。一般に、化学メーカーは化学者の集団なので、物理学者がいないんです。しかしマイクロ波は化学と物理学の境目にある技術で、業際的な分野です。創業した当初からマイクロ波に着目していたので、物理学の専門家と化学の専門家を集めました。
そのうえで、時間をかけて試行錯誤を繰り返しました。先ほど申し上げた2つのデザインを行い、それをコンピュータ上のシミュレーションにより検証します。仮想空間での実験だけで済むわけはないので、今度はモノを実際に動かしてデータを取得。それをプログラムにフィードバックして、実験を改めて行って、といった繰り返しでノウハウを蓄積して、7〜8年かけてスケールアップを実現させました。
シーズとニーズの接合点を見つけ出す
――どこで収益が生まれるビジネスモデルなのでしょうか?
吉野:当社は、プロセス開発や技術の提供がメインです。化学メーカー様や装置メーカー様にソリューションを提供するのが当社の役割で、お客様が抱える課題をナレッジで解決しています。
現時点での注力分野は2つあります。1つ目がケミカルリサイクルです。リサイクルのために、プラスチックをお釜で加熱して分解しようとしても、お釜の中には空気も入っているので熱伝導効率が悪いんです。また、色々な物質が混ざっている時に、ある特定の物質にだけエネルギーを伝えるのも、従来手法だと困難でした。マイクロ波はターゲットごとにエネルギーを伝えられるので、こうした課題を解決できると考えました。三菱ケミカル様と本田技研工業様と実施しているテールランプtoテールランプの水平リサイクル実証実験、旭化成様とのポリアミド66のケミカルリサイクル共同実証試験、使用済みプラスチックをリサイクルする技術のレゾナック・ホールディングス様との共同開発などの実績があります。
2つ目が鉱工業の分野です。現在、オーストラリアや南米で採れた鉱石は中国に持ち込まれてリチウムなどの資源が精製されています。精製工場では高いエネルギーを消費することもあり、環境負荷が課題として挙げられてきました。そこで当社では、鉱石中に含まれる成分にマイクロ波を使ってエネルギーを選択的に加えることで資源を取り出すことに取り組んでいます。
――マイクロ波を使える分野は限定されているのでしょうか?
吉野:いえ、既存の技術で解決できない課題がある企業にとっては、広く役に立つものです。多くの企業は何らかの形でエネルギーを使うわけですが、マイクロ波は従来とは真逆のエネルギー伝達手段なので、革新的なソリューションとしてお使いいただけるものだと思います。コストを下げたい、新素材を作りたいといった課題をお持ちの企業様はぜひ当社にお越しください。
ただ、当社のようなスタートアップだと参入が難しい分野があることも事実です。たとえば鉄鋼や自動車などは、旧来型のテクノロジー技術がすでに導入されていて、しかも数十年単位の耐用年数で工場や設備が作られています。「優れた新技術があります」と言われても、タイミングがかなり良くないと導入は難しいでしょう。

――応用範囲が限りなく広い中で、2つの分野に今のところ注力しているのはなぜですか?
吉野:ケミカルリサイクルは比較的新しい事業分野なので、我々の技術を採用していただきやすい分野です。技術的にも親和性が非常に高いことからすでに30件以上のプロジェクトが動いており、年間に300トンを処理するプロトタイプのプラントもあります。また、鉱工業領域については、国際情勢もあり事業的な機会を見出しています。
2022年にはIPOも達成 ディープテック領域で事業を成長させる秘訣とは
――ディープテック領域のスタートアップでは志半ばで事業を諦めざるを得なくなるケースも多いかと思います。そうした中で、貴社が成功している理由はどこにあるのでしょうか?
吉野:結局はヒトです。研究やエンジニアリング、事業開発をできる人が揃っていることは当社の何よりの強みです。外注だと提供できる価値が大きく減ってしまうので、組織づくりには力を入れてきました。組織運営は本当に大変なのですが、キーパーソンに管理を任せたり、横串を通すような組織構造にしたりと試行錯誤しています。結果として、事業開発、研究からエンジニアリングまでを一気通貫できる技術とノウハウが蓄積されました。
――ちなみに、貴社のビジネスは技術を提供するものですが、自社でプラントを建設することは考えなかったのでしょうか?
吉野:実は、当社も化学工場を所有していました。当時はインキの原料を製造し、インキメーカー様に販売するビジネスを行っていたんです。ところが、新聞用インキの市場が飽和状態になったこともあって事業成長の限界が見えてきました。
そこで改めて自社の強みを見直したところ、サイエンスやエンジニアリングのイノベーションに専門性があるという結論に至りました。工場を運営・管理する上では5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)などの規律がキーワードになるわけですが、規則を守ることとイノベーションは対極にあります。工場の拡大に注力するよりも、工場を大型化する過程で得た知見を活かして技術を提供するモデルに切り替えるべきだという結論に至りました。
――試行錯誤の末に、自社の強みを活かせるビジネスモデルを作り上げたのですね。
吉野:その通りで、これまでの経験も踏まえて、IPO前後はアセットライトなビジネスモデルを作り上げました。脱炭素の文脈で電化が注目され、当社の技術も注目されたことで引き合いが増えたこともあり、事例が蓄積されてIPOも達成しました。

――IPO達成に向けて有効だった施策はありますか?
吉野:投資してくださる方への説明責任を果たせるような再現性の確保だと考えています。引き合いに対して受注の割合がどれくらいで、そうするといくらの売上が立って利益がこれくらい生まれるといったプライシングも含めたパイプラインモデルを作りました。それに基づいて事業がステージアップしていくというように説明を行っていました。
――2025年の6月には上場3年目を迎えました。これからの事業プランについても教えてください。
吉野:大きな流れでいえば、今までとは全く違ったことはやらないとは思います。というのも、脱炭素の流れは、小さな波はありつつも不可逆なものだと認識しているからです。豊かな生活を送るためには環境負荷を低減させることはどう考えても必要なので、当社の事業が伸びていくのは間違いないでしょう。
ただし2の矢、3の矢を打っていく必要性も感じており、主には2通りの展開を考えています。1つ目が、従来通りのマイクロ波を新分野に提供することです。当初は化学分野でスタートして、金属も扱うようになりました。次の分野としては半導体などを見据えていて、研究開発を進めているところです。
もう1つの展開としては、提供できるソリューションを増やしたいと考えています。現在はマイクロ波を使ったソリューションを提供しているわけですが、お客様としてはマイクロ波を使うことは手段でしかなく、本質的な課題は二酸化炭素削減やエネルギー使用量削減、効率化によるコストカットなどです。マイクロ波に代わる技術を当社が持っていたら、お客様はハッピーですし、当社にとっても事業になります。そうした想いから、マイクロ波に代わる技術を仕込んでいるところです。
ディープテックのスタートアップにとって、今の日本はチャンスである
――上場せずにユニコーンを目指すスタートアップもある中で、IPOを選択されていかがでしたか?
吉野:メリットの方が大きかったと感じています。というのも、株式が公開されるとガバナンスが効きますので、良い意味での緊張感が生まれました。こうした緊張感は役員や従業員にとっても刺激となっていて、研究開発やエンジニアリングなど全てにおいてプラスに働いています。

――ありがとうございます。最後に、吉野さんから見たディープテックを取り巻く状況についてお話を聞かせてください。
吉野:今の日本は、ディープテック領域のスタートアップにとって大きなチャンスだと思います。ディープテックという言葉が脚光を浴びていることもあるのですが、そもそも日本は技術的な基盤もありますし、自動車や造船、鉄鋼など一通りの産業が揃っています。世界を見回すと、これほど産業が揃っている国は多くはありません。ディープテック関連のテクノロジーをベースにして新しい技術や産業を作るのには適している国だと言えるでしょう。また、ディープテック領域は、天才的なスタープレーヤーによるブレークスルーよりも、チームワークが光る分野です。地道な努力の先に、大きな事業やプラットフォーム化につながるテクノロジーが生まれるものだと思います。
一方で、面白い技術があり実装の目途も立っているのに、スケールさせられない会社は多くあります。ものづくり企業はラボからスタートする場合も多いので、事業開発の人材がいなかったり、エンジニアリングの機能を有していないことも多々あります。
前述したように、当社は今後ともマイクロ波を使った技術プラットフォームの提供を核にしながらも、お客様や社会の課題を解決する様々なソリューションを打ち出す所存です。既存の技術では解決できない課題をお持ちの企業様にお目にかかれる日を楽しみにしております。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:宮崎ゆう
撮影:阿部拓朗




 カーボンニュートラル
カーボンニュートラル