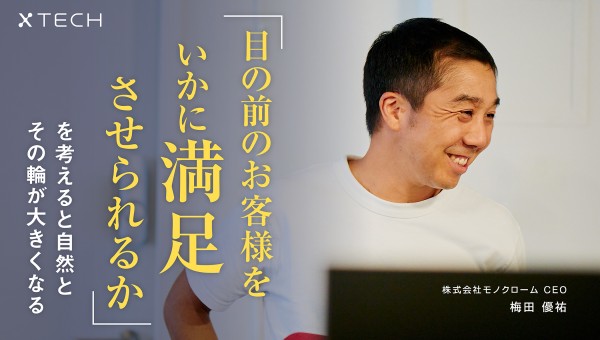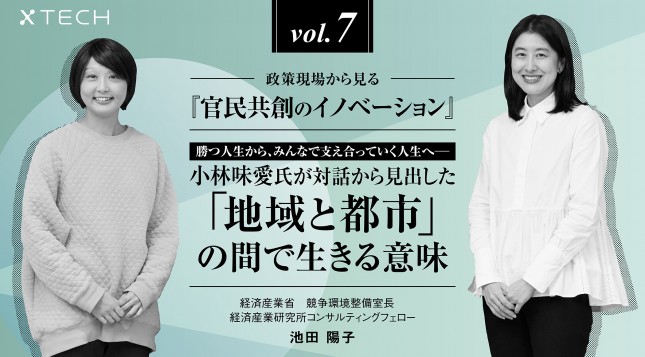目指せ国産浮体式風車!アルバトロス・テクノロジーが挑む新しい形の洋上風車
読了時間:約 12 分
This article can be read in 12 minutes
日本ではまだそれほど普及していない洋上風力発電。海外ではメジャーな発電方法ではあるが、日本では政策的な理由や地形的・技術的な制約などのために開発・実装が大幅に遅れている。原発再稼働に時間を要する中、結果として、エネルギー需要を満たすために石炭・石油などを海外から輸入せざるをえず、経済安全保障上の課題となっていることはご存じの通りだ。
しかし、日本は海に囲まれた島国であり、洋上風力発電のポテンシャルは我々の想像よりもはるかに大きい。計算上「日本国内の全電力需要を賄える」と語るのは、アルバトロス・テクノロジーのCOO、長壁一寿氏。研究開発型スタートアップである同社は、洋上風車や潮流・海流タービン、波力タービンの実用化に取り組んでいる。うまくいけば、日本のエネルギー問題を大きく改善できるかもしれない。
日本の洋上風力発電は、かつては大手メーカーも取り組んでいた領域。そうしたメーカーでさえも撤退を余儀なくされた市場において、スタートアップはどのように戦えば良いのだろうか。大手海運会社や外資コンサル、中小企業など様々な企業を渡り歩いてきた長壁氏に、同社が開発する洋上風力発電や日本のエネルギーの未来についてお話を伺う。

長壁一寿
株式会社アルバトロス・テクノロジー COO
2023年に株式会社アルバトロス・テクノロジーに参画。COOとして資金調達や採用を中心にコーポレート関連業務全般を担当。
川崎汽船に入社後、船舶投資、IR、新規事業開発等に従事。2017年には労働組合執行委員長を兼務。その後、外資系コンサルティング会社のA.T.カーニーに入社。クライアントのビジネスデューデリジェンスや新規事業計画立案などを支援。創業100年超の地方の中小企業にて事業計画立案や海外事業を推進。
IE Business School MBA。
ポイント
・洋上風力発電は、「着床式」と水深が深いエリアに設置する「浮体式」の2種類の設置法式、「水平軸型」と「垂直軸型」という2種類の構造を掛け合わせた、4種類がある。浮体式はまだ黎明期で、様々な開発が進んでおり、今後急速に設置が増えていく見込み。
・国内で洋上風力発電が下火になった理由は、地形的な理由もある。日本は急峻な地形であるため陸上風車市場が拡大しにくかった。一方で海外の主要メーカーは膨大な陸上風車市場を前提に、洋上用の大型化競争を進めることができた。
・アルバトロス・テクノロジーでは、主流の水平軸型風車とは全く異なった見た目の垂直軸型風車を採用。重い発電機部分を低い位置に置き、傾きを許容することで重心を下げ、浮体を小型化、大幅なコスト削減を目指す。
・同社の”FAWT”設置には大型作業船が不要で設置コストも大幅に低減する。また、大型の発電機を1台置くのではなく、複数台の小さなものとすることで国内調達を可能にし、調達の問題も解消する。
・学校では「日本は資源が乏しい国」と誰もが習うが、実際には日本には風という資源が豊富にある。”FAWT”は日本の安全保障に貢献するだけでなく、国内技術を活用することで経済効果も見込まれる。日本は資源が乏しい国だという常識を変えなくてはいけないと考えている。
INDEX
・世界的には一般的な洋上風力発電が日本で普及が遅れている理由とは
・固定概念を打ち破る 新しい形の洋上風車
・日本のエネルギー問題解決に向けて、2030年の商用化を目指す
・日本における浮体式洋上風力発電の先駆者的存在として
・なぜ今の職場で働きつづけるのか?
世界的には一般的な洋上風力発電が日本で普及が遅れている理由とは
――洋上風力発電について教えてください。
長壁:洋上風力発電には、海底に基礎を固定する着床式と水深が深いエリアに設置する浮体式の2種類があり、水深50m程度が境目とされています。海の上で風車が回っている写真や映像を見た方は多いと思いますが、それらはほとんど着床式です。着床式は技術が成熟してきており、特にヨーロッパや中国で設置が進んでいます。浮体式はまだ黎明期であり、様々な開発が進んでいて、今後急速に設置が増えていく見込みです。
日本では馴染みはあまりないかもしれませんが、グローバルでは風力発電は太陽光発電よりもメジャーな発電方法です。たとえば日本と同じ島国のイギリスの場合、洋上風力発電だけで全電力供給の30%に迫る勢いです。そのほか、国内の電力消費量が多い中国も圧倒的なスピードでキャッチアップして、今では世界で最も多い洋上風車が新規導入されています。これは水深の浅いエリアが欧州や中国周辺に多く着床式を設置しやすいこと、洋上のオイル&ガス産業のノウハウがあったこと、国の積極的な後押しがあったことなどが主な要因です。
一方で、日本では陸上と洋上風力発電を合わせても電力構成の1%程度です。海に囲まれていることもあり、浮体式風車の開発においてはトップランナーだった時期もあったのですが、今では欧米や中国に比べて洋上風力は10年以上ビハインドの状態だと言わざるを得ません。ただ、洋上風力発電には日本の全電力需要をカバーできると試算されるほどのポテンシャルがあり、この状況は変えなくてはなりません。
――かつて日本でも盛んに開発が行われていたというのは意外です。日本で洋上風力発電が下火になってしまった原因は何なのでしょうか。
長壁:いくつも理由はありますが、一つには地形的な問題が挙げられます。急峻な地形である日本では陸上風車の設置余地が限定的で陸上風車市場が拡大しにくかった。そのため陸上風車の技術の延長である着床式風車の開発に繋がりにくかった。欧米メーカーの陸上風車の売上は洋上よりも何倍も大きいのです。そんな中、グローバルな風車の大型化競争が一気に進み、国内大手メーカーは撤退を余儀なくされた部分もあったと理解しています。
結果的に日本国内では大型風車の技術開発は止まってしまいました。洋上風車システムは風車のブレード(羽根の部分)、発電機、浮体・タワーの主に3つで構成されますが、技術的に難しいのはブレードや発電機の部分です。洋上風力発電のコアとなるこうした技術が国内にはほとんどないのが現状です。つまり、資源はあるのに技術がない、火力発電とは逆の状態にあります。
――国内生産が難しいのであれば、ひとまずは輸入から始めるといったことはできないのでしょうか?
長壁:現実的に今は輸入していますが、調達自体が困難、調達できても高い、欲しいタイミングで買えないなどの問題が起きています。購買先として挙げられるメーカーは実質的に欧米の3社しかありませんが、その3社はグローバルな市場を抱えています。日本のプロジェクトは他の国に比べると小規模になりがちです。しかも台風対策など様々なカスタマイズが求められます。魅力的な市場として映らないことで、調達自体が困難です。また、足元では円安と世界的なインフレの影響により調達コストが高騰しています。
固定概念を打ち破る 新しい形の洋上風車
――日本では洋上風力発電の導入が遅れているということは理解できました。その中で、貴社はどのように洋上風力発電を推し進めているのでしょうか?
長壁:私たちは、FAWT(Floating Axis Wind Turbine)と名付けた浮体式風車を開発しています。前述した通り日本は深い海に囲まれていることもあり、海底に固定する着床式風車を設置できるエリアは限定的です。そこで、洋上に浮かべられる風車を開発。これを実現・普及させるために、主流の水平軸型風車とは全く異なった見た目である垂直軸型風車を採用しています。重い発電機部分を低い位置に置くことで重心を下げ、傾きを許容することで浮かべるのに最適な設計とし、浮体を小型化することで大幅なコスト削減を実現します。


FAWTのイメージ(アルバトロス・テクノロジー提供)
――私たちが想像する風車とは全く違った形をしていますね。これは貴社の独自技術なのでしょうか?
長壁:独自技術部分は当然ありますが、この垂直軸型という形自体は千年以上前から存在しています。今でもたとえば日本のビルの屋上や公園に、小型の垂直軸型風車が設置されていることもありますね。
こうした垂直軸型が大型風車に採用されてきていないのは、実験がしやすい小型機でも発電効率の出やすい水平軸型風車の開発が進んできたためです。陸上風車で一般的な形となった水平軸型の技術をベースに、洋上の着床式風車の開発につながった。洋上でも着床式であれば水平軸型で問題ありません。
しかし、浮かべるとなると事情が変わります。水平軸型はナセルとブレードが構造物のてっぺんに配置され重心が高い。波と風がある中で傾きにくく、転覆させない設計とするために浮体を超大型化しなくてはなりません。洋上に地面を作る必要があるのです。それでは効率が非常に悪いため、これまでの土木や建築発想の技術ではなく、船舶海洋工学をベースとした発想が必要になりました。当社のFAWTの開発にはこれまでとは全く別の要素を加味しなくてはなりません。
――だからこそスタートアップがやるしかないということですね?
長壁:そうですね。これまで積み上げた技術アセットを大きく変え得るため、大手プレイヤーが方針変更の舵を切りにくいところはあると思いますし、そもそもこれまで風車メーカーと言えばブレードと発電機を提供する会社を指しましたが、当社のデザインでは浮体セットで開発が必要なため船舶のノウハウが不可欠です。方針を変え、さらに新たなノウハウを社内に取り込むのは大きな判断が必要でしょう。しかも大手メーカーは先述の通り売上の大きな水平軸型の陸上風車市場を抱えています。
――先ほど日本における洋上風力発電普及への課題を伺いました。垂直軸型であれば、様々な課題は解決できるのでしょうか?
長壁:特にコストとサプライチェーンは解消すべき大きな問題ですが、当社のFAWTはこれを解消できます。水平軸型の洋上風車の場合、発電機は上空150mを超える位置に設置されるため、構造物が大型化し設備費が上がる、また設置に必要な特殊作業船の傭船料も高い。これらの問題に対して、当社の風車は発電機を上空約15mに設置することで重心を下げ、傾きを許容し構造物を最小化し、設備費を下げます。設置に大型作業船が不要で設置コストも大幅に低減します。
調達における問題は、例えば大きな発電機を1台置くのではなく、複数台の数MW単位の小さなものとすることで、日本の既存技術を活用することを考えています。
――なるほど、サプライチェーンの国内化も念頭に置いた上で開発を進められているのですね。
長壁:また、あまり着目されない部分なのですが、実は、洋上風車のライフサイクルコストのうち、40%弱が保守まわりの費用[*]だと言われています。この部分にも貢献できます。
一般的な水平軸型の風車は、複雑な形状をした3枚あるブレードを1枚ずつメンテナンスしていくので時間が掛かります。しかしFAWTでは3枚のブレードを同時にメンテナンスすることができますし、風向きに合わせて首を振る構造など水平軸型には必ず必要な機械系の部品が不要です。これは非常に壊れやすい設備であり、ダウンタイムを大きく減らす効果が期待できます。
*着床式の洋上風力発電の場合。
日本のエネルギー問題解決に向けて、2030年の商用化を目指す
――日本のエネルギー問題の常識を変える、すばらしい技術だと感じました。現在、開発はどの程度まで進んでいるのでしょうか?
長壁:海上に実際に浮かべる実験機の製作段階に入っており、2026年中には初号機を浮かべる予定です。こちらの実験機は全体の高さが30m程度になる予定で、耐久性などを確かめます。特に、台風などの過酷な条件に耐えられることを確かめることが重要な目的の1つです。
また、風車の設計や電力供給に際しては様々な法規制がありますので、そちらの認証ノウハウの構築も進めており、2030年頃には商用化を実現させたいところです。今回の実験機は全長30m程度と比較的小型の発電機を想定していますが、大型化に向けた実証準備をNEDO事業で同時並行で進めています。

――経済産業省は、2040年度の発電電力量のうち、風力は4~8%程度を占めるものと見通しています。こうしたシナリオにも大きく貢献できそうですね。
長壁:こちらの4~8%という数値は、外国から部品などを買う想定での見通しだと認識しています。当社の事業が軌道に乗ればさらなる上乗せや、2040年とされている年次の前倒しも可能になるかもしれません。
日本は2050年のカーボンニュートラルを謳っています。そのためには、2030~2040年代にはフルスイングできる段階にもっていかなければならない。当社としても、そうしたスケジュール感で開発できるよう尽力します。
――経済産業省の第7次エネルギー基本計画原案でも、洋上風力発電は注目されています。これほど着目される理由は何なのでしょうか?
長壁:カーボンニュートラルに抜本的な貢献を果たせるほどの発電ポテンシャルが1つです。洋上風力発電は前述した通り、日本の全電力需要をカバーしうる発電方式です。ポテンシャルのうち何%かを使うだけでも莫大な発電量を確保できます。
また、将来的な発電コストの低下余地も挙げられます。欧州では火力発電のコストを下回りつつありますし、温室効果ガスの排出による外部コストや原発事故のリスクを計算に織り込んだ際には、風力発電の優位性は非常に高いです。石炭や石油に依存する発電の場合、海外から資源を輸入しつづけることになります。しかし風力発電の資源は無料の風であり、ペイバックという概念も成り立ちます。
日本における浮体式洋上風力発電の先駆者的存在として
――洋上風力発電は今でこそ着目されていますが、貴社が研究開発を開始した10年以上前には国内での注目度は大きくありませんでした。他社に先行して事業を開始した理由は何だったのでしょうか?
長壁:当社代表の秋元は船舶海洋工学を専門として東京大学や大阪大学で教員をしていたこともあり、船に着想を得て開発を進めてきました。船舶の専門家にとって、既存の風車のように重心が高い構造物を海上に浮かべるのは無駄が多く、これをどのように変えられるかをかねてから考えていました。一般的な水平軸型の風車は建築や土木をバックグラウンドとして開発されてきたため、船舶の専門家にとっては非効率に見えるところも多かったようなのです。
2011年に東日本大震災が起こりました。災害をきっかけに、海外に依存しない、できれば原子力発電に依存しないようなエネルギー供給を志したのです。震災の翌年、2012年に創業して以降、資金調達は中々進まず、2022年にようやく資金調達ができました。それ以降電力会社などの大手企業も共同研究で参入してくださり、開発が大きく前進したという流れです。

――通常の風車が建築や土木を背景に開発されてきたところ、船舶の専門家として新しい視点を持ち込んだということですね。後発プレイヤーならではの視点もありますね。
長壁:水平軸型のブレードはタイ焼きのように型で作ります。ブレードが120mを超える長さですので大型工場や広大な保管場所も求められます。断面形状も複雑で、要求される設計・製造技術も高いわけです。
これに対して私たちの風車は全てのブレードを同一断面形状で設計しているため、鋳型成形だけでなく引抜成形という自動プロセスによる作り方も選択肢として入ってきます。さらに、垂直軸型風車の構造上、アームごとに分割してブレードを作ることができるので、120mのブレードでも、40mに分割して大量生産するといったこともできます。そうすれば保管しやすいですし、輸送もより簡単になります。国内で調達しやすいデザインとなっています。
――ありがとうございます。こうした技術が開発されていることは、日本にとって大きな前進だと理解できました。
長壁:日本は化石燃料を毎年30兆円かけて輸入しているなど、エネルギーの海外依存が大きい国です。学校では「日本は資源が乏しい国」と誰もが習うのですが、実際には日本には風という資源が豊富にあるわけです。私たちの垂直軸型風車は日本の経済にとって必要な技術ですし、日本は資源が乏しい国だという常識を変えなくてはいけないと思っています。
なぜ今の職場で働きつづけるのか?
――最後に、長壁さんのキャリアについてもお伺いします。もともと船舶工学を専門とされているわけではなかったとお伺いしていますが、なぜ貴社にジョインされたのでしょうか?
長壁:良く転職を考える際に、今後何をしたいのか?と次のことを考えがちですが、私はかつて一部上場の大企業で勤めていた際、「なぜ今の職場で働きつづけるのか?」を考えていました。当時の企業は確かに恵まれた環境でしたが、待遇面だけを理由として働きつづけるべきとは考えませんでした。この企業に留まるべき理由が明確に描けない中で、退職して留学することにしました。
留学後は、外資系企業や地方の中小企業で働いたこともあります。自分の強みは何か、自分は社会に何を求められているのか、一生かけてやりたいことは何かを、環境を変えながら自問自答しつづけることで、自分のキャリアが徐々に縁取られてきたイメージです。
そうした中で、VCの方にお声がけいただき、当社代表の秋元と話してみることになりました。秋元は、震災の翌年から10年間にわたって1人で戦い続けていました。私がプロボノとして半年ほど働いてみたところ、アルバトロス・テクノロジーが社会に求められていることは当然ながら、私自身がこの企業に求められていることにも気づきました。当社の代表はあくまでも研究者なので、ビジネスサイドは私が引き受け、FAWTを世に出さなくてはならないという使命を感じ、正式な入社を決断します。

代表取締役 秋元博路氏
――風力発電の領域はまだまだ新しく、数十年単位でのコミットを求められる領域です。従来のキャリアの延長線上ではない領域に飛び込まれたのはすごい勇気だと感じました。
長壁:もやもやとこのままで良いのか、を考え続けたこともそうですが、かつて1年間、ヨーロッパに留学していた経験も大きいのだと思います。50か国くらいから学生が集まる大学院での留学経験だったので、様々な人との出会いがありました。印象的だったのがレバノン人との出会いです。レバノン人は自国の産業が弱く、自分たちの力で会社を興すのが当たり前といった価値観です。日本の”就職活動”は世界では特異だと気付きました。いろいろな価値観を持つ人に揉まれたことで、こうした決断ができるようになったのだろうと思います。
特にエネルギー系のディープテックについては、おっしゃる通り10年単位での勝負になってきます。また、自社だけでなく、国の後押しもなくてはならないなど、非常に不確定要素の多いビジネスです。人生の中でも長い時間をかけることになるので、志や想い、あるいはどれだけ考え、行動し倒したかが問われるのかなと思っています。
――ありがとうございました。この記事を読んだ人に向けて伝えたいことはありますか?
長壁:当社では現在、5社との共同研究を進めていますが、研究開発やサプライチェーンの構築には仲間がもっと必要です。会社として、当社の社員やアドバイザーとして、ご関心があれば是非ご連絡ください。1つの大きな産業を新しく作ることになるので、日本企業が持つアセットをフル活用して産業を盛り上げていければ幸いです。
私たちは風車を作る会社ですが、その目的は特に日本のエネルギー問題への貢献です。再エネ比率を上げれば、化石燃料の調達にかかっていたコストの大幅な削減につながります。風力発電を含めた再生可能エネルギーによって、安定した電力供給を守ることはもちろん、数兆円単位で浮いたお金を使ってより良い国づくりを進めることもできます。わたしたちの浮体式風車FAWTは日本にとって欠かせない技術であると信じています。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:宮崎ゆう
撮影:阿部拓朗




 エネルギー
エネルギー