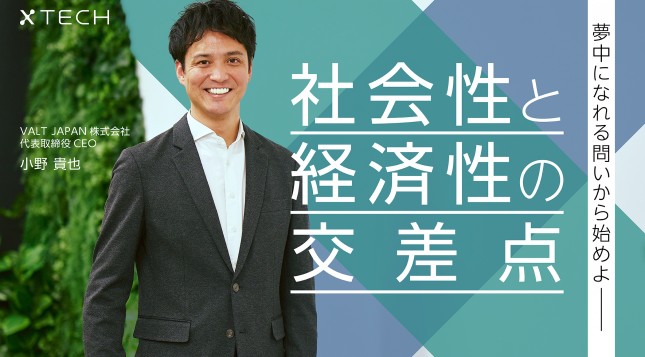がん治療薬の効き目を“見える化”——北大発スタートアップHILOが挑む、分子標的薬最適化の社会実装
読了時間:約 9 分
This article can be read in 9 minutes
がん治療は、いまだに“薬を試してみないとわからない”という不確実性の上に成り立っている。高額な分子標的薬や免疫療法であっても、すべての患者に効くわけではなく、「この薬が効くのかどうか」を事前に判断する術は限られているのが現実だ。
そうしたなか、患者ごとの“実際の薬効”を事前に見極める診断技術を開発したのが、HILO株式会社。北海道大学発スタートアップである同社は、生きたがん細胞の反応をリアルタイムに観察することで、“効く薬”を科学的に見える化する独自技術を武器に、がん医療の在り方を根本から変えようとしている。
技術の可能性と社会実装の裏側について、代表取締役・天野麻穂氏に話を聞いた。

天野麻穂
HILO株式会社 代表取締役
1995年、お茶の水女子大学 理学部化学科卒業。1997年、同大学大学院修士課程修了。2000年、東京大学大学院 農学生命科学研究科応用生命化学専攻博士課程修了。米UCLAでの研究生活を経て、2006年より昭和女子大学 生活科学部講師。2007年北海道大学 大学院先端生命科学研究院 特任助教に着任。その後、学内の研究活動を推進支援する専門職 ・URAに転じ、2019年に医学研究院に移籍。NEDO TCP 2020 (Technology Commercialization Program)最終審査会にて最優秀賞受賞。2021年8月HILO株式会社を起業。
ポイント
・HILOの独自技術は、薬の効き目を“治療前に見える化”。 従来の遺伝子検査と異なり、生きたがん細胞の反応をリアルタイムに観察。効く・効かないを色で明確に示し、患者に最適な治療法を科学的に選ぶことができる。
・治療の無駄をなくし、医療費と患者負担を軽減 効かない高額な薬の投与を未然に防ぎ、医療費の最適化に貢献。患者の身体的・経済的負担を減らし、より納得感のある治療選択を可能にする。
・大学発ディープテックの社会実装モデルで、北海道大学の基礎研究から生まれた技術。既存ビジネスモデルに合わず埋もれがちだった技術を、代表自らが起業し社会実装を推進。大学の支援制度を活用し、正規教員との兼業を実現した。
・診断から創薬まで広がる技術の可能性 現在は分子標的薬の薬効判定が中心だが、将来的には患者細胞を使った創薬ターゲット絞り込みや新薬スクリーニングにも応用。がん医療全体の精度向上に貢献が期待されている。
・大学発のスタートアップに重要なのは、“この技術を社会に出すべきだ”という確信と、その思いを貫く勇気。
INDEX
・薬が効くかどうかを「治療前に見える化」する。HILOが切り拓くがん治療の未来
・「この薬は本当に効くのか?」——“実証型”診断技術が生まれるまで
・なぜ“起業”を選んだのか。大学発技術を社会実装に導くまでの道のり
・医療現場への実装とその先へ——診断から創薬まで広がるHILOの可能性
・“技術を埋もれさせない”という決意——HILOが描くがん治療のこれから
薬が効くかどうかを「治療前に見える化」する。HILOが切り拓くがん治療の未来
――まずはHILOの技術について聞かせてください。
天野:私たちは、生きたがん細胞に複数の薬を作用させ、それぞれの効果を1細胞単位で見極める診断技術を開発しています。従来の遺伝子検査は“この薬が効きやすい可能性がある”という予測にとどまっていました。
しかし、私たちの技術は、薬が効いているか“実際の反応”をリアルタイムで可視化し確認できるのが特徴です。患者本人の細胞を使って判定するため、現場の医師にとっても判断の説得力が高く、患者さんにも納得いただきやすい診断を可能にしました。
――薬が効いたかどうかを、どのように可視化しているのでしょうか?
天野:我々が対象としている分子標的薬という種類の治療薬は、がんの原因となる物質だけを標的に攻撃します。分子標的薬を投与した後、分子標的薬の標的であるがんの原因となる物質に、活性があれば薬は効いていない、活性がなければ薬が効いていることになります。その変化を光に変換する独自のバイオセンサーを使い、細胞の色が青に変われば“効いた”、赤や黄色に変われば“効かなかった”と一目で判別できる仕組みです。
この反応を生きたままの細胞で観察できるのがHILOの強みであり、効かない細胞が効く細胞の中に少数混ざっているような複雑ながんにも対応できる点が、既存の技術と大きく異なります。
――どのような患者さんにとって、特に効果的なのか教えてください。
天野:特に恩恵が大きいのは、分子標的薬など“効く人には劇的に効くが、効かない人には全く効かない”という薬を使うケースです。たとえば慢性骨髄性白血病では、複数の治療薬がある中で、患者さんごとに効きやすいものが異なります。
そのような場合も試行錯誤を繰り返すのではなく、事前に自分に合った薬の種類と量を見極められれば、より早く、より少ない副作用で病状の改善を目指せます。私たちは、この個別最適な治療を支えるインフラになりたいと思っています。

――診断精度や臨床現場での反応はいかがですか。
天野:予測精度は現時点で90%前後です。特に“効かない薬を外す”精度が高く、医師の方からは“現場感覚と非常に近い”という声をいただいています。ある先生からは『これまでの経験と勘に頼っていた部分に、科学的な裏付けが加わる』という評価もありました。
また、患者さんにとっても“事前に効く薬がわかっていれば、治療に前向きになれる”という声が印象的でした。色で見える変化が、医師との対話や意思決定をサポートする大きな手助けになっていると感じています。
――この技術が社会実装されることで、どんな社会的影響があるか聞かせてください。
天野:私たちの診断技術が普及することで、治療の無駄を減らし、医療費の最適化にもつながると考えています。高額な薬が効かなかった場合のコストロスは非常に大きく、医療財政に与える影響も無視できません。
患者さんにとっても、身体的な負担や経済的な負担の軽減につながり、より納得感のある治療選択が可能になります。がん治療薬が効くか見極めるまでに半年などの期間を要することが多く、かつ分子標的薬などは高額な上に、副作用が辛いものもあります。効くか効かないかわからない不安のなかで、高額な治療を続けていたのが現状でした。医師にとっても、確かな根拠に基づいた治療方針を立てやすくなるはずです。
「この薬は本当に効くのか?」——“実証型”診断技術が生まれるまで
――HILOの技術はどのようにして生まれたのでしょうか?
天野:この技術は、北海道大学の大場教授がライブセルイメージングという分野の基礎研究から生み出されました。ただし、もともとは細胞の中で起こっているタンパク質の活性化やイオン濃度の変化を可視化する研究で、臨床検査目的ではなかったのです。
しかし、血液内科の臨床医から、がん治療薬の選択に困っているという声をいただいて、基礎研究から臨床検査という実用化に向けた動きが始まりました。
――実用化に向けて乗り越えてきたハードルがあれば聞かせてください。
天野:細胞を生きたまま運んで臨床検査する仕組みを作る必要があり、プロセスの構築には苦労しています。また、これまでの製薬企業や臨床検査会社のビジネスモデルには合致しないため、ライセンスアウトも困難で、研究者だけでは進めにくいという現実もあったと思います。
それでも、この技術は社会的ニーズが非常に明確だったため、”面白い技術”で終わらせるのではなく、ぜひ臨床応用すべきだと感じていました。

――どのような経緯で起業に至ったのでしょうか。
天野:私は大学のURA(リサーチ・アドミニストレーター)として、このプロジェクトを発掘しました。研究者と社会をつなぐ立場で、臨床の課題や患者さんの声、技術の可能性を間近に見てきたのです。
最初は起業するなんて考えていませんでしたが、この技術を社会に届けたいという使命感から起業に至りました。技術の価値を一番深く理解していて、関係者との信頼関係も築けていたのは私だと思ったからです。
それならば、自分がやるのが一番早いんじゃないかと。誰かがやらなければ、技術が埋もれてしまうという危機感に、背中を押されました。
なぜ“起業”を選んだのか。大学発技術を社会実装に導くまでの道のり
――なぜ自ら起業する選択を取ったのでしょうか?
天野:社会実装が進まないまま研究室に埋もれていく姿を見て、“このままじゃいけない”という焦りがあったからです。製薬会社や検査会社に打診しても、“既存のビジネスモデルに合致しない”、”事業のリスクにもなり得る”という理由で前向きな反応が得られず、他に動く人もいなかった。
それならば、自分がやってみよう、と決断したのです。
――起業にあたり、大学側との調整についても聞かせてください。
天野:ちょうど私が起業準備をしている間に、大学で“スタートアップを支援する”という風潮が生まれ、制度の整備も進んできました。2021年に会社を立ち上げた際、私は当時北海道大学の正規教員だったのですが、代表取締役との兼業が認められるようになったのです。そのおかげで、正式に両立が可能になりました。
そのような次第で、私は、正規教員として兼業代表取締役となる初めてのケースになりました。ただし制度が整ったばかりで前例が少なかったため、利益相反や兼業の線引きなど、多くの課題について大学と一緒に走りながら考えつつ、進めることとなりました。

――大学教員が企業経営に関わることに対して、学内での反応はいかがでしたか?
天野:当初はまだ理解が進んでおらず、“ベンチャーの社長?”と半ば冗談のように受け取られることもありました。大学教員たるもの、教育と研究に一生を捧げるべきだという空気も強くて、企業経営に時間を割くことに懸念の声があったのは事実です。
ただ、近年は“週の何割を大学業務、何割を事業に”といったエフォート配分の考え方も浸透してきていて、少しずつですが現実的な対応が進んでいると感じています。
――現在は特任教員として活動されているそうですね。
天野:はい。正規教員時代は授業の責任が重く、スタートアップとの両立は非常に難しくて。現在は特任教員として授業を持たず、研究とスタートアップ支援の両立に集中できるようになりました。
現在はHILOに完全コミットしており、本格的に事業を拡大していくフェーズに入っています。
医療現場への実装とその先へ——診断から創薬まで広がるHILOの可能性
――現在、HILOの技術がどのような形で医療現場に提供されているのか聞かせてください。
天野:現時点では自由診療および研究利用というかたちで、一部の医療機関と連携しながら提供を始めています。まだ薬事承認前の技術ですので、公的保険の対象にはなっていませんが、“効く薬を見極めたい”という患者さんや医師からの強いニーズがありこの形が実現しています。
いまは限られた環境での社会実装を少しずつ進めている段階ですが、臨床のフィードバックを得ながら、現場で本当に使いやすいサービスにしていきたいと思います。
――薬事承認は、今後の事業展開にとって大きな節目になると思います。どのようなスケジュール感で進めているのでしょうか?
天野:厚生労働省への申請準備は進めており、2026年度中には薬事承認の申請を目指しています。私たちの技術は“診断補助”という位置づけになりますが、精度の高さや実際の治療結果との相関性について、しっかりとエビデンスを積み上げていかなければなりません。
プロセスには時間がかかりますが、丁寧に実績を重ねることで、多くの医療機関に安心して導入してもらえる体制を整えたいと考えています。
――診断の提供にあたって、臨床医との連携体制はどのように築かれているのでしょうか?
天野:血液がん領域におけるKOL(キーオピニオンリーダー)の先生方と密に連携し、臨床研究を進めてきました。研究利用の枠組みでは、患者さんに無償で診断を提供しているケースもあり、論文データの蓄積と薬事承認に向けた信頼性の構築を両立しています。
また、現時点では、一般の医療機関でも患者さんの経済的負担を抑えるため、受託研究として先生方の研究費でまかなっていただく仕組みを活用しようとしています。まだ広く公的な保証があるわけではない段階だからこそ、“いかに負担をかけずに届けられるか”という視点を大切にしています。
――分子標的薬の特定以外にも技術は活用できるのでしょうか?
天野:創薬の分野においても、私たちの技術は高い可能性を持っていると考えています。実際に患者さんのがん細胞ひとつひとつの薬効を測定できるという特性から、創薬のターゲティングやスクリーニングにも非常に相性がいいんです。
実際の患者細胞を使って新薬候補を絞り込むことで、臨床試験の成功確率向上や、特定の患者層に効く薬の事前選定につなげられると期待しています。現時点では薬効判定が中心ではありますが、今後は創薬プラットフォームとしての価値も着実に広げていきたいですね。
“技術を埋もれさせない”という決意——HILOが描くがん治療のこれから
――研究から事業化までの道のりを経て、いま描いている未来を聞かせてください。
天野:今は、慢性骨髄性白血病に特化していますが、がんの種類やステージにかかわらず、“治療前に薬の効き目を見極める”というアプローチが医療の当たり前になる未来を目指しています。血液がんから始めた取り組みを、将来的には固形がんや難治性がんなどにも広げていきたいです。
また、診断だけでなく創薬や他分野への応用も視野に入れながら、私たちの技術が、医療の精度と効率を根本から変えるインフラになると信じています。

――将来的な事業展開の選択肢として、資本提携やM&Aも視野に入れているのでしょうか?
天野:選択肢として視野に入れていますが、私たちにとって最も大事なのは、“診断技術を確実に患者さんへ届けること”です。よりスピーディに、より多くの医療機関に普及できるのであれば、他社との連携や資本提携、M&Aといった形も積極的に検討します。
もちろん、単独での成長やIPOの道も視野に入れていますが、“届けること”を最優先に、柔軟な姿勢で展開していきたいですね。
――最後に、スタートアップを目指す方や大学の中に眠る技術に関わる方々へ、メッセージをお願いします。
天野:起業を考えている方の中には“自分にできるだろうか”と迷う人も多いと思います。私も最初は何もわからないところからのスタートでした。
大切なのは、“この技術を社会に出すべきだ”という確信と、その思いを貫く勇気です。技術は放っておくと簡単に埋もれてしまいます。でも、誰かが動けば、そこから道が拓ける。迷っているなら、その“誰か”になってほしいと思います。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:鈴木光平
撮影:阿部拓朗




 ディープテック
ディープテック