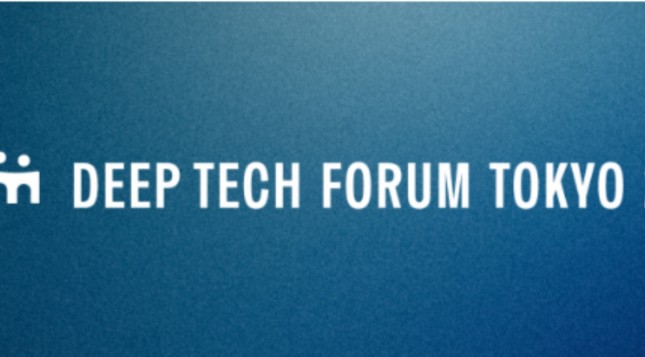都市、ビジネス、人々の共生。最先端技術が導く社会課題解決への道筋【東大Week@Marunouchi DAY2】
読了時間:約 12 分
This article can be read in 12 minutes
東京大学の最先端の知見に触れる「東大Week@Marunouchi」の2日目が2024年7月31日、丸の内の2会場で開催された。イベントでは4人の東大教授陣が登壇。現代社会が直面する様々な課題に対する革新的なアプローチが紹介された。技術革新と社会課題解決の融合という共通テーマのもと開催された各講演は、未来社会の在り方を考える貴重な機会となった。本記事では、各講演の要点とそこから得られる示唆をレポート。学術界と実業界の架け橋となる本イベントの意義と、そこから見える日本の未来像に迫る。
INDEX
・デジタル化によるインフラと産業の変革
・ビジネスと社会的責任の変遷
・革新的新製品のブランド戦略の課題
・多様性と都市空間の現状と課題
デジタル化によるインフラと産業の変革

会場の一つである「GARB Tokyo」でまず登壇したのは、東京大学大学院情報理工学系研究科教授
の江﨑浩氏。九州大学大学院を卒業後、東芝に入社。米国ニュージャージ州 ベルコア社(現iconectiv社)客員研究員、コロンビア大学の客員研究員を経て、2005年に東京大学の教授になっている。現在は、東大グリーンICTプロジェクトの代表も務めている。
講話では、「DN(デジタルネイティブ)とCN(カーボンニュートラル)同時実現への挑戦」をテーマに、モノとコトが分離されることでの変化について語られた。
江﨑「デジタル化は従来のインフラの概念を根本的に変革し、コスト削減と効率化をもたらします。たとえば、社会インフラ構造は鉄道や道路などの面、空港や港湾などの固定点、固定の場所を必要としない移動点、という3種類に整理できます。地方財政で大きな費用が発生するのは、面である道路や橋梁。これらが必要なくなれば港をつくった方がコストを抑えられますし、ドローンや空飛ぶクルマが普及すれば物理的なインフラに依存する必要がなくなります。
また、物理的なモノ(荷物)の移動には大量のエネルギーが必要ですが、ビット(通信)の移動であれば、その1万分の1のコストしかかかりません。このように、デジタル化がすすむことで企業や自治体の費用負担が軽減され、より持続可能で効率的な経済運営が可能となります」

江﨑「より身近な例で示すと、従来、新聞社は新聞を販売するために専用の印刷機を保有し、独自のデリバリーシステムと集金システムを確立していました。これがデジタル化によって、すべて必要のないものになったのです。デジタル版の新聞は圧倒的に少ない資源でメディアを提供できるようになったうえ、瞬間的に地球の裏側まで情報を送れるようにもなりました。
では、デジタル化は産業界にどんな影響を及ぼすのでしょうか。19世紀以前、物流業界は排他的な個別網を持っていましたが、コンテナパレットの発明により物理空間のシェアリングエコノミーが可能となり、効率が劇的に向上しました。
具体的には、トラックや船で食品や機械部品など種類の違う品をまとめて運べるようになったのです。現在はサイバー空間のシェアリングエコノミーが同様にすすめられています。たとえば、一般家庭ではレシピ本を買わずにアプリで電子レンジのレシピを確認したり、製造業ではプログラムを送信して3Dプリンタで製品を出力したり。モノ(Physical object)からバイト(Digital object)へ置き換えることで、移動コストの効率化や廃棄物の削減がすすみ、エネルギー効率の大幅な向上が実現しています」

江﨑氏は、デジタル化による遠隔作業の普及は、オフィスの物理的な必要性や不動産価値にも影響を与えており、不動産業界はビジネスモデルの見直しを迫られていると続けた。
江﨑「モノを起点とした発想からデジタルを主軸とした新たなモデルを開発するか、人が集まるようなより高いバリューをモノに付与するか。既存の資源を再利用して最適化を図りつつ、カーボンニュートラルを意識した発想を持って、これからの持続可能な社会に対応する必要があるでしょう。
ここからは具体的な実例を紹介します。たとえば、ドイツの某自動車メーカーではリアルタイムでの反応が必須ではない80%の製造業務を、再生エネルギー先進国であるアイスランドやスウェーデンで行っています。この取り組みによって、地代や電気料金などのキャッシュアウトを減らすとともに、CO2排出量の大幅な削減に成功。地球に優しい企業というブランディングとプロフィットの最大化を両立したのです。
一方、日本においてもエネルギー需要の典型的な産業として、データセンターと半導体製造工場をピックアップし、再生可能エネルギーや通信ネットワークの効率的な活用を推進しています。具体的には、北海道や九州に新たな産業の中核拠点を設立。DX化による新規の価値創造を行いつつ、初期費用とランニングコストの効率化を図ることで、資源と消費するエネルギーを同時に削減しようという取り組みです。将来的には海底ケーブルをヨーロッパや北米につないでいくことを構想しており、日本が国際的なデータ流通のハブとしての役割を担うことを目指しています。
今後さらに、ドローンや空飛ぶクルマ、移動型の電力源が普及していけば、既存インフラへの依存が必要なくなり、コストやカーボンフットプリントが大きく下がることが見込まれます。デジタル化とネットワーク化によって、自由に、安価に、超高速に、動き回れるようになる世界が実現され得るのです」
ビジネスと社会的責任の変遷

続いて登壇したのは、東京大学大学院経済学研究科准教授の山本浩司氏。慶應大学を卒業後、ヨーク大学の歴史学研究科にて博士号を取得し、ロンドン大学、ケンブリッジ大学などの研究員を経て、2018年より東京大学大学院の准教授となっている。2016年には、歴史研究の支援と活性化を目的とした日本全国の大学を繋ぐ研究者組織「歴史家ワークショップ」を立ち上げ代表を務めている。
今回の講話のテーマは「ビジネスは社会課題を解決できるのか ー歴史とジェンダーの視点から」。ヨーロッパの歴史を紐解とくと、ビジネスを社会課題の解決に役立てようという考えには400年の歴史があるという。ビジネスがどうすれば社会課題を解決できるのかについて、ジェンダーの観点も交えながら語られた。
山本「ノーベル賞を受賞したマクロ経済学者のミルトン・フリードマンはその著名なエッセイで、『ビジネスの社会的責任とは、その利潤を最大化することにある』と主張しました。この考え方は長年にわたり、ビジネスの基本原則として受け入れられてきました。しかし、現代の学生たちは、フリードマンの主張に対する納得感を次第に失ってきています。その背景には、SDGsといった社会的価値観の普及があると考えられます。フリードマンの論はアダム・スミスの『国富論』に基づいており、自身の利益を追求することが結果的に社会全体の利益を促進するというものでした。しかし、現代においては、こうした考え方に対する異なる視点が広がりつつあります。
資本主義の歴史を振り返ると、ビジネスはしばしば労働者や自然資源を搾取するものとして描かれてきました。しかし、社会的責任を果たすという観点から、ビジネスが推進された例も存在します。たとえば、1698年にウェールズで設立された銅山会社は、株主を募る際に利益還元だけではなく、『雇用創出や地域発展』という社会的な価値を前面に押し出していました。これは、CSRが現代社会の新しい概念ではなく、300年前から同様の発想が存在していたことを示しています」


山本「さらに、当時も多様な株式投資の手法が存在し、ビジネスマンに対する批判も盛んでした。特に、社会貢献を謳いながら実際には私利を追求する企業への風刺画が多く確認されています。こうした批判の文化は、過去から継続して存在しており、ビジネスの社会的責任がいかに歴史的な問題であるかが浮き彫りになっています」
社会課題の解決にはジェンダー視点も重要だと、山本氏は続けた。歴史的に見て、ビジネスや経済活動は男性主導ですすめられ、社会に与える影響やその社会的責任についての議論も、男性視点が強調されがちなのだという。
山本「ビジネスにおいて、男性視点が強調されますが、実際は女性もまたビジネスや経済活動の一部を担っており、特に家庭内での労働や、日常的な経済活動において重要な役割を果たしてきました。
この観点から注目すべき事例が、近世イギリスにおける石鹸の独占問題です。石鹸は当時の生活必需品であり、特に洗濯において不可欠なものでした。清潔さが社会的なステータスを示す重要な要素であった時代において、石鹸を独占する企業は洗濯を担う女性たちに大きな負担を与えました。しかし、この問題は当時の男性主導の視点からは、石鹸を製造する男性労働者の権利侵害としてしか語られず、女性たちがどのような影響を受け、その声がどのように無視されてきたのかについては言及されていないのです。
このように、ビジネスが社会に与える影響を議論する際、ジェンダーの視点を取り入れることは極めて重要です。石鹸の独占問題は一例に過ぎませんが、女性たちの視点や経験が歴史のなかで無視されてきたことを示しています。こうした過去の事例から学び、現代のビジネスにおいても、男女両方の視点を考慮した社会課題の解決が求められます。
では、ビジネスが社会課題を解決するために、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。現代のビジネスが社会課題を解決する力を持つかどうかは、単なる利益追求にとどまらない複雑な問題です。歴史的に見ても、ビジネスが社会に与える影響は大きく、ときには意図せずに社会課題を悪化させることもありました。そのため、ビジネスの役割については、より多角的な視点からの検討が必要であり、ジェンダーの視点を取り入れることが不可欠であると考えています。
今回の講演を通じてCSRやSDGs、ESG投資といった概念が、実際には資本主義の初期から問題設定されてきたことがご理解いただけたのではないでしょうか。これからの社会課題解決においては、これらの歴史的教訓を踏まえ、ビジネスの役割を再評価することが重要なのです。ジェンダーの視点を含めた包括的なアプローチが必要であり、そのためには大学や研究機関だけでなく、広く社会全体での対話が求められます」
革新的新製品のブランド戦略の課題

もう一つの会場「ADRIFT by David Myers」で登壇したのは、東京大学大学院経済学研究科教授の阿部誠氏。阿部氏はマサチューセッツ工科大学大学院で博士を取得後、フンボルト大学(ドイツ)、UCLA、イェール大学、ニューサウスウェールズ大学(シドニー)、シンガポール国立大学にて、客員教授、准教授、研究員を歴任し、2003年にJournal of Marketing Educationからアジア太平洋大学のマーケティング研究者 第1位に選ばれている。
今回、「革新的新製品に対する消費者の製品評価・需要可能性を高めるためには?~緑の珈琲がアリで無色のコーラがダメな理由~」と題し、革新的なアイデアやイノベーション受け入れてもらうためにはどうすればいいかを行動経済学、消費者心理の観点から紐解いた。
阿部「ブランドとは単に製品やサービスを名前として表すものではなく、消費者がそれに対して抱く感情や価値観が深く関わるものです。そのため、ブランド戦略において消費者心理を理解することは極めて重要であり、特に『選択的知覚』という人間の特性は無視できません。
選択的知覚とは人間が自ら意識したものにしか注意を払わない性質を指し、ブランドが消費者の意識にどう入り込むかが鍵となります。このため消費者心理を理解し、どのように製品やサービスが知覚されるかを考慮したブランド戦略が求められるのです。
マーケティングにおいて、新製品は大きく2つに分類されます。1つは革新的新製品(RNP: Really New Product)であり、もう1つは漸進的新製品(INP: Incrementally New Product)。革新的新製品は、既存の製品カテゴリーを超えて全く新しいカテゴリーに分類されるような製品です。これに対して漸進的新製品は既存の製品に改良を加えたものであり、消費者にとっては理解しやすく、受け入れやすい特徴があります。
実際、ある研究によると、漸進的新製品は革新的新製品に比べておよそ4倍の確率で選択されることがわかっています。消費者が新しいカテゴリーや機能を理解するのに時間がかかり、リスクや便益に対して懐疑的になるためです」
阿部氏は、1992年頃に発売された透明なコーラ「Crystal Pepsi」が市場に受け入れられなかったことを例に、革新的新製品が消費者に受け入れられることの難しさを語った。
阿部「革新的新製品の受容性の低さを解消するにはどうすれば良いのでしょうか。Crystal Pepsiが市場に受け入れられなかったことは、『スキーマ一致効果』と呼ばれる消費者心理のメカニズムで説明できます。スキーマとは、ある対象や出来事に関して記憶されている情報や知識のネットワークを指します。製品がスキーマと不一致である場合、注目度は高くなりますが、不一致のレベルが極端すぎると消費者はその製品を理解することをあきらめてしまいます。一方、適度な不一致が生じると、一定の注目を集め、消費者が活発な情報処理を行うバランスのよい状態が生まれます」

阿部「このようなメカニズムから、革新的製品は既存カテゴリースキーマとの完全な不一致により、理解困難な製品となることがあるのです。その受容可能性を高める手法の1つが『イネーブラ(意味付け)』です。イネーブラは革新的新製品に対しても、消費者の理解に対する『手掛かり』として機能し、既存スキーマに新たな意味付けを行い、製品を受け入れやすくしてくれます。
このイネーブラの有効性を示す論文が、イギリスの研究チームから発表されています。この実験では、ビタミン入りとビタミンなしの3色(黒色・緑色・赤色)のコーヒー、計6種類を用意しました。実験参加者は、それぞれのコーヒーについて『飲んでみたいか』『関心があるか』を評価しました。
その結果、ビタミン入りのコーヒーは緑色と赤色が黒色よりも高評価を得ました。これは、緑色や赤色という『色』が、野菜や果物などを想起させるイネーブラとして機能し、ビタミン入りコーヒーが肯定的に受け入れられたと考えられます。一方、『透明なコーラ』には適切なイネーブラが存在しなかったため、消費者はその製品を理解できず、結果として市場に受け入れられなかったのではないでしょうか。
では、改めて消費者の需要可能性を高めるブランド戦略について考えていきましょう。革新的新製品が市場で成功するためには、完全な不一致を適度な不一致に置き換え、受容可能性を高めることが重要です。このためには、イネーブラを適切に用いることが効果的なブランド戦略の1つとなります。
たとえば、Crystal Pepsiの販売を成功させるためには、『透明=天然水』というイネーブラを活用することで、消費者に『自然で健康的な飲み物』というイメージを植え付けることができたかもしれません」
最後に、革新的新製品は適切なイネーブラを導入することで、消費者の受容可能性を高めることができるだろうと締めくくった。
多様性と都市空間の現状と課題

続いて登壇したのは、東京大学大学院情報学環准教授の澁谷遊野氏。澁谷氏は同大学の大学院情報学環・特任助教、空間情報科学研究センター・准教授を経て、2024年より現職につき、空間情報、社会情報学などを中心に、都市空間・デジタル空間での人々の行動の多様性や異質性、参加に関する研究に従事している。
「多様で包摂的な都市空間デザインのための人流解析とシミュレーション」のテーマで、人流解析やシミュレーションを通じて、人々の行動や経験の格差やその要因を紐解いた。
澁谷「都市空間における多様性は、現代社会においてますます重要になっています。都市に住む人々が、自分とは異なる年代、趣味嗜好、国籍、ライフステージなどを持つ他者とどの程度接触しているかが、都市空間の豊かさや包摂性を測る1つの指標となります。しかし、日常生活において、私たちはしばしば同じような背景や価値観を持つ人々とばかり接触しがちです。この現状を改善し、より多様で包摂的な都市空間を実現するためには、人々の行動を正確に把握し、その多様性を解析する技術が求められます。近年、スマートフォンから収集されるGPSデータを活用し、こうした人々の行動や接触のパターンを解析する取り組みがすすめられています。
昨今、都市への人口集中と、その多様化がすすむなかで、都市内の格差や孤立が問題視されています。国連の予測によれば、2050年には世界人口の3分の2が都市部に居住するとされています。日本でも、東京への人口集中が顕著であり、それに伴う都市内・都市間の格差が拡大しています。また、多様化に伴い、高齢化や家族構成の変化、外国にルーツを持つ人々の増加が都市空間に新たな課題をもたらしています。これに対処するためには、異なる背景を持つ人々が接触する機会を増やし、偏見や対立を軽減することが重要です。たとえば、集団間接触理論では特定の条件下での異なる集団間の接触は、偏見の減少や集団間対立の軽減に寄与することが報告されています。
具体的な研究として東京圏における世帯年収の異なるグループ間の接触を分析しました。結果として、勤務先での格差は比較的小さいものの、余暇活動においては同じような世帯年収の人々とばかり接触していることが明らかになりました。特に、子どもを持つ女性は、男性に比べて空間的な孤立が大きいことが確認されています。
さらに、非平時やデジタルソリューション介入時の行動変容に関する調査結果をお伝えします。世界銀行と共同で実施した、ウクライナ侵攻直後の避難行動の調査では、比較的裕福な地域に住む人々がより遠方へ避難する傾向が確認されました。この行動の背景には、車の所有やその他リソースなど多様な影響が推察されます。また、コロナ禍の台湾ではマスクの在庫状況をタイムリーにアプリで提供。全体ではパニック購買を抑制する成功事例となりましたが、その効果は地域の教育水準によって異なり、大学卒業率の高い地域でより顕著でした」

澁谷氏は、前述の事例は、デジタルソリューションが本当に使って欲しい人に使われるのか、ソリューション展開への示唆を得る重要な事例となると語った。
澁谷「現在、都市空間のデザインを行っていくうえで、デジタルツイン技術の活用が注目されています。デジタルツインは、現実の都市空間を時空間的に反映したデジタルレプリカであり、都市の変化や介入による影響をシミュレーションすることが可能です。東京大学空間情報科学研究センター関本教授を中心としたチームでも、デジタルツインを構築できるような基盤技術を開発。全国の自治体がオンラインでダッシュボードを作成できる仕組みを昨年から提供しています。また、自治体ごとの課題に応じた追加アプリケーションの提供も行っており、私は人流変化のシミュレーションを行う、モジュール開発に注力しています。
たとえば、静岡県裾野市では富士山噴火時の溶岩流の流れや人々の避難行動をシミュレーションするためのダッシュボードを共同で作成。このような技術を活用することで、都市空間のデザインにおける課題を事前に検討し、より効果的な対策を講じることができます。
また、今後は都市空間における多様性を解析・評価し、それをデジタルツイン上で可視化する取り組みもすすめていきます。これにより、都市空間の利用状況や、人々の行動の多様性をデジタル上でタイムリーに把握し、適切な都市計画を立案することが可能となります。特に、都市の人口増加や多様化が進む中で、こうした技術はますます重要な役割を果たすことが期待されているのです。
都市のデザインにおいて多様性と包摂性をどのように高めるかは、今後の大きな課題です。異なる背景を持つ人々がどのように接触し、共存していくかを理解することは、より良い都市空間を創出するための鍵であり、人流データを基にしたシミュレーションは、その一助となる技術として注目されています。都市の人口の増加と多様化のなかで、コミュニティがそれぞれに孤立せず、よりイノベーティブな空間デザインにつながる。そんなシミュレーションを今後も継続したいと思います」




 アカデミア
アカデミア