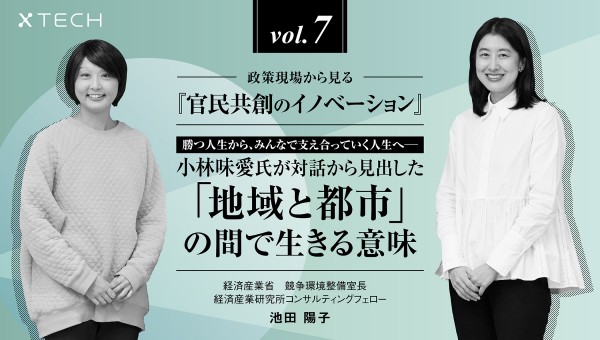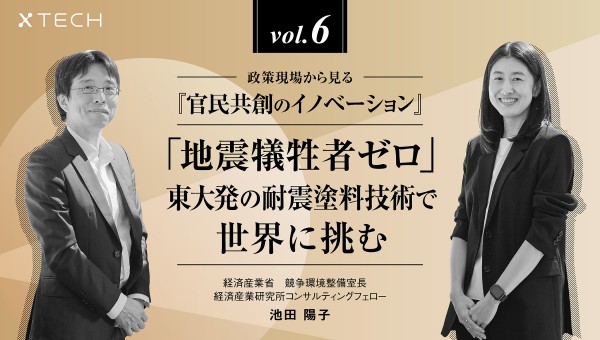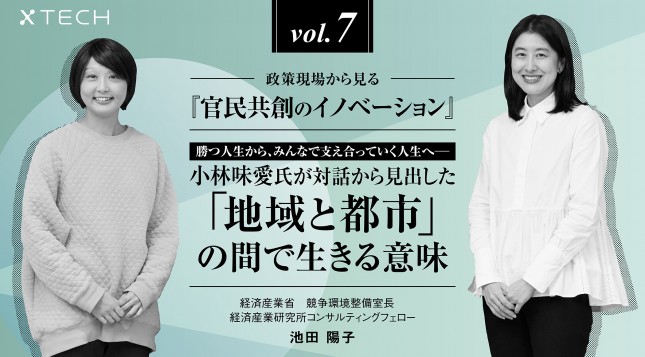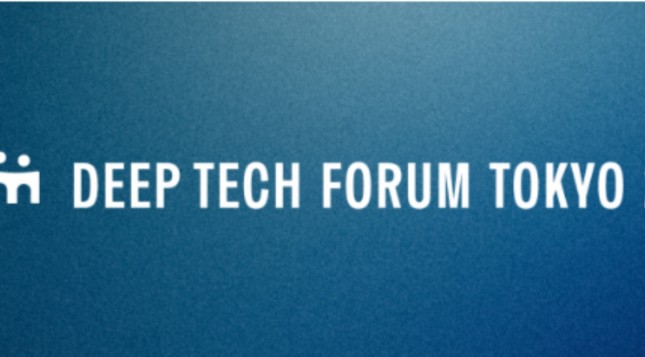越境はズレに気づく手段。ヒャダイン氏が語るメタ認知の価値|政策現場から見る『官民共創のイノベーション』vol.4
読了時間:約 9 分
This article can be read in 9 minutes
音楽クリエイターとして様々な楽曲提供を行うとともにタレントとしても活動し、高専生のディープラーニング起業コンテスト「DCON」の司会も務めるヒャダイン氏。「越境」に注目する本連載において、紛れもなく、特定の肩書きに縛られない越境人材といえるでしょう。しかし、その越境ぶりは多彩な才能の表れであることは言うまでもなく、ご自身にとって自分の“ズレ”に気づき、補正し続けるための選択だと語られます。
シリーズ『官民共創のイノベーション』vol.4。今回は特別編として、ヒャダイン氏に、AI×ものづくりの起業コンテスト「DCON」を起点に、アントレプレナーシップ、自身のクリエイティブのあり方、AI時代の教育論、ひいては、より良い人生を送るための秘訣まで、多岐にわたる話題をお聞きしました。インタビューアーは、政策・共創領域で数々のプロジェクトを推進してきた経済産業省の池田陽子です。固定化されがちな時代の「正しさ」を、彼の感性はどう突き崩していくのでしょうか。
ヒャダイン
音楽クリエイター
1980年大阪府生まれ。本名 前山田健一。3歳でピアノを始め、音楽キャリアをスタート。京都大学卒業後、本格的な作家活動を開始。ももいろクローバーZなど様々なアーティストをはじめNHK Eテレの「いないいないばぁっ!」での体操曲「ピカピカブ〜」や同じくNHK Eテレ「歴史にドキリ!」の音楽などの楽曲提供を行う。自身もタレントとして活動。レギュラーとしてテレビ朝日系列「musicるTV」、ABCテレビ「おはよう朝日です」、BS朝日「サウナを愛でたい」、「朝日中高生新聞」、「クロワッサン ヒャダインの台所」、「DIME」など。
池田陽子
経済産業省 競争環境整備室長/経済産業研究所コンサルティングフェロー
2007年に東京大学卒業後、経済産業省に入省。専門分野は、イノベーション政策、ルール形成、グローバルガバナンス。内閣官房では政府全体のスタートアップ政策を統括。近著に『官民共創のイノベーション 規制のサンドボックスの挑戦とその先』。これまで携わってきたスタートアップ政策、対GAFAのデジタルプラットフォーム規制、出版等の功績を評価され、2024年、Forbes JAPAN「Women in Tech」に選出。なお、本連載において、事実関係に関する記載以外の部分は、経済産業研究所コンサルティングフェローの立場による。
INDEX
・まず“誰かのために”という優しさがある。ヒャダイン氏がDCONで見た原点としての創造
・「できない自分」が教えてくれたこと─AI時代の教育論とは
・“味がする人生”を生きるために必要なメタ認知
まず“誰かのために”という優しさがある。ヒャダイン氏がDCONで見た原点としての創造
池田:まずはヒャダインさんが長年MCを務められている「DCON」について伺いたいです。今年で6回目、年々規模も拡大する中、全国各地の高専生たちと接するなかで、どのような印象を持たれていますか。
ヒャダイン:ここ1〜2年でガラッと雰囲気が変わったと感じます。やはりChatGPTの登場以降、AIがぐっと身近な存在になったことが影響していると思います。一方で、変わらないのはスタート地点に“優しさ”があることです。自分の暮らす地域に根差す課題の解決から始まっている印象があります。
池田:起業ありきというより、身近な生活実感から確かな気づきを得て、高専で培ったものづくりスキルと組み合わせ、社会とつながっていく感じですね。
ヒャダイン:まさにそうですね。そして、彼らを見ていて共感するのが「まず中に入ってやってみる」ことの重要性です。先入観や固定観念でやる前から「自分には無理だ」と決めつけるのではなく、とりあえず一度やってみて、そこから考える。彼らもまた、アントレプレナーに必要な“まずやってみる”という大事な資質を持っていると感じます。

池田:ヒャダインさんも先駆的にニコニコ動画・YouTubeなどのプラットフォームを活用されてきましたよね。
ヒャダイン:私がニコニコ動画に投稿し始めた2007年は、まだYouTubeも黎明期で。SNSや動画投稿サイトが広がるタイミングと重なって、個人がそうしたインフラで何かを発信するという選択肢が出てきました。運によるところも大きかったですが、あのときに新しいことに対して忌避感なく「面白そうだからやってみよう」と動いた経験が、今につながっています。
池田:「まずやってみる」ことが大事だというお話がありましたが、クリエイターとして作品を作る時に意識されていることはありますか。
ヒャダイン:大衆音楽をつくっているため、突拍子もない新しいことを思いつくというより、「ちょっとズレた場所」に立つことを意識しています。メインストリームが向かっている方向に、自分なりの角度で斜めの線を足してみるというか。既存の三角形に、補助線を一本引いて新しい領域をつくるようなイメージですね。
池田:なるほど。その“補助線”があることで、見えなかった構造や価値が立ち上がってくると。
ヒャダイン:そうなんです。「それ、考えたことなかったけど、たしかにそうかも」と驚いたり喜んでもらえる瞬間があると、やっぱりうれしいですね。誰かの見ていた景色に、ちょっと別の輪郭を加える行為というか。みんなが感じているけど言語化できていない違和感を放っておけないんですよ。違和感って、言葉にすることでようやく共有できるものになる。
そういう意味では、みんなが言語化できていないフワッとしたアメーバのようなものを瞬間冷凍して、「こういう形ですよ」と代わりに見せるのが社会的役割なんだと思います。音楽の歌詞でも、「そうそう、これが言いたかった」と思ってもらえる言葉を探していて、それが見つかるとすごく気持ちいいです。
池田:言葉にすることで、感覚にも輪郭が出てきますよね。
ヒャダイン:輪郭があると、人に伝えられますし、自分自身でも再認識できます。補助線を引くという行為も、ある意味では感覚を言葉で可視化することなんじゃないかと思っています。
池田:DCONの高専生たちも、もしかしたらそういったところを出発点にしているのかもしれませんね。
ヒャダイン:何かをつくるときって、結局はズレや違和感から始まると思うんです。そのズレこそが、新しい価値を生む補助線になっている。だからこそ、高専生たちのアイデアにもすごく可能性を感じるんですよね。
「できない自分」が教えてくれたこと─AI時代の教育論とは
池田:「補助線を引く感覚」と言うのは、いつ頃から意識されてきたのでしょうか。
ヒャダイン:明確に意識していたわけではありませんが、小学生の時から似たような感覚を持っていたのかもしれません。以前、体育科の教員向けの専門誌に「体育が大嫌い」というエッセイを寄稿したのですが、ある意味補助線を引いたからこそ見えた視点なのだと思います。
子どもの頃から体育が大の苦手で、授業中に恥をかく経験があまりにも多くて。「自分はここにいるだけでダメなんだ」と思いながら過ごしていました。

池田:たしかに体育の授業って、できる子が中心に設計されていることが多いですよね。
ヒャダイン:そうなんです。チームで対抗する競技が多くて、できないと空気が悪くなる。先生の前でも、クラスメイトの前でも、できない自分をさらされる。苦手な子ほど“目立たないようにやり過ごす”ことに必死になっていて、そこに教育的な意味なんて見出せなかったですね。
池田:そのときの実感を、あえて文章にされたんですね。
ヒャダイン:当時の恨みもあってか、かなり厭味ったらしく書きました(笑)。しかも、体育が得意でそれを仕事にしている読者が多数を占める専門誌だったので、「どうせ伝わらないだろう」と開き直って、まじめに受け止められることは前提にしていなかったんです。
ところが数年後に、バタフライエフェクトのように、SNSでそのエッセイが話題になって。「自分もこの違和感を抱えていた」「言語化してくれてありがとう」といった多くの声が届いて、学校の試験問題や教育現場で話題になるなど想像以上の反響があったんです。
池田:それはうれしいですね。
ヒャダイン:体育が苦手な子が「どうして苦手なのか」を言える機会って、そもそもないんですよ。でも、それが少しでも可視化されたことによって、周囲のまなざしも変わっていくのを感じました。僕自身「できなかった」という経験が、こんなふうに誰かの補助線になりうるんだと思えたのは大きかったですね。
池田:教育って、「何ができるか」だけじゃなくて、「何が苦手だったか」から見えてくることもありますよね。
ヒャダイン:そう思います。社会で活躍している人って、得意なことを活かしているのはもちろんですが、苦手な部分や失敗体験も含めて、それを認識して向き合っているように感じます。
池田:その視点は、現場の教育関係者にとってもすごく大切になりますね。
ヒャダイン:「なぜ苦手なのか」が置き去りにされてしまうと、評価軸も単一的になります。体育に限らず、あらゆる科目で「できること=正しいこと」とされる風潮は、もう少し見直してもいいんじゃないでしょうか。

池田:できるかどうかだけでなく、「なぜそれを学ぶのか」という問いも、もっとあっていいのかもしれませんね。
ヒャダイン:そうですね。たとえば、よく「数学なんて将来使わない」とか「歴史なんて覚えても意味ない」って言うじゃないですか。でも僕は、ああいう科目こそ“複眼的に考える”ためのトレーニングだと思うんです。世界史の知識がすぐ役立つわけじゃなくても、今起きている出来事に対して「これって昔のあれと似てるな」とか、そういう思考の下地になる。文系・理系の枠を超えて、複数の科目を学ぶことで世の中の事象を多角的に見ることができるようになりますよね。
池田:そういう切り口で複数の科目を学ぶことの重要性を語られる方は意外と少ないかもしれません。複眼的な視点こそが「教養」ともいえますね。
ヒャダイン:AI時代だからこそ、そのような「教養」の意味が増していると思います。AIに何かを聞いたときに、「それ、どういうこと?」って掘り下げたり、「他の考え方もあるよね?」って疑ったりする力がなければ、ただの受け身になりますから。
つまり、自ら提案したり、的確な感情表現を行うために、語彙力や知識は必要です。知識がなくても楽しめるかもしれませんが、知識があることで感情を言語化して固定化できます。平易な言葉でクリティカルに物事をとらえることも重要で、因数分解に近い感覚だと思います。結局は“他の視点を持っているかどうか”で決まるんですよね。
池田:それが、AIを使いこなせる人と、そうでない人の分かれ道になると。
ヒャダイン:だから僕は、できない自分だったからこそ気づけた視点とか、ズレを感じる側の違和感を、これからも大事にしたいと思っています。アントレプレナーシップもクリエイティブも、そして教育も、すべてはそこから始まる気がするんです。同時に、DCONの高専生たちの、AIとの“ニュータイプ”の共存の仕方を見てすばらしいと感じています。
“味がする人生”を生きるために必要なメタ認知
池田:ヒャダインさんは音楽クリエイターにとどまらず、幅広い分野でのタレント活動など、いわゆる“マルチキャリア”を実践されています。さまざまな領域に関わって、この連載のテーマでもある「越境」を体現されてきた背景には、どんなお考えがあるのでしょうか。
ヒャダイン:僕にとって、マルチに活動するのは「自分を補正するため」なんです。たとえば音楽の世界だけにいると、自分の価値観がその業界の基準にどんどん引っ張られてしまう。気づかないうちに一般的な感覚からズレていって、視野が狭くなる危険があるんですよね。角度が1度でもズレるとそれがどんどん広がって取り返しがつかなくなると思っています。
池田:そのズレを、自分で感知するのは難しいですよね。
ヒャダイン:だからこそ、異なる領域に身を置くことで、自分を定期的に客観視することを大切にしています。別の世界の中に入ることで、「今の自分、ちょっと古くなってないか?」って気づけるんです。
池田:それはまさに、メタ認知的な視点ですね。
ヒャダイン:40代にもなると、ある程度“型”ができてきますよね。組織のなかでも、自分の中でも。だからこそ、鏡に映る自分と他人から見えている自分がまったく違う可能性があることを受け入れる必要があると思っています。
同じ組織内で20年生き残ってきたということは、自分にとって心地よい場所、もっといえば特定のパラメータに最適化された結果ともいえるわけで。その型が今の社会にフィットしているかというと、必ずしもそうとも限らない。そこを点検しないまま続けていると、思考がどんどん凝り固まってしまう気がしていて。
たとえば「多様性」という言葉も古くなってきたように感じます。言っているのは大抵おじさんかおばさんばかり。若い子たちは、そんな言葉を使わなくても自然に多様性を受け入れられています。そのようなズレに気づいていくのが大事だと思うんです。
池田:そういった感覚を更新するには、どうすればよいと思われますか。

ヒャダイン:新しいことに挑戦するのが一番ですね。たとえば僕は最近麻雀を始めたんですが、当然ながら下手なんですよ。でも、その“できなさ”を堂々と引き受けてみたら、すごく楽しくて。
池田:それはすばらしいですね。
ヒャダイン:うまくできないことがあっても、恥ずかしいと思わない。うまくやれることばかり繰り返していたら、変われないですから。あえて、できないことに挑戦してみる。知らない世界に飛び込むことを、ゲーム内でプレイヤーを変えるように、ステイタスゼロからやり直す感覚で楽しめたらと。老いって、身体の問題というより「挑戦しない状態」から始まるんじゃないかと思うんです。
池田:その挑戦が、人生の“手応え”を作っていくということですね。
ヒャダイン:僕はそういう状態を、“味がする人生”って呼んでいます。できることを繰り返すと、だんだん味がしなくなるんですが、新しいことを始めてみると試行錯誤が生まれて味がする。
自分のズレや未熟さを抱えながら、それでも進んでいく感覚がある限り、人生ってちゃんと面白いなって思えるんです。
池田:越境しながら長年第一線で活躍され続けるヒャダインさんだからこその実感を伺えて感激です。

ヒャダイン:僕にとっての越境は、実は「新しい世界を見に行く」というより、「自分を見直すための装置」なんです。いまの自分の立ち位置が、時代や他者との関係のなかでどこにあるか。それを自覚して、また微調整する。その繰り返しが、僕のすべての活動のベースにある気がします。
池田:多岐にわたるテーマについてお伺いしましたが、ズレに気づき、補正し続ける姿勢が通底していて、そしてそれこそが、創造や共創の原動力になっていくのだと思いました。
ヒャダイン:ええ。まだ味が残っているうちは、もうちょっとやってみようかなって思えるんですよ。
池田:たいへん貴重なお話をありがとうございました。




 AI
AI