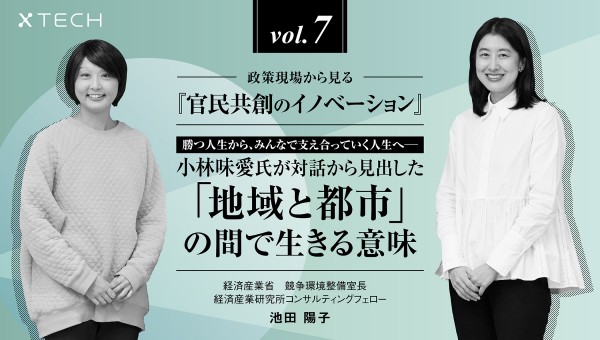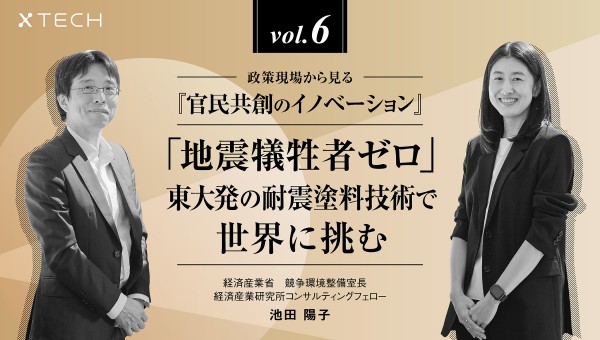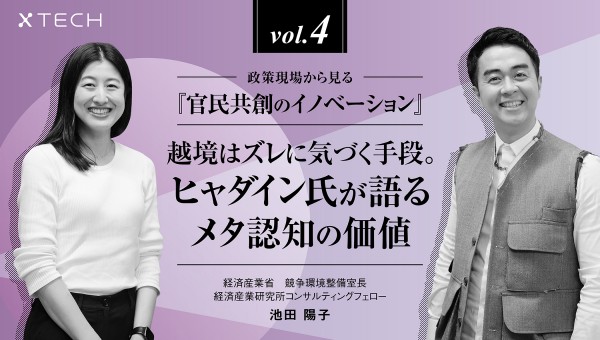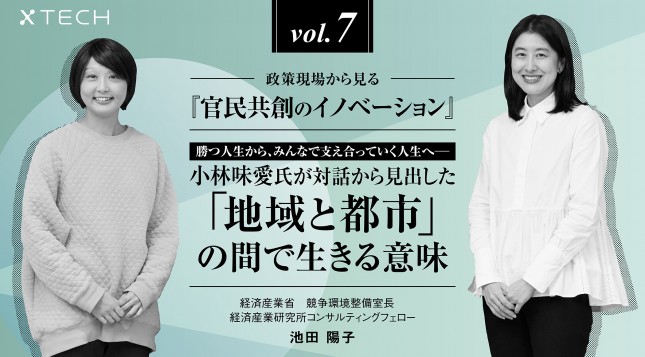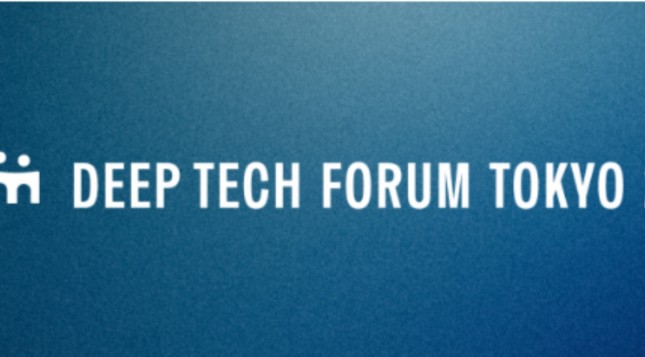「AI×ものづくり」高専生ビジネスコンテストDCONがつくる未来|政策現場から見る『官民共創のイノベーション』vol.5
読了時間:約 10 分
This article can be read in 10 minutes
AI技術の進展により、社会のあり方や産業構造が急速に変化する中、次世代を担う若者たちがどのように社会課題と向き合い、解決へと踏み出していくのか。その答えのひとつとして注目を集めているのが、今年で6回目を迎えた「全国高等専門学校(高専)ディープラーニングコンテスト(DCON)」です。
高専で培ったものづくり×AI技術を武器に、高専生が実際の社会課題を解決するプロダクトやサービスを考案し、チームをスタートアップ企業に見立ててその事業性を企業評価額で競う、というリアルでユニークな設計が特色です。
ものづくり×AIへの着目は、OpenAIのサム・アルトマンCEOが生成AIの次のステップとして語る「フィジカルAI」の先駆けともいえます。同時に、DCONは学生のビジネスコンテストの枠を大きく超え、教育、産業、行政を横断する共創のモデルとしても機能しています。これまで全国58校のうち50校が参加し、高専が地方創生の主役になることも期待されます。
本シリーズ「官民共創のイノベーション」では、さまざまな領域の第一線で越境的な共創を実現する実践者たちに話を聞いてきました。第5回となる今回は、DCONを生み育ててこられたDCON実行委員会事務局長の岡田隆太朗氏にインタビューを実施。AI時代を生きる高専生の潜在力を起点に、社会変革のプラットフォームとしてのDCONの意義と可能性に光を当てます。インタビュアーは、政策・共創領域で数々のプロジェクトを推進してきた経済産業省の池田陽子です。
岡田隆太朗
DCON実行委員会事務局長
1974年生東京都出身。慶應義塾大学在学中に起業。事業売却後事業会社を連続設立し、2012年 株式会社ABEJAを共同創業。2015年攻殻機動隊Realize Projectを発足し、コンテンツを活用したアカデミアと産業の連携する場を創設。同年より、IT経営者のコミュニティイベントInfinity Ventures Summitの運営事務局を設立し事務局長に就任。2017年、ディープラーニングの産業活用促進を目的に一般社団法人日本ディープラーニング協会を設立し事務局長に就任。2018年より同理事兼任。(現専務理事)
池田陽子
経済産業省 競争環境整備室長/経済産業研究所コンサルティングフェロー
2007年に東京大学卒業後、経済産業省に入省。専門分野は、イノベーション政策、ルール形成、グローバルガバナンス。内閣官房では政府全体のスタートアップ政策を統括。近著に『官民共創のイノベーション 規制のサンドボックスの挑戦とその先』。これまで携わってきたスタートアップ政策、対GAFAのデジタルプラットフォーム規制、出版等の功績を評価され、2024年、Forbes JAPAN「Women in Tech」に選出。なお、本連載において、事実関係に関する記載以外の部分は、経済産業研究所コンサルティングフェローの立場による。
INDEX
・DCONのはじまり――AI時代の高専生の潜在力とは
・コンテストが変えた教育――全国高専でAIプログラムが必修に
・評価はVCによる企業評価額――今年の優勝チームは「7億円」
・自在に越境を重ねるキャリア――好奇心がひらく未来のかたち
DCONのはじまり――AI時代の高専生の潜在力とは
池田:まずは「DCON」を始められた経緯をお聞かせください。
岡田:きっかけは、2015年、第3次AIブームの頃、『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』を書いた東大の松尾豊先生と出会い、一過性のブームで終わらせないよう日本ディープラーニング協会(JDLA)を設立し、ディープラーニングの社会実装や人材育成を考える中で、「高専生の力をもっと社会につなげられないか」と思ったことです。2019年にプレ大会を開催し、2020年から本格的にスタートしました。
池田:高専生に注目したのはなぜだったのでしょうか?
岡田:高専は、中学卒業後の15歳から入学できる5年制の高等教育機関で、全国各地の58校で6万人の学生が学んでいます。日本独自の仕組みで、60年以上にわたって、機械や電気といった日本のものづくりを支えてきた優れた教育制度です。
松尾先生とお話する中で、松尾研に編入してくる高専出身の学生が本当に優秀だと伺いました。すぐに手を動かして何かを作って持ってくる、この「試す」ことができるのがものすごく価値を生んでいると。まずやってみる、ダメだったらまたやるという試行錯誤が染みついているのです。
池田:なるほど。高専生が培ってきた確かなものづくりスキル、そして、その試行力や実践力に着目されたということですね。
岡田:はい。ソフトウェア領域では既にGAFAM海外勢にインフラを取られている状況ですが、日本が強みを活かし大きな成功につなげていくためにも、ハードウェアとディープラーニングの融合が欠かせません。高専生が自分たちのものづくり技術に、新しく成果の出ているAI、とくにディープラーニングの技術を掛け合わせ、それによってこれまで解決できなかった社会課題を解決するポテンシャルがあると考えました。
つまり、これからの日本の勝ち筋として、その担い手である高専生が自分たちの価値に気づき、また社会もその価値に気づくために、コンテストの形にしてみようということになったんです。
池田:ダイナミックな構想ですね。起業がゴールに設定されているのですか?
岡田:いえ、起業がゴールというわけではありません。あくまで「社会実装」がテーマです。DCONでは、実際の社会課題に向き合い、学校の先生や事業経験のあるメンターの支援を得ながら、それを自分たちのスキルでどう解決できるかを試行錯誤しながら考え抜きます。結果として起業につながるケースもあり応援していますが、本質は、ひとりでも多くの高専生が社会のさまざまな仕組みを知ることを含め、「実装を通じて社会と接続する」ことにあります。仮に就職したとしても、考え出したアイデアが社会に実装されていくことを十分残せますし、それも良いと思います。

池田:実装を通じて社会と接続する、ですか。
岡田:そうです。たとえば、日本が人口減少社会に直面する中で、特に高専が所在する地方部はそうした社会課題の先端にあるといえ、地域密着で課題感を把握できている学生もいます。そこから本当に日本を支える事業がたくさん生まれるはずだと思っています。
一方で、技術はあるけれどどう活かせばよいかわからないという学生も少なくありません。そうした場合によく起こるのは、ごく身の回りのテーマに着目して、「バイトしているコンビニで、数十種のタバコの銘柄から、お客さんが注文したタバコをAIで一発で見分けたい」みたいな課題設定になってしまうことです。便利かもしれませんが、その技術を使えばもっとすごいことができるのでは、と思ってしまいますよね。
池田:とはいえ、自力で目線を一気に上げるのもなかなかむずかしいかもしれません。
岡田:はい。逆に企業や行政には「こういう課題を解決してくれる人がいれば……」という実ニーズがあります。その橋渡しをするのがDCONです。そのため、夏休み期間にパートナー企業の方に来ていただいて、課題のお裾分けというか、「実際にこういうニーズがあるんだよ」と教えてもらう講義をやっています。そこから秋口にエントリーしてプロトタイプを作って、という流れです。
メンターがピボットさせることもありますが、やはり最初の課題設定は大事です。その結果、たとえばDCON2022本選に出場した豊田高専チームの熱中症リスクを可視化するというアイディアがベースとなり、株式会社ポーラメディカルにて暑熱対策AIカメラ「カオカラ」の実証が進んでいます。ほかにも、地方自治体と共同でインフラ点検の自動化に取り組むチームもあります。
池田:コンテストの形をとりながらも、通常の学生のビジコンの射程を大きく超えますね。
岡田:はい。DCONの理念として、その場かぎりの「アイデア勝負」や「プレゼン力」ではなく、「実際に社会で動くもの」をつくってもらうことを大事にしています。もちろん、最初から完成されたプロダクトは求めません。DCONはコンテストで、多くの企業がサポートしてくださり、色々な人の目に触れる機会があります。大事なのは、社会とつながりながら、課題設定から実装までを自分たちでやり抜くプロセス、そしてその中でしか得られない気づきだと思っています。
コンテストが変えた教育――全国高専でAIプログラムが必修に
池田:ものづくり×AIといったとき、特にディープラーニング技術の習得については、教育現場との連携も必要のように思いますが、何か変化はあったのでしょうか。
岡田:はい。従来は、一部の学科でしかAIに触れる機会がないという感じでしたが、大きな変化のひとつは、学科によらず、「AI教育が正式な必修カリキュラムとして全国の高専に導入された」ことです。2023年度から、全国58高専すべてにおいて、AI・数理・データサイエンスに関する教育プログラムが本格的に始まり、それはもう土台になっています。
これからは専門分野にAIをかけ合わせて成果を出したり、今まで解決できなかった課題を解決しようと言ってきたことがそのまま高専の教育に入ってきて、DCONでの成功体験や学生たちの成長が、ひとつの後押しになったと自負しています。
池田:それは驚くべきことですね。教育制度上、カリキュラムを変えるのは容易なことではないと思います。AI教育というと専門性の高い領域というイメージでしたが、それが高専のカリキュラムの一環として標準化されたというのもインパクトがありますね。
岡田:そうですね。特に注目すべきは、G検定レベルの知識を高専3年生までに身につけることを目標にしたカリキュラム設計が進んでいる点です。日本ディープラーニング協会のG検定のシラバスを参考にして作られているのですが、実際にDCONに参加した学生たちは、すでにそのレベルの知識と応用力を身につけています。これは相当難しいですが、やはり高専生は習得スピードが速いです。
また、2023年度から、アントレプレナーシップ教育も始まっています。技術だけでなく、会社や株式の仕組みを知って社会にどういう価値が生まれるのか理解することも大切です。
池田:学生サイドの受け止めはいかがですか。
岡田:やはり学生たちの目線がすごく広がりますね。私たちが出張して授業を提供させていただくこともありますが、「株式会社ってこういうことなんだ」という感じで。学生さんたちだけでなく、先生方もキラキラしています。
高専生の半分ぐらいは地方都市で5年間寮生活をして、進路といえば先輩が行った大企業に就職するか大学に進学するか、という世界観の中で、自分の力を活かして会社をやってみる、チャレンジをするという、従来では指導しようのなかったところが動き始めていると感じます。

池田:実際に、DCONを経て起業した学生も複数いらっしゃるんですよね。
岡田:これまでに12チームが実際に起業しています。
池田:社会変革の一翼を担うエコシステムとしても機能しているということですね。
岡田:はい。DCONをきっかけに起業を目指すプロジェクトに対して、1億円規模のファンド(DCON Start Up 応援1億円基金)を設けるととともに、創業バックオフィス支援や事業メンタリングなど一気通貫のサポートを行う体制も整備しています。
評価はVCによる企業評価額――今年の優勝チームは「7億円」
池田:一貫したコンセプトとしてリアリティの追求を大切にされているように思いますが、事業性の審査はどのような仕組みで行われるのでしょうか?
岡田:DCONの評価方法はユニークで、考案された事業の価値を、「点数」ではなく、「円(えん)」という単位で名だたるベンチャーキャピタリストの方々が企業評価額を算出します。介護記録の自動化に取り組んだ今年の優勝チームの評価額は「7億円」でした。つまり、その事業アイデアがいくらの価値を生み出す可能性があるのか、どれだけ社会とのつながりをもたらすのか、といった視点から評価するということです。
池田:私も観覧させていただきましたが、観客としても、手に汗にぎってコンテストを楽しめる大きな要因と思います。
岡田: 普通に高専生がものづくりをして作ったものに審査員が92点とかつけるのではなく、それが本当に社会課題を解決している事業で、一流のVCの方々に「円」という単位で評価されることがこだわっているポイントです。
それで何億円という価値がついたとしたら、社会は「この子たちはこんな価値があるものを考えたんだ、作ったんだ」と注目できるし、出場した高専生も「日々学校で学んでいる技術がこれほどの価値を生むのか」と気づけます。さらに、日本中の6万人の高専生が「僕たち、私たちもやればできるんだ」と思ってくれたらいいし、これから高専を選ぼうとしている中学生にも届いたらうれしいです。このように、リアルであればあるほどそれを体験できる人が増えます。
池田:評価方法の作り込みによって、あらゆるステークホルダーに気づきをもたらす設計が本当にすばらしいと思います。

自在に越境を重ねるキャリア――好奇心がひらく未来のかたち
池田:DCONのお話を伺っていると、技術や知識の習得だけではなく、「越境する力」や「社会とつながる感覚」を育てる場でもあると感じました。こうした壮大な仕組みを実現された岡田さんご自身のこれまでのキャリアについてぜひお伺いさせてください。
岡田:私の実家は医者の家系で、私自身ももともとは医学部進学を目指していました。しかし、医学部進学に失敗し経済学部に進学したので「社長になるしかない」と思い、いわゆるビットバレーの頃、在学中に起業して事業売却まで経験しました。1996年から始まったサッカーのワールドカップの日本招致プロジェクトに関わったこともあります。
その後、2012年にAIスタートアップである株式会社ABEJAに共同創業者として参画してAI業界に入っていき、日本ディープラーニング協会の設立へと至ります。コロナの時には災害支援の団体を作ったり、最近では、一般社団法人AIロボット協会(AIRoA)も立ち上げました。

池田:非常に幅広い領域を横断されていますね。何か明確なキャリアプランがあったのでしょうか?
岡田:正直、計画性はほとんどなかったです(笑)。常に「面白そう」「なんか気になる」「盛り上がりそうだ」と好奇心に従って動いてきた結果、気づけば分野をまたいで活動していた、という感覚です。社会にはそのときどきでなにか渦が起きているような場所があるので、自分にできることがあれば、そこに向かいます。
池田:素敵なポリシーですね。行政の現場でも、「分野を超えて考え実行できる人材」への期待は年々高まっていると感じます。私自身、専門性を持ちながらも固定されず、自分の力を異なる文脈で柔軟に活かせるよう精進したいです。
岡田:これまでいろんな立場を経験してきましたが、結果的に「思い出される存在でいたい」ということが軸になっているように思います。何か課題が出てきたときに、「そういえば岡田ってこういうことやってたな」と思い出してもらえる存在。だから、いつもうろうろしていて行動量は多いです。言い換えれば、「そこにいる力」でしょうか。
池田:変化のスピードが早く不確実性の高い時代において、メソッドどおりの「キャリア構築」ではなく、「好奇心」に導かれて自由に越境される中で、いつもふと思い出され、頼りにされる存在になるというのは、きっと最先端の人材像ですね。
岡田:その上で、面白そう、やれるかもしれないというときには一番汗をかきます。最初は本当にだれもいないし、辛そうだけどもなんだかんだ楽しそうにやっていると、「何やってるの?」とみんな集まってきて、場ができる。コミュニティ的なやり方かもしれませんが、それで課題や思いを持ち寄りやすくなりますね。
実際、日本ディープラーニング協会という社団法人を作ったことで、一営利企業ではなく業界団体として、政府の方ともお話しやすくなりました。そういう空間があるとエコシステムが回り始めるので、どんどんやるべきだと思います。
池田:岡田さんは、DCONをはじめ、エコシステム形成のプロフェッショナルであられ、自在に越境しながら、常に社会変革の渦のど真ん中で未来をつくられているのだと思いました。貴重なお話をありがとうございました。



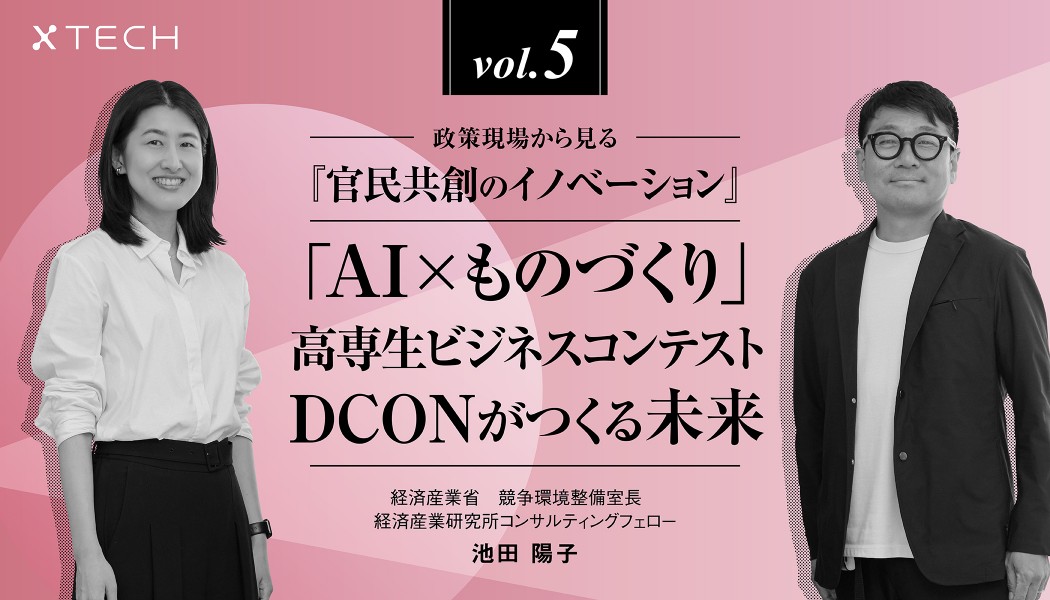
 政策現場から見る『官民共創のイノベーション』
政策現場から見る『官民共創のイノベーション』