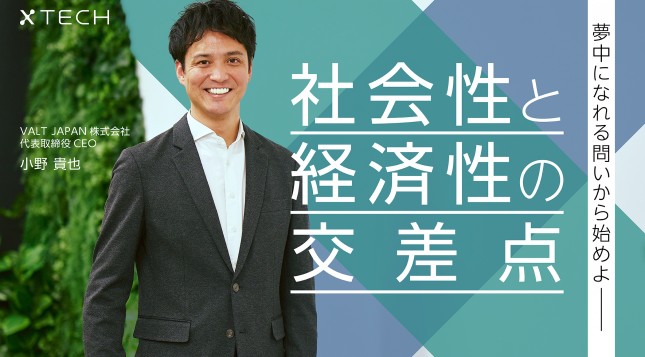2026年スタート、排出量取引制度で創造されるチャンス|環境経済学から見るクライメートアクション vol.8
読了時間:約 7 分
This article can be read in 7 minutes
2025年5月28日、「GX=グリーントランスフォーメーション推進法」の改正法が参議院本会議で可決・成立しました。これにより、2026年度から「排出量取引制度」が日本全体で本格稼働することが決まりました。
このコラム連載vol.1から繰り返しご紹介している通り、日本は2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにまで減らす目標を掲げています。それを実現するための新たな施策がこの制度となります。今回のコラムでは大企業のCxOや起業家・投資家の方向けに、来年から始まるこの排出量取引制度に備えるポイントを環境経済学の視点から共有します。
INDEX
・日本の排出量取引制度の概要
・排出枠価格の推移を注視
・2026年度から「CO2排出削減市場」が生まれる可能性
日本の排出量取引制度の概要
「排出量取引制度とは?」は以前の連載vol.3の記事をご覧ください。対象とした産業全体でのCO2排出量の規制値を政府が決定し、その排出枠を企業に割り振り、排出枠の企業間取引を認める制度です。すでにEUや中国で導入されています。このセクションでは2024年12月に公表された資料「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)」(こちら)に基づいて、この制度の方向性を共有します。
ポイント1)2023年度からの3カ年平均のCO2直接排出量が10万トン以上か?
上記資料によると、この制度の対象事業者は「CO2の直接排出量が前年度までの3カ年平均で10万トン以上の法人(単体)」となっています[1]。この「直接排出」は企業が石油や石炭の燃焼などで自ら排出する分を指し、他社から供給された電気や熱の利用で間接的に排出する分は含まないことを意味します。つまり、2023年度から2025年度の3カ年平均で自社だけで10万トン以上のCO2を排出していない場合は、制度対象とはなりません。この規模に近い事業者の多くはすでにまた別の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」でCO2排出量の報告を国にしていると思われますので、各事業者は自社が来年度からの新制度の対象となるかがおおむね予想できていることでしょう。いずれにせよ、まずは自社が排出量取引制度の対象となるかの確認が最初の備えになります。
[1]2026年度は制度の立ち上がり時期であるため、この年度の排出枠の割り当ては2027年度に2年分まとめて割り当てられる予定です。
ポイント2)制度の対象者以外でも2027年度からの市場取引に参加できる
では、排出枠を割り当てられない事業者にとってこれは関係のない制度でしょうか?実は、ここがビジネスチャンスとしても面白い点で、排出枠を割り当てられない事業者でも排出枠の取引自体は認められる方向性となっています(2025年6月現在)。
より詳しく説明します。まず、排出枠取引市場での枠の取引は、当然ながら制度対象事業者が参加可能です。結果的に枠に余裕ができた事業者は枠を売ることができ、枠を超えてしまった事業者ないしは、超えると見込まれる事業者は、追加の枠を市場で購入して償却義務を履行する必要があります。なお、償却義務の不履行となった場合、結局、枠の上限価格以上の単価での支払いが求められます。
この制度対象者以外にも、「一定の経験を有する」事業者の参加が認められる方向性となっています。例えば、制度対象者からの依頼を受けて、市場から排出枠を調達する、あるいは逆に枠の販売を担う新たなビジネスが生まれる見込みです。この市場参加者の候補となるのは、「排出枠に類するクレジット等」の取引の経験がある事業者となる見込みです。例えば、私個人のイメージとしては、金融機関、商社、コンサルティング企業やカーボンクレジット領域のスタートアップに市場への参入チャンスが生まれると考えています。なお、制度開始後しばらくは排出枠の現物取引のみが認められる計画ですが、将来的には先物などの派生商品も検討されています。
ポイント3)対象者に割り当てられる枠は何トンか?
再び対象事業者の話に戻ります。各事業者が最も気になるのは「自社が割り当てられる排出枠は何トンか?」でしょう。現状、これは分かりません。また、段取りとしても国が目安を示し、事業者が自ら排出枠の割り当ての申請を行うフローとなります。その前提で、割り当ての仕組みについて少しだけ解説します。
まず、業種によって大きく二つに分かれます。一つは「ベンチマーク」という考え方で割り当てられる見通しのCO2を多く排出する業種です。もう一つは「グランドファザリング」という考え方で割り当てられる見通しのその他の業種に分かれます。
この「ベンチマーク」方式のイメージは、同業種内で生産量1単位あたりのCO2排出量が少ない「上位X%」のトップランナーの基準がベンチマークとなり、それに生産量が掛け算されるイメージです。一方、「グランドファザリング」はベンチマークの設定が難しい事業者を対象として、ある年から毎年Y%ずつ排出削減となるように割り当てられるイメージです。
各事業者が排出枠の売り手になるか買い手になるか、今のところ誰にも分かりません。枠の割り当てがどの量に決定されるか、そしてその事業者が2026年度以降にどのくらいCO2の直接排出を減らせるかで決まります。
排出枠価格の推移を注視
以上は制度が確定すると更なる詳細が決まってくるポイントです。ぜひ今後の政府公式発表をご確認いただき、正確に把握していただきたいです。その上で、制度が確定したとしても不確実性が生じる点があります。それは排出枠の「価格」です。
ポイント4)2026年度の排出枠の価格はいくらになるか?
枠の買い手になる事業者はもちろん、売り手になる事業者もその価格が気になるでしょう。しかし、この価格が市場で決まる点も排出量取引制度の特徴です。価格形成に影響を与えると予想される点は少なくとも4点あります。
第一に、今後決定される排出枠の国全体での量です。これが少ないほど、排出枠に余裕を残せる事業者が少なくなり、排出枠が希少になるため価格が上がることが予想されます。各事業者にとっては自社の枠がどれだけ認められるかも気になるところですが、国全体でどのくらい排出量の「キャップ」がかぶせられるかが枠の価格に影響します。
第二に、景気動向、いわゆるマクロ経済です。2025年はアメリカの関税政策が動き出しました。こういった要因で2026年度に日本の製造業全体の生産量が少なくなってしまった場合、結果的にCO2排出量も減ることが予想され、その結果として排出枠を下回る企業が続出すると価格はゼロに近いままが続くでしょう。
第三に、カーボンクレジット市場や他国の排出量取引市場での枠の価格です。現状、日本の排出量取引制度では政府が運営するカーボンクレジット(J-クレジット・JCM)で排出枠の一部をまかなうことが認められる方向性です。その場合、J-クレジットの単価や、さらにはEUの排出量取引市場の価格などの動向に、日本の枠の価格もひっぱられる可能性があります。
第四に、政府による追加の価格安定化策です。排出枠の価格が高すぎたり、低すぎたり、さらには乱降下するようですと企業経営にとっては不確実性が大きくなり、投資の意思決定などに悪影響となります。そうならないように、先行する海外の制度にならって日本政府では「価格安定化措置」を準備しています。例えば、あまりに枠の価格が高騰した場合には、政府が指定した上限価格で枠を購入することで、超過した排出量分の枠をまかなえるようにする手などが検討されています。こういった価格安定化の措置がいつどのように発動されるかでも枠の価格は変わってきます。
なお、実際の取引市場の開設は2027年度となる予定です。ちなみに先行する諸外国の場合には、制度開始当初の排出枠価格はかなり低い水準で推移していました。2027年半ばからの最初の1年間に枠の値動きがどういった推移となるか、今から注目です。
2026年度から「CO2排出削減市場」が生まれる可能性
まだ制度の詳細が決定していない段階ですので、見通せないポイントが多いのも事実です。また、制度が確定しても価格の推移はその時々の経済全体に影響されるため、不確実性が残ります。しかし、この排出量取引制度が始まること、そして2023年度から2025年度までの排出量を下回る「国全体での排出量のキャップ」がかぶせられることは確定しました。つまり、2026年度からは日本国内でより一層、CO2排出削減のインセンティブが強まるといえます。
ポイント5)CO2排出削減ビジネスやスタートアップへの需要が高まる
これにより、今以上にCO2の排出を削減したいというニーズが生じ、新たなビジネスチャンスが広がります。これまでよりも再生可能エネルギー由来の電力の需要が高まるかもしれません。あるいは、省エネや節電に繋がる技術へのニーズも強まるでしょう。燃料の代替も起きるかもしれません。
すぐにでも実装できるクライメートテックや省エネ・節電ビジネスへの注目が2026年から着実に高まるでしょう。日本に排出量市場が立ち上がることで海外から日本市場に参入してくる企業も増えるかもしれません。新たな制度が市場をつくり、新たなビジネスを生むことが期待されます。この先もビジネスと政策が二重らせんのように、お互いに影響を与えつつ、日本の社会を変革していくことでしょう。
(このコラム連載「環境経済学から見るクライメートアクション」は今回で最終回です。これまでの応援を誠にありがとうございました。)
[1] 内閣官房GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ(第5回)事務局説明資料「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)」(令和6年12月19日)
[2] Fuss, S., Flachsland, C., Koch, N., Kornek, U., Knopf, B., & Edenhofer, O. (2018). A framework for assessing the performance of cap-and-trade systems: Insights from the European Union Emissions Trading System. Review of Environmental Economics and Policy.
[3] Hintermann, B., Peterson, S., & Rickels, W. (2016). Price and Market Behavior in Phase II of the EU ETS: A Review of the Literature. Review of Environmental Economics and Policy.
[横尾英史:一橋大学大学院経済学研究科 准教授]
専門は環境経済学。経済学の理論と手法を応用して、環境政策に関係する人々の選択や市場の動向を研究。
京都大学にて博士(経済学)を取得。環境経済・政策学会常務理事、経済産業研究所リサーチアソシエイト、国立環境研究所客員研究員等を兼務。2024年度はスウェーデン・ヨーテボリ大学経済学部に滞在。




 クライメートテック
クライメートテック