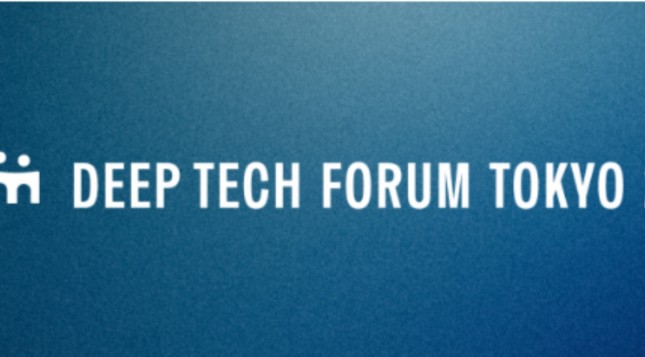AIと人を組み合わせ小売店舗で高級ホテルのような体験が可能に? AWLが映像自動解析技術で目指す未来
読了時間:約 10 分
This article can be read in 10 minutes
ひと昔前は遠い存在に思えた「AI」だが、今では生活の一部と言っても過言ではないだろう。スマホの音声認識をはじめ、カメラアプリの自動補正、翻訳ツールもAIが支える技術。現在ではビジネス領域にも参入が進み、製造や金融、通信、配送業など、幅広い分野でプロダクトが提供されている。
私たちが日常的に使う小売店も、自動化の波が押し寄せている領域だ。接客や商品管理はもちろん、防犯カメラを利用して購買分析を行う動きも出ている。
今回紹介するAWL(アウル)株式会社はAIカメラに特化した企業で、店舗に設置された防犯カメラの映像を自動解析して、店舗運営に活かすプロダクトを開発している。
同社の代表取締役、北出宗治氏は「将来的にはリアル空間をデータ化して、社会の最適化を進めたい」と話す。彼はなぜこのAIビジネスに踏み込んだのか。起業の背景や将来のビジョンを伺った。
INDEX
・優れた技術は人生を変えてくれる。AIにその可能性を感じた
・「何でも屋では競争に負ける」、その危機感がAWLを生んだ
・リテールからオフィスへ、アクセラレータープログラムを契機に新領域に踏み出す
・大企業との協業を成功させる秘訣は「熱意ある担当者」にある
・リアル空間のデータ化を通して、社会の利便性を高めていきたい
・ここがポイント

北出宗治
1978年北海道苫小牧市生まれ。⼤学在学中からインターネットビジネスを始め、卒業後に米コンサルティング会社(D.C.)、米レコード会社(NY)にてWEBマーケティング&コンサルティングを担当。帰国後、マンツーマン英会話のGABA社のIT部署の立ち上げに参画。その後、ライブドア社にてメディア事業部マネジャーとして多数の事業立ち上げを経験したのち、2006年に独立。大手企業を中心としたコンサルティング、事業、会社立ち上げのプロデュースを行う。北海道大学川村教授との出会いをきっかけに、AIの社会実装を推進すべく、2016年6月にAWL株式会社【旧AI TOKYO LAB(株)】を創業。
優れた技術は人生を変えてくれる。AIにその可能性を感じた

もともと北出氏の専門分野は事業プロデュース。現在のAWL(旧AI TOKYO LAB)を立ち上げるまでAIに触れたことはなかった。そんな彼がなぜ、この領域に参入したのだろうか?
北出:きっかけは、2015年のあるクライアントからの相談でした。そのクライアントから「事業の課題解決にAIを活用したい」と何度も相談を受けていたので、一緒に提案できる協力者を探していたんです。僕の会社の顧客に相談すると「それならいい人がいるよ」とAIの研究者を紹介してくれました。
この研究者が、AWLの技術顧問を務める北海道大学の川村秀憲教授だ。教授からAI技術の現状や技術的な可能性を教えられた北出氏は、「これは将来すごいことになる」と考えた。
北出:僕は優れた技術があれば人生は大きく変わると思っています。川村教授の話を聞いて「AIは間違いなく多くの人の生き方を変える要素技術になる」と確信しました。
実は僕自身、大学生の時にインターネットと出会って価値観や人生が大きく変わった人間なんです。祖父は卸売市場を経営していて、小さい頃から「大人になったら家業を継ぐ以外の選択肢は無い」と思い込んでいました。卸売市場はすごく大変な世界で、真冬でも毎朝4時に起きてセリの準備をしなければいけないし、肉体労働も多い。ですが僕は力はないし、朝も弱い。市場経営を自分が引き継いでいる姿を想像しては、よく絶望していました。
その絶望を変えてくれたのがインターネットとの出会いです。テクノロジーを使えば、時間も空間も超えて様々なことができる。同様にAIが普及すれば、レジ打ちや倉庫管理など、人手に頼っていた仕事をテクノロジーが代行できます。「余計なお世話だ」と言われてしまうかもしれないけれど、「私にはこれしかできない」と思っている人に「あなたには別の可能性があるかもしれない」と提案することができるんです。
AIの可能性を感じた北出氏は川村教授とタッグを組み、事業化に向けて動き出す。クライアントから相談された販促物の校正作業の自動化を皮切りに、2016年にAIを活用したサービスの受託開発する企業を立ち上げた。
北出:クライアントは毎年何冊もカタログをつくっていました。校正スタッフが高齢化して、若手にノウハウを継承することも難しかったので、これをAIで解決することに挑戦したんです。商取引をするなら受け皿として会社がなければいけません。急いでAWLの前身となる「AI TOKYO LAB」を立ち上げました。
この時は、「まだAIの成功例は少ない、実験的にやってみよう」と考えていた北出氏だが、世の中のニーズは同社を放っておいてはくれなかった。文字認識・音声認識・画像認識・数値シミュレーションなど様々なAI開発案件が舞い込んだ。
北出:当初の動きは会社というより、プロジェクトチームに近い形でしたね。僕自身、独立してからの10年で10社程度の立ち上げに関わったので「やってみないとわからない」と思っていたし、「分からないことは失敗しながらでも、ノウハウを蓄積して進めていけばいい」と考えていた。けれど想像以上に奥深い世界で、苦労はたくさんしました。
開発サイドに研究者が多かったので、意識のすり合わせも大変で。スケジュールの遅延やアカデミックな内容に踏み込んだ難解すぎる資料など、ビジネスサイドとの価値観の違いに戸惑いました。何度か衝突がありましたが、川村先生にサポートしてもらったりしながら、ビジネスと開発サイドの足並みを揃えることができました。
「何でも屋では競争に負ける」、その危機感がAWLを生んだ

同社は順調に事業を拡大していたが、創業から数年でAI業界には様々なプレイヤーが参入していた。北出氏は「このままでは先が無くなる」と危機感を抱き始める。
北出:事業を立ち上げた当初は、AI開発ができるだけで仕事が途切れることはありませんでした。しかし、業界にプレイヤーが増え、専門領域に特化した会社も増えてきていた。このまま「AIの何でも屋」をしていては、先細りになると思いました。
AI技術は日々急速に進歩しています。領域を絞らなければキャッチアップが難しく、開発力が落ちれば競争力が低下してしまう。「自分たちならではのソリューションを作りたい」とエンジニアからの声も上がっていました。
とはいえ、北出氏はどの分野に絞るか決めかねていたようだ。しかし、クライアントの相談がAIカメラの領域に進むきっかけをくれた。
北出:ドラッグストアチェーンの「サツドラ」を経営するサツドラホールディングスから、AIカメラを利用した店舗改善の相談がありました。課題を聞いて、ソリューションの検討を進めていくうちに、すごくポテンシャルがある領域だと気づいたんです。
リアル空間のデータ化をしているプレイヤーは当時まだ少なく、どこも実証実験のフェーズから抜け出せていませんでした。IoTと連動させたり、データをうまく活用したりすれば、効率的な店舗運営ができます。また、人が行き交うリアルな店舗で使ってもらうシステムなので、アプリやWebプロダクトといったデジタル空間と違い、利用者の姿がイメージしやすい。エンジニアもやりがいを感じると話していました。
「この分野ならいけるのでは」と考えた北出氏は、小売業界のクライアントにヒアリングを開始。まだプロダクトはなかったが、構想中のサービスと価格を伝えると「その価格なら絶対に導入する」と話す担当者が多かったという。
北出:ヒアリングのなかで業界の共通課題を掴めましたし、サービス導入のために支払える費用感も把握できた。このまま「何でも屋」を続けていても事業が停滞してしまいます。ならばリスクを取ってリアル空間のデータ化に特化しようと考え、AWL(AI+OWL:ふくろうが由来)というソリューションの開発に一点集中し、社名もAWLに変えました。
新事業に資源を集中するため、2019年に「AI TOKYO LAB」のブランドで展開していた受託事業を売却し、新ブランドAWLを立ち上げて、新たな一歩を踏み出した。
リテールからオフィスへ、アクセラレータープログラムを契機に新領域に踏み出す

社名変更後のAWLはリテール分野に的をしぼり、SaaS型のプロダクトを開発。ユーザーは店舗に防犯カメラやサイネージにAWLのデバイスをつなぐことで、購買分析や防犯・欠品のアラートなど、様々な機能を利用できるそうだ。
北出:ほぼ全ての小売店は何かがあった時のエビデンスとして防犯カメラを設置しています。AWLのプロダクトは、すでにある防犯カメラという資産を活用する形で開発を進めました。利用者は防犯カメラにAWLのシステムを繋ぐだけで購買分析や防犯アラートなどのAI機能が使えるようになります。すでにある資産を利用するため、導入費用を抑えられ、競合と比べて月額費用も10分の1程度の価格で運営することができます。
小売業界の予算は限られており、「新しく予算をつくってください」と提案しても断られてしまう。僕らは「実はコストダウンのご提案です」と話せますし、既存のカメラを使ってできることも増えるので、順調にユーザーを増やすことができました。
さらにAWLは、2020年1月に三菱地所のアクセラレータープログラムへ参加。現在は小売店舗向けだったソリューションを応用して、オフィス向けソリューションの開発を加速しているそうだ。
北出:映像解析技術はオフィスや工場、病院、学校など人が集まるところには全て応用できます。けれど、まずはどこかの領域にフィットしたものをつくらないとスケールしづらい。創業当初はリテールに的を絞っていましたが、「いずれは別の領域にも進出したい」と考えていました。
「次はオフィスが良いかも」と考えていた時に、多数のビルを管理する三菱地所がプログラムを実施していることを知りました。応募したら運良く採択してもらえたので、三菱地所が管理する、企業のDXやオープンイノベーションの促進を目的として丸の内の新東京ビルに開設した「Shin Tokyo 4TH」に本社を移転して、オフィス向けプロダクトの開発が始まりました。

AWLはプログラムのなかで、来場者の体温検知や顔認証、ラウンジや喫煙室の混雑状況を検知するシステムを開発。混雑状況はビルで働く人のスマホに通知され、三密の回避に役立てられている。
北出:コロナ禍とアクセラレータープログラムは事業内容を見直す転機になりました。
実はコロナ禍の影響で小売店舗向けシステムの既存商談の多くがストップしたんです。一方で、「並びたくない」「混雑を避けたい」「触りたくない」など新しいニーズが生まれたので、急いでコロナ対策機能を開発。これが新たなビジネスになり、売上の構成比は変化したものの、これまでと同水準の業績を維持することができました。
開発にあたって、プログラムに参加できたことは大きかったと思います。AWLはシステムをつくれますが、それを実装、検証する場を持っていません。三菱地所が実証実験ができるオフィス空間を提供してくれたので、スムーズな開発が可能になっています。
コロナ禍は同社に大きな影響を与えたが、素早く対応することで難を逃れることができた。今ではリモートワークの普及でDX化に関心が集まり、事業の追い風になっているという。
大企業との協業を成功させる秘訣は「熱意ある担当者」にある

プログラムを通して新規プロダクトを生み出した同社の事例はアクセラレータープログラムの成功例と言っていいだろう。しかし、企業文化の違いから大企業とスタートアップの協業はスムーズにいかないことも多い。AWLは円滑な協業のためにどのような工夫をしたのだろうか。
北出:AWLは過去3回ほどアクセラレータープログラムに採択されていますが、協業がうまくいくかどうかは確率論です。自分たちで調整できないこともあるので、ある程度参加してみるしかないと思っています。
もちろん、分かりやすい資料や動画をつくってミーティングの手間を省くなど、工夫は必要です。でも決定打はなくて、良いシナジーが起きる時は起きるし、起きない時は起きません。
ならば、なぜ今回の協業はうまくいったのか。北出氏は「物理的な距離の近さ」と「担当者の熱意」を挙げていた。
北出:結果論かもしれないけれど、三菱地所の物件へオフィスを引っ越したことはプラスに働きました。実装にあたり「ちょっと打ち合わせいいですか?」「今から実機を持っていきます」とすぐに提案できる環境だったので、熱を保って行動できました。
窓口になってくださる三菱地所の担当者の熱意もすごくて。担当者はアグレッシブにこちらの要望を社内で通してくれました。彼はスタートアップが好きで今の部署に移動しています。「僕が責任を持つから」と積極的に動いてくれたので、カメラやシステムの導入を円滑に進められました。
「協業にあたって担当者の存在は大きかった」と北出氏は話す。大企業がシステムを導入するためには社内調整が必要で、管理部やIT部、法務部の許可を得なければいけない。彼は率先して間に立ち、決裁者と引き合わせてくれた。個人の熱意が大きな企業を動かしたのだ。
リアル空間のデータ化を通して、社会の利便性を高めていきたい

最後に、同社のビジョンを聞いてみよう。北出氏はリアル空間のデータ化を通してどのような世界をつくっていきたいのだろうか。
北出:伝え方が難しいけれど、僕は「AIが人の創造性や可能性を拡張する世界」をつくりたいと思っています。
DX化は経営者にとって分かりやすいメリットです。「例えば、無人決済を導入して600人のレジスタッフの人員削減を実現できます」と話せば、経営者は「ぜひやりましょう」と喜んでくれる。一方で、「私はレジ業務のパートを20年間やってきて、これで生計を立てている。私の仕事を奪うのか」という人もいます。その人の気持ちも理解できるんです。
けれど、テクノロジーの進歩は止まりません。数百年前は馬や牛で移動していたのに、車や飛行機が生まれ、仕事が生まれては消えてきました。仕事が無くなるとその時は苦しいんです。けれど、新しい仕事は常に生まれている。もしかしたら、その仕事が自分の新しい価値に気付ける機会になるかもしれません。
どの業界でも人材不足が続いているので、企業は貴重な人材の働き方をアップデートしていかなければいけない。セーフティネットをつくる必要はありますが、AIの普及は必要不可欠な動きです。
AIが普及した未来では人はどのように協調して働いていくのだろうか。その理想例の一つとして北出氏は「Amazon Go」を挙げた。
北出:Amazon Goは無人店舗だと思われがちですが、実は人も配置されているんです。まずは入り口に入店補助をお手伝いするスタッフがいて、「今日はいい天気だね」と明るく声をかけてくれます。連日行くと顔も覚えてくれるし、ホスピタリティに溢れているので、まるで高級ホテルに来たような体験が得られるんです。
お酒売り場にも年齢確認のために人が配置されていますが、非常にフレンドリーです。「今日のメニューは?」「ならばこのワインが一押しです」とソムリエのようなサービスをしてくれる。そこに人がいる必然性があるし、また店に行こうと思えるんです。
僕らはリアル空間のデジタル化、省人化を通して、「人と技術のハイブリッド」を目指したい。店舗を無人化するのではなく、AIがお手伝いをすることで人間がプラスアルファの価値を出せる、そんな世界をつくりたいと思っています。
北出氏は、今後「リアル空間のデータ化を通して、社会の利便性を高めていきたい」と話す。
北出:AIカメラの社会実装は、賛否が分かれる領域です。「もしかしたら監視社会になるのでは」という意見もある。僕もそれは避けたいけれど、「プライバシーが保護されている状態」で個人情報が管理されるなら、社会の利便性はより上がっていくと思います。
迷子になる子どもはすぐに見つけられた方がいいし、犯罪者が出たらすぐに検挙できる方がいい。たとえば、行きたいお店の混雑状況を見て「混んでいるからデリバリーにしようか」と選ぶこともできるはず。
空間のデータ化は社会をより便利に、最適化してくれる技術です。慎重に進めるべき分野ですが、フロンティア精神を持って切り拓いていきたいと考えています。
AIは単なる道具だ。人間は道具を使うことで進歩してきた。自動車やスマホが私たちの生活を便利にしてくれたように、AIを使いこなせば豊かな社会を実現できるはず。近い将来やってくる変化を恐れず、適応していきたい。
ここがポイント
・「AIは、インターネットの様に多くの人の生き方を変える要素技術になる」という確信があった
・AIの経験はなかったが、「分からないことは失敗しながらでも、ノウハウを蓄積して進めていけばいい」と考えていた
・AIカメラに特化した理由は、「AIの何でも屋」では先細りになると考えたから
・映像解析技術は人が集まるところ全てで活用できるが、どこかの領域にフィットしたものをつくらないとスケールしづらい
・アクセラレータープログラムで協業がうまくいくかどうかは確率論
・「物理的な距離の近さ」と「担当者の熱意」は協業がうまくいく一因になる
・リアル空間のデジタル化、省人化を通して、「人と技術のハイブリッド」を目指したい
企画:阿座上陽平
取材・編集:BrightLogg,inc.
文:鈴木雅矩
撮影:小池大介




 AI
AI