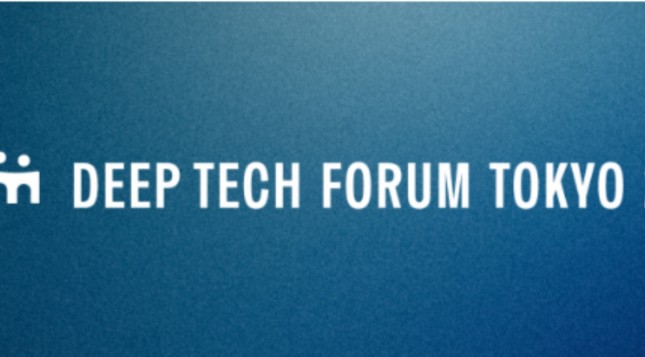新しいスマートホームスタンダードは1社では作れない。リンナイと三菱地所が「HOMETACT」で共にDXに取り組む理由
読了時間:約 8 分
This article can be read in 8 minutes
今や多くの企業が経営戦略の中心におくDX。しかし、その多くは「トランスフォーメーション」にまで至らず、デジタル化(デジタイゼーション)止まりのケースも少なくない。多くの大企業がDXの実現に向けて抱えている課題はなんなのだろうか。
その解を探るべく、直近数年で住設機器/IoTデバイスメーカー複数社を巻き込んだスマートホームサービス「HOMETACT」プロジェクトを推進し、パートナー企業のDXも進めている三菱地所の橘氏にインタビュー。
プロジェクト初期から「HOMETACT」に参画したリンナイの三浦氏を交えて、日本の大手メーカーが抱える課題と、三浦氏がどのようにその壁を乗り越えてきたのか深掘りした。

橘 嘉宏
2008年三菱地所株式会社入社。住宅業務企画部 新事業・DXユニット所属。分譲マンションの用地・一棟リノベーション事業の立ち上げなどを経験後、同社の住宅事業グループのバリューチェーン推進業務に従事。以後、住宅事業グループCRM立上げや会員組織「三菱地所のレジデンスクラブ」統合プロジェクトなどDX施策・新事業立上げを主に担当。総合スマートホームサービス「HOMETACT」を2021年11月にリリース。

三浦 浩一郎
1995年、リンナイ株式会社入社。大手ガス会社、大手ハウスメーカーなどを担当。2016年、デジタル領域での新規サービス検討部門の立ち上げ。2020年、関東支社 営業推進部 部長として事業部門におけるDXなどを担当。
INDEX
ガラパゴス化した日本の「スマートホーム」市場に新しい仕組みを作るために
DXの価値は、無形のリターンを計上する「BS思考」で考える
大手企業同士が手を組み、エコシステムを作ることに意味がある
ここがポイント
ガラパゴス化した日本の「スマートホーム」市場に新しい仕組みを作るために
――まずは三菱地所がスマートホーム領域に乗り出したきっかけを聞かせてください。
橘:きっかけは2018年頃に、弊社住宅事業グループの会員組織「三菱地所のレジデンスクラブ」やCRMデータを一つに統合するプロジェクトを進めていた時のことです。私たちはデジタル顧客接点を活用したマーケティングの強化を検討しているなかで、顧客のエンゲージメントを高めるために、まずスマートロックに目をつけたのですが、当時の日本市場ではまだ浸透しておらず、グループ会社の理解もなかなか得られない状況でした。そこで、2019年頃から私は海外のスマートホーム市場について調べ始めたのです。
そこで気づいたのは日本の住設機器やIoTデバイスの連携の拙さ。特にアメリカでは様々な通信規格で制御されるIoTデバイスが群雄割拠の状態で、かつ、スマートホームに関連したセキュリティサービスなど、IoTを活用した生活関連サービスもそれぞれが市場を形成しており、メーカーやプラットフォーム間での連携も進んでいました。一方で日本のスマートホームは同一メーカーの機器連携を前提にするなど、拡張性とユーザー目線での利便性に欠けていました。
さらに、2020年1月にCESに参加したことで日本市場と世界の差を目の当たりにして、危機感を感じると同時にビジネスチャンスだとも思えたのです。その頃から日本のIoTで新たな座組を作れるとしたら、それはメーカーではなく、デベロッパーである私たちの役割ではないかと思い動き始めました。

――そもそも日本のIoTがアメリカのようにメーカーを問わず連携されていない要因を教えてください。
橘:歴史を振り返ってみると、日本のスマートホームは阪神淡路大震災を契機に普及が進んだHEMS(Home Energy Management System)を中心に進化してきています。約20年以上にわたり各メーカーがしのぎを削って商品開発を進め、囲い込みを進めてきたことに1つの要因があると考えています。
そんな状況ではクラウドサービスのAPI整備など、アメリカでは当たり前に進められているメーカーやプラットフォーム横断での連携は進みません。メーカーからするとIoT家電のラインナップを揃えるのも一苦労ですし、それらを管理するためのソフトウェアも新たに開発し、維持していく必要があるからです。
――ガラパゴス化している日本市場で、橘さんはどのようにプロジェクトを立ち上げたのですか?
橘:2019年から度々アメリカに足を運び、どんなIoTデバイスがあり、それらがどのように家にインストールされており、サービスとして提供されているのか調べました。アメリカには複数のIoTプラットフォーマーがいるのですが、その中でも数多くのIoTデバイスのAPI連携基盤を提供しているYONOMI,Inc.と提携することにしたのです。
2020年、コロナが流行する直前に彼らのオフィスで「日本で実証実験しようよ」と話したのが、大きなターニングポイントでしたね。それからは日本の家電メーカーに何社もお声がけし、その一社がリンナイでした。当時はまだ実績もなかったので、断られることも多かったですね。
DXの価値は、無形のリターンを計上する「BS思考」で考える
――給湯器メーカーのリンナイが、なぜスマートホームのプロジェクトに参画したのでしょうか?
三浦:リンナイでは当時、一部のメンバーの中でそれまでのような「製造業」ではなく「サービス業」へ転換する必要があると強い危機感を抱いていました。今やレガシーな業界にも大きなデジタル化の波がきており、これまでのように「もの作って売るビジネス」だけでは未来がないのは明白でした。
そこで私が新規事業推進プロジェクトを立ち上げ、パートナーを探している時に出会ったのが橘さんです。私たちもIoTデバイスを連携する構想を考えていたので、橘さんから声をかけてもらったときにはすぐに参画を決めました。

――メーカーとしては先行きの見えない提案だったと思いますが、社内でどのように経営層を説得したのか教えてください。
三浦:社内の説得で一番むずかしいのはROI、つまり投資しただけのリターンを回収できるか説明することでした。
そこで私が提案したのはBS的な発想。スマートホーム事業単体の収益を考えるのではなく、そこで得られる無形資産がいかに既存事業に貢献するか数字で説明しました。「スマートホームのプロジェクトに参画することで、会社のブランド価値が上がり、給湯器がこれくらい売れるようになります」と。
実際に数字を出したことで、経営陣にも納得していただき情報システム、開発、その他社内各部門の協力を得ることができました。

橘:実際に今後、三菱地所グループ物件ではHOMETACTを導入する集合住宅で、リンナイさんの給湯器・床暖房を積極的に推奨していく予定です。そういう意味では実際にリンナイさんの既存事業にも貢献できると思っています。
大手企業同士が手を組み、エコシステムを作ることに意味がある
――約4年に渡ってオープンイノベーションを実践してきた橘さんからみて、日本企業の変化を感じていれば教えてください。
橘:ここ数年で日本企業のオープンイノベーションに対する姿勢は大きく変わったと思います。私がプロジェクトを始めた2018年当初は、オープンイノベーションのための組織や窓口がなく、協業の打診のために問い合わせをするとお客様センターなどピントがズレた窓口に繋がることもしばしば。打ち合わせに漕ぎ着けても技術研究所の所長さんが出てきて、先方の技術の話に終始して「機会があれば一緒にやりましょう」と言われて終わっていました。
今は会社によって名前は違えど、多くの企業が共創相手とのカウンターパートとなる組織を作っています。それも社長直下の組織にしていることも多いので、技術の話やプロジェクト単位ではなく、企業同士でどのように進めていくか話せるんです。世界に比べたら遅れはとりましたが、ここ数年で日本も大きく変わりましたね。
――その変化の背景には何があると思いますか?
橘:焦りがあるのだと思います。コロナ禍が追い風となって「DXをしなければ未来がない」と、これまでアナログだった企業がこぞってDXに乗り出しました。しかし、DXを自社だけで進めるのは容易ではありません。そこで、オープンイノベーションを駆使してデジタルを活用した企業変革を図っているのではないでしょうか。

――リンナイさんも現在進行系でDXを推進していると思いますが、どのような壁を感じますか?
三浦:自社に閉じて考えないことが重要なことであり、難しさでもあります。当社でも当初は1社完結で自社アプリを作成し、給湯器にインターネットで接続出来るようにしていました。『今日は寒いからお湯を張ろう』と屋外から操作してくれることを想定しましたが、アプリ自体がDLされずあまり使われませんでした。
そこで得られた示唆は、1社で1機能の側面から考えるだけでは、デジタル化に取り組んでもUXに結びつかず、効果は薄いということ。だからこそ自社だけに閉じるのではなく、エコシステムを作っていくことが大事なのです。そして、エコシステムを作っていくにはプラットフォーマーと参画企業の相互努力が必要になります。
こうしたことから現在開発中のアプリにおいては、アプリ単独のUXの改善とともに他社とのAPI連携を前提に開発を進めています。
メーカーである私たちがしてきたものづくりビジネスと、デジタル起点のサービスは何もかもが違います。私たちもITスタートアップと話をすることがあるのですが、時間軸がぜんぜん違うんですね。彼らは平気で「来週までにできますか」と聞いてきますが、私たちは一つの製品を作るのに最低でも1年はかかります。
設計、試作をして、金型をおこして大量生産するビジネスをしているので、万が一金型にミスがあった場合には数千万円の損失がでることもありえます。スタートアップのようにトライアンドエラーを繰り返すことができず、最初から慎重に設計しなければいけないのです。
私たちも新しい領域にチャレンジしようとは思っていますが、突然ビジネスの進め方を変えることはできません。まずはHOMETACTなどで実績を出しながら、少しずつビジネスの進め方を変えていきたいと思います。

――DXを実現するために必要なものを教えてください。
橘:最終的には担当者のパッションにかかっていると思います。DXはお金もかかりますし、それだけの投資をするには経営層を説得する必要もありますし、現場を巻き込むには膨大なエネルギーも不可欠です。また、当然ですが、個人でそれを突破することは難しく、それを支える組織力も必要不可欠です。
周囲のコンサルタントや同じように大企業のDX・新事業を担当している人から、「人事異動でプロジェクトが止まった」という話をよく聞きますし、そんな状況をよく目にもします。やはり、DXには時間がかかりますし、頻繁な人事異動は逆効果かもしれません。
私がHOMETACTを推進できたのも、今の部署に長く在籍していることが要因のひとつだと思います。加えて、上司とも何年も一緒に仕事をしている信頼関係があるからこそプロジェクトを続けてこられました。
最後に、スマートホームに挑戦したい企業は、ぜひHOMETACTを活用してください。ゼロから検討をスタートするより、遥かに時間とコストを有効に使えると思います。また、HOMETACTを通してお客様からフィードバックをもらいながらサービスを改善していけますし、販売提携による効率的なIoTデバイスの販路拡大や、スマートホームによる物件価値の向上を共に実現していきましょう。まずはリンナイさんにモデルケースになってもらいながら、多くの企業にHOMETACTを利用してDXを実現してもらえればと思います。
ここがポイント
・2019年頃のアメリカ調査で見えたのは日本のIoTデバイスの連携の稚拙さ。アメリカでは様々な通信規格で制御されるIoTデバイスが群雄割拠の状態で、メーカーやプラットフォーム間での連携も進んでいた
・日本のIoTで新たな座組を作れるとしたら、メーカーではなく、デベロッパーである自分たちの役割ではないかと思うようになった
・リンナイがプロジェクトに参画した理由は、「製造業」ではなく「サービス業」へ転換する必要があると強い危機感を抱いていたから
・社内はBS的な発想で説得。スマートホーム事業単体の収益を考えるのではなく、そこで得られる無形資産がいかに既存事業に貢献するか数字で説明した
・1社で1機能の側面から考えるだけでは、デジタル化に取り組んでもUXに結びつかず、エコシステムを作っていくことが大事
・DXには投資が必要で、経営層を説得する必要もあるし、現場を巻き込む膨大なエネルギーも不可欠
企画:阿座上陽平
取材・編集:BrightLogg,inc.
文:鈴木光平
撮影:小池大介




 DX
DX