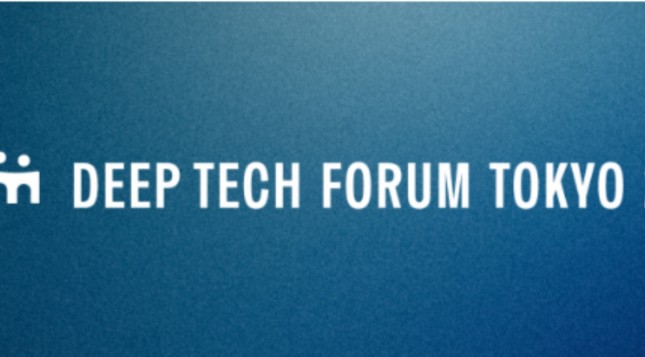食糧とエネルギーの自給率という2大国家問題にバイオで挑む。光合成細菌で窒素の固定化による肥料作りを行うDeeptech企業Symbiobe
読了時間:約 13 分
This article can be read in 13 minutes
バイオテクノロジーの力で環境問題に取り組み、持続可能な社会と産業を「あたりまえ」にするSymbiobe。窒素や温室効果ガスの固定により、社会や地球に貢献する。
同社の強みは、大気や水中のCO2・窒素などを固定する先端的なバイオテクノロジーにある。窒素の固定や有効利用はプレイヤーが少ないこともあり、同社はリーディングカンパニーのポジションにあるようだ。圧倒的な競争優位性を有していて、いわゆるブルーオーシャン戦略を取っている。しかしそれは同時に、パイオニアとして市場を開拓していかなければならないことも意味するため、突破すべき高い壁も多くあるはずだ。
同社はどのような戦略で市場開拓を目指すのか。顧客である農家や危機に瀕する社会・地球に対して、どのようなアプローチからの価値提供を模索しているのか。代表取締役の伊藤宏次氏にお話を伺う。

伊藤宏次
Symbiobe株式会社 代表取締役
ヤマハ発動機株式会社にて、主に「食と農業」「サステナビリティ」領域でスタートアップとの事業開発に従事。米国シリコンバレー駐在中には、出資先の農業系スタートアップとの新事業立ち上げを推進するなど、食と農業領域における海外事業も経験。2023年8月、事業開発部長として当社に参画。横浜国立大学卒業、IESE Business School経営学修士課程(MBA)を修了。
ポイント
・Symbiobeは「20世紀型ものづくり」に対して、次世代のものづくりを通して持続可能な社会の実現を目指している。
・CO2の除去や有効利用は求められているにもかかわらずプレイヤーが少ない。
・Symbiobeの技術の特長は「窒素の固定」にあり、光合成細菌であれば、高温・高圧など大きなエネルギーを必要とせず、肥料生成に結びつけられる可能性がある。
・光合成細菌自体は珍しくないが、「大量培養技術の構築」「遺伝子レベルでの操作」「菌の開発」により、ありふれたものを価値のあるものに作り変えることを可能にしている。
・戦略として、リスクを徹底的に下げたうえで、会社がビジネスとして成り立つところに持っていく道筋を付けることを重視している。
INDEX
・地球が直面する課題に、バイオテクノロジーの力で取り組む
・果敢な投資と技術力で、先行者優位を築く
・リスクを徹底的に下げることで、着実な社会実装を進める
・社会実装の鍵は、パートナー企業との協業
・「2030年」の先を見据えて
地球が直面する課題に、バイオテクノロジーの力で取り組む
——Symbiobeと、伊藤さんについて、自己紹介をお願いします。
伊藤:当社はもともと、前代表の後圭介と取締役CTO兼京都大学教授の沼田圭司が共同で立ち上げた会社です。沼田が研究プロジェクトの中で取り組んでいた技術を社会実装するためにスタートアップを立ち上げたという経緯があります。温室効果ガスであるCO2を大量に排出しつづけてきた「20世紀型ものづくり」に対して、次世代のものづくりを通して持続可能な社会の実現を目指しています。
私がSymbiobeと出会ったのは、前職のヤマハ発動機でスタートアップ支援に携わっていた時のことでした。新規事業開発で食と農業に関わる機会があり、プロジェクトマネージャーとして深く関わる中で、食と農業は環境問題と密接に関わっていることに気づきはじめます。
たとえば、カリフォルニアでは2022年から2023年にかけて大雨が降りました。普段は干ばつに苦しんでいる土地なのですが大雨にも弱く、路地栽培で作られているイチゴ畑に甚大な影響が及ぼされました。アメリカで生産されるイチゴの8割くらいはカリフォルニア産なので、イチゴのシーズンなのにスーパーには全然並ばないといった状況が起こっていたのです。同じ時期、ニュージーランドではハリケーンが起こり、畑だけでなくインフラも壊滅的被害に遭って、ブロッコリーなどの値段が高騰。一般の人々は夜ご飯に野菜を食べられない事態になっていました。
——環境問題に対して取り組む企業は数多くあります。Symbiobeにジョインした決め手はどこにあったのでしょうか?
伊藤:大きく分けて2点です。1つ目はビジネス面での競争優位性です。CO2の除去や有効利用は、これほどまでに求められているにもかかわらずプレイヤーが少ない。日本全国を見渡しても数社に過ぎず、しかも一部門で取り組んでいるケースがほとんどです。世界を見渡しても同様に希少性が高いというのが現状でしょう。
この理由としては参入障壁の高さが挙げられるでしょう。CO2除去に取り組むためには、相応の研究リソースが必要です。これは単独では難しく、アカデミアとの協業に取り組まなければ参入は難しい領域だと言えます。その点、Symbiobeは大学発のベンチャーなので優位性があるものと考えました。

——沼田先生の技術がコアコンピタンスとなっていると理解しています。その技術について詳しく教えて下さい。
伊藤:前述の通り、私は当初CO2を除去する脱炭素の文脈でジョインしたのですが、当社は今のところ光合成細菌(海洋性紅色光合成細菌)による資源生成の分野に重きを置いています。それを踏まえて技術の特長を一言で表すと、「窒素の固定」にあると説明できます。
農業肥料の3大成分のN(窒素)P(リン)K(カリウム)はほとんど全てを輸入に頼っている状況です。当社の技術であれば空気中の窒素を固定させられるので、食糧安全保障の観点からも大きな貢献になり得ます。
少しだけ、技術的なお話をしますね。窒素源として農業肥料に欠かせないアンモニアの生成は、高温高圧化の環境で化学的に行われてきました。では高温高圧をどうやって作るかというとエネルギーや石油の話に行き着きます。一方で、私たちの技術を使えば光合成細菌によって、高温・高圧など大きなエネルギーを必要とせず、窒素を固定させて肥料生成に結びつけられる可能性があります。同じように窒素を固定させる根粒菌は工業的な培養が難しいため、それに代わって窒素を人工的かつ工業的に固定させられる点で優れています。
——ありがとうございます。伊藤さんがSymbiobeにジョインしたもう1つの決め手についても伺えますか?
伊藤:先ほどと比較すると感覚的になるのですが、一時期グリーンウォッシュだと炎上していたように、この領域では付け焼き刃ではなく科学的な裏付けを持った技術が求められていることを感じます。しかし、私にはSymbiobeの技術的な価値はどこまでいってもわからないと思いました。創業者兼CTOの沼田を見て、研究者として確固たるキャリアを築いているとともに、ビジネス感覚も持ち合わせていた点に惹かれました。彼と実際に会って「この人なら信じられる」と感じたこともあり、一緒にビジネスをしたいと思えました。
果敢な投資と技術力で、先行者優位を築く
——窒素固定による肥料の開発に挑んでいますが、肥料といえば、先ほども話にでたアンモニアの利活用が盛んですよね。
伊藤:おっしゃる通り、窒素固定の実用化を試みる企業はほとんどない一方で、農業肥料に向けてアンモニアを生成する企業は多くあります。ただしアンモニアの場合、肥料として利用するまでには様々な工程を経ることになります。コストが膨らんでしまい、使途も狭まってしまうことが課題でした。
当社の場合、石油や天然ガスなどに由来する化学肥料とコスト競争することは、現段階ではなかなか難しいと言わざるをえません。ただし、今後持続可能性の観点から脱化学肥料が進む中で、有機農業へのシフトを促す有機肥料の選択肢を提案できるのではないかと考えていて、将来的なコストダウンを含めて開発を進めています。
また、使途の広さは強みになるのではないかと考えています。窒素を固定してタンパク質を作るので、畑に撒く肥料のほか、水産養殖用の飼料にも活用できます。この辺りはアンモニアでは難しい領域でしょう。
さらにタンパク質は生体内でアミノ酸に分解されますが、アミノ酸は植物の活性化に貢献するバイオスティミュラント[1]としても作用します。これによって、高温や干ばつでも枯れづらい植物づくりにつながるほか、低量の肥料でも育ちやすいなどの効果が期待されています。

——単に肥料として用いられるだけでなく、肥料投入量の抑制にもつながるバイオスティミュラントとしても作用するというのは大変興味深いです。
伊藤:今後、気候変動が更に進む可能性が高いです。植物の生育環境も目まぐるしく変わることから、こうしたバイオスティミュラントのニーズは高まるでしょう。当社の技術はその意味で、温暖化に対する根本的な解決にも資するほか、いわゆる対症療法としての貢献も考えられます。
そのほかにも、水産などへの活用も考えられます。今私たちの食卓に並ぶ養殖した魚は、主にチリやペルーで獲れたイワシを加工して作った魚粉を食べて育てられています。世界人口の伸びと中産階級の増加に伴って、水産養殖を支える魚粉需要は今後ますます増えていく可能性がありますが、海洋資源にも限りがあります。そこで、我々は光合成細菌に豊富に含まれているタンパク質・アミノ酸に着目し、魚粉代替飼料原料の開発を行っているところです。また、たとえば私たちが食べているサーモンは、赤色などの色素が入った飼料を与えている場合が多いです。当社が扱う光合成細菌には、そうした色素がもともと入っている上に機能性も高い。こうした分野にも貢献したいと考えて取り組みを進めています。
——本当に様々な応用先があるのですね。ただ、不勉強で申し訳ありませんが、こうした光合成細菌自体は珍しいものではなく、自然界にもありふれているものなのではないかと考えています。
伊藤:おっしゃる通り自然界を見渡せばどこにでもいる生物ではあります。しかし、効果的に扱うのは意外と難しいのです。そこに対して、当社は真正面から取り組んでいます。
具体的な取り組みは、大きく分けて3つです。1つ目が大量培養技術の構築です。紅色細菌を大量培養しているケースは世界的にも稀ですが、当社の場合は京都大学の桂キャンパスにあるデモプラントを利用しています。プロトタイプ段階のデモプラントとはいえ、一番大きく展開しているのではないかと自負しています。当然ながら相応のノウハウの蓄積がありまして、そちらも強みとして挙げられると思います。
2つ目としては、遺伝子レベルでの操作です。これまで微細藻類と比べて光合成細菌がフォーカスされてこなかった理由として、遺伝子の変異をかけるのが困難だったことがあります。沼田は、光合成細菌の遺伝子加工に向けたツールを整えて、数年前には改変もさせられるようにしました。当社でも扱うバイオポリマーも、こうした研究の成果です。
3つ目が、菌の開発。光合成細菌や、その中でも紅色細菌といっても、いろいろな種類があります。利活用に際しては選抜をかけてライブラリ化することが有効なのですが、そうした取り組みを他社に先駆けて行っており先行者優位が働きます。
要するに、沼田の技術を用いると、光合成細菌と空気や海水といったありふれたものを使って価値のあるものに作り変えていくことを可能にするのが当社の独自性だと理解してください。これによって、自然界に常在する身近な細菌を、社会に役立つものとして利活用することを狙っています。
[1]バイオスティミュラント・・・植物や土壌により良い生理状態をもたらす様々な物質や微生物
リスクを徹底的に下げることで、着実な社会実装を進める
——ビジネスとしては、どの程度の生産量に達しているのでしょうか?
伊藤:現在はまだ商用化の段階にありませんが、今まさに商用化手前まで漕ぎ着けるための実証を準備しているところです。光合成細菌の培養方法は特殊なもので、生産量の増大はまさに当社の課題です。こちらについては当社が単独で解決できるものではなく、島津製作所など地元京都の企業にもご協力もいただきながら事業を進めています。
——生産量増大に向けたアプローチには具体的にはどういったものがあるのでしょうか。
伊藤:ポイントは、大きく分けて3つです。1つ目が、菌自体の能力を上げていくこと。2つ目が培養に適した環境を作り出すこと、3つ目が培養液の検討を進めることです。
注力しているのは1つ目と2つ目です。ラボベースで行われている実験をふまえて、菌の改良と培養環境の最適化を進めています。特に当社の場合にはプラントにおけるノウハウが確実に蓄積されてきているので、ラボの実験結果の再現性は高まりつつあります。パートナー企業と一緒にサイクルを回し、生産性のさらなる向上に向けて進めています。

ラボでの培養の様子
——マーケティングの観点からの戦略も教えてください。
伊藤:まずは、飼料ではなく農業肥料から取り組もうと考えています。これについては「高付加価値領域を攻めずに、逆を行くのか」と言われることもあるのですが、当社ではあくまでも肥料から取り組むべきだという認識です。
——逆張り戦略ということですか?
伊藤:いえ、そういうわけではありません。高付加価値なプロダクトから始めたというのは、あくまでも結果論だというのが私の考え方です。全ての研究開発が高付加価値になるものを狙って行われているわけではありません。世の中を見渡してみると、低付加価値と言われている分野からのイノベーションも数多くあります。
私たちが強みとする技術力を社会実装するために、最も重要だと考えているのはローリスク戦略です。リスクを徹底的に下げたうえで、会社がビジネスとして成り立つところに持っていく道筋を付けることを常に考えています。
——高い技術力を持つ貴社にとって、リスクを排除しながら社会実装を行うというのは実直な戦略だと感じました。
伊藤:そこで、リスクの洗い出しを具体的に行いました。考えられるリスクの1つ目は、マーケットリスクです。せっかく製品化しても使われなければ意味がありません。ただしこれに関しては、現実的には大きな問題ではないと考えています。なぜなら、肥料も飼料も、常に使われるものだからです。そのほか、レギュレーションリスクも懸念材料ではありますが、当社が扱う材料は天然のものをベースとしていますので、その点も大きな障壁にはならないと考えています。
真正面から取り組むべきなのは、テクノロジーリスクです。これはディープテックスタートアップではどこもそうかもしれませんが、実現するための技術開発の難易度が高いことが特徴です。なので、比較的技術開発が早く進むものから順次事業化を進め、最終的にプロダクト間やマーケット間でシナジーが働くようなプロダクトロードマップを検討しました。
そこで最初にやりたいと考えているのは地産地消で循環していくモデルの立ち上げです。私たちのプラントは海外から輸入するような原料を必要とせず、地域で排出される温室効果ガスを利用して光合成細菌を培養します。地域から排出されるはずだった温室効果ガスを肥料化し、化学肥料を使わない有機農業向けの肥料として使ってもらうことで、その土地に炭素や窒素を戻していきたいと考えています。例えば、京都であれば「京野菜」が有名ですが、ゼロカーボン農産品といった有機野菜に続く新しいカテゴリを地域から提案できたら面白いですよね。

——ローリスク戦略でプロダクトを順次投入する考え方は大変勉強になります。その先にどういった未来を見据えているかについても、教えて下さい。
伊藤:主に、社会に対する価値提供と、農家に対する価値提供を考えています。
いま、「みどりの食料システム戦略」にあるように、日本としては化学肥料の使用量を下げつつ輸入に頼らない食料生産が課題となっています。当然ながら、窒素源をどのように確保するのかは課題の1つとなるでしょう。そこに対して、私たちの原料も輸入しない純国産の肥料は効いてくるものだと考えています。
消費者側の姿勢もゆくゆくは変容するかもしれません。アメリカでは、調達ポリシーを掲げてインパクトレポートを出している小売店舗も多くあります。有機野菜を優先的に扱ったり、CO2排出量が少ない農作物を調達したりする事例も散見されます。こうした流れが日本社会でも起こる可能性はありますよね。
また、若い新規就農者を中心として、有機農業を選びたいという方が一定程度いらっしゃいます。しかし、有機農業の障壁となるのが肥料選びの難しさです。たとえば堆肥は牛糞などから作られますが、動物の副産物であるために成分があまり安定していない。地域によって堆肥の中身は異なりますから、窒素含有量も当然ながら異なり、それによって農作物生産が不安定になりかねません。私たちの工業的な技術を使って、同じ成分の有機肥料を安定して作り出すことができたら、有機農業を選びたい農家さまの役に立てるのではないでしょうか。
さらに、有機肥料の多くは効きが遅いのですが、そうした課題にも取り組んでいけるのではないかと思っています。有機肥料の場合、元肥として使う場合が多いです。逆に、「窒素が少し足りない」といった場合に追肥する際には化学肥料を用いることが多いのです。特に新規就農したばかりであれば、NPK(窒素・リン酸・カリウム)の最適なバランスを予め想定しておくのは簡単なことではありません。そうした悩みを抱えた新規就農者にも貢献したいと考えています。
社会実装の鍵は、パートナー企業との協業
——ここまで農業肥料や家畜飼料の話が中心でした。貴社の技術の応用範囲は広いという話ですが、今後はどのような分野に進出するお考えですか。
伊藤:これまでの話に共通しているのは、大気中にある炭素や窒素を固定するものですよね。これに対して、他にも炭素や窒素はあります。ここに取り組む考えもあります。
具体的な話として挙がっているのは、陸上養殖の分野です。実は、魚を飼育する陸上養殖槽でも炭素や水素はあります。あるいは下水処理施設でも同様の構造があり、そちらで発生するメタンガスの4割はCO2だったりします。私たちがイメージする窒素・炭素といえば大気中が主ですが、気づいていないところで、取り込める炭素や窒素はまだあるはずです。これまで放置されていたものについて、地球に悪影響を与える前に利活用方法を見出すことで有効に使っていけるのではないかと思います。
また、光合成細菌の活用の仕方にも工夫を凝らすことでいろいろなイノベーションを起こせるかもしれません。光合成というと藻類をイメージされる方が多いのですが、当社の光合成細菌は嫌気環境である閉鎖系バイオ槽の中で培養されています。そのため、培養槽を構造物にすることでスケールさせられる可能性もあります。
将来的な応用先としては、たとえばビルの1区画の壁を培養槽してしまえば、光合成細菌を活用して窒素・炭素の固定ができるかもしれない。培養槽を構造物するには費用が嵩んでしまうことから通常であれば難しいものの、ハイバリュー化とうまく噛み合えば可能性はあるかもしれません。
カーボンクレジットの文脈も、ゆくゆくは大きく変えられるかもしれません。カーボンクレジットといえば植林を思い浮かべる方も多いですが、日本の場合にはこれ以上木を植えるのは現実的には難しい。それに対して、実は光合成細菌はCO2の濃縮が不要であることから大気中のCO2を回収するDACのように低度濃度CO2も利用できますから、森林のような機能を持つ人工物も作れるかもしれないわけです。
もちろん、こうした試みはまだ始まったばかりなので、一朝一夕にたどり着くゴールではありません。上述したようにビジネスの観点からは低リスク分野から攻めていくことになるので、着実に歩みを進めていくことになります。また、排ガスや排水といっても、その中にはいろいろなバリエーションがあります。様々な物質と結びついて排出されているので、それぞれに対する取り組み方にも違いがあるでしょう。
——製鉄会社の高炉から排出される排ガスと、火力発電所から排出される排ガスには違いがあるということでしょうか?
伊藤:イメージとしてはそうしたことです。だからこそ、多くの企業さまとの密な連携が鍵の1つだと考えています。まだまだ乗り越えるべき課題は多くあり、現実的には「御社のCO2排出量を即座にこれだけ削減できます」と言える段階ではないことも事実です。ただ、それでも我々と一緒に環境問題に取り組みたいと言ってくださる企業さまとはコミュニケーションをぜひ取らせていただきたいです。
「2030年」の先を見据えて
——応用先としては、社会の側もあると思います。
伊藤:そうですね、まずは当社の飼料・肥料が社会に受け入れられている土壌づくりを進めていきたいと考えています。少し先の長い話となりますが、ゼロカーボンで作った農作物を消費者の方々にお届けしたい。そのためには飲食店さまやEC業者さまとの協業で何らかの企画を立てられないかと画策しています。
それについては日本国内では食べ物の背景があまり注目されていないこともあり、アメリカやヨーロッパから始めることになるのかもしれません。日本の場合、たとえば卵1つとっても平飼いの卵を目にすることはほとんどありませんが、欧州ではケージフリーは一般的な育て方です。生産方法にも着目する小売店さまとのつながりを考えるときには、アメリカから始めるのが戦略的には妥当なのかもしれません。ゆくゆくは日本でもそうした潮流は起こるはずで、口にするものは自分で選ぶ流れになることを見据えて、いろいろな企業さまとの協業を進めていきたいところです。

——ありがとうございます。最後に、今後のロードマップについて教えてください。
伊藤:カーボンニュートラルに向けた施策は2030年以降ますます重要になってきますから、それまでに我々の事業が準備できている状態を作り上げたいと考えています。
いま、多くの企業さまは2030年に向けて様々な取り組みを進めていらっしゃいます。そこに向けたCO2削減などのサステナビリティに対するロードマップは引けているのではないでしょうか。
私たちは、その先を見据えています。2030年から2050年くらいにかけて求められるはずの技術を作っているのが私たちです。2030年以降の未来について、具体的なイメージを描いている企業さまは必ずしも多くないはずです。未来を皆さまと一緒に描いていきたいというのが、私たちの想いです。
企画:阿座上陽平
取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:宮崎ゆう
撮影:小池大介




 DeepTech
DeepTech