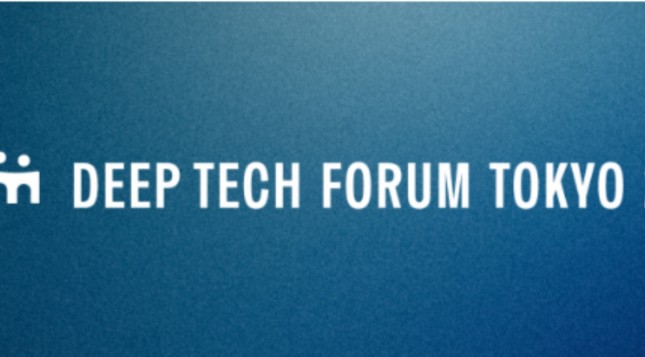文理融合が拓く未来。東大Weekが示すアカデミアとビジネスの新たな共創【東大Week@Marunouchi DAY1】
読了時間:約 10 分
This article can be read in 10 minutes
急速に変化する社会の中で、アカデミアとビジネスの関係性も大きな転換期を迎えている。従来の枠組みを超えた協働や、文理の垣根を越えた新たな学問の形が模索される中、MEC-UTokyo Labが主催する「東大Week@Marunouchi」が2023年に引き続き、開催された。

「アカデミアとビジネスは”文理融合”で共創できるのか」をテーマに行われたトークセッションには、東京大学生産技術研究所の松永行子教授と東京大学史料編纂所の本郷和人教授が登壇。NewsPicks Brand Design編集長の呉琢磨氏がモデレーターを務め、文理融合と産学連携の可能性について熱い議論が交わされた。
工学とデザインの融合に取り組む松永教授、日本史研究の第一人者である本郷教授。一見異なる分野で活躍する二人の研究者が、それぞれの視点から「学問の本質」や「社会との接点」について語る。本セッションでは、デザイン思考を取り入れた最先端の研究アプローチから、歴史に学ぶ日本の「二刀流」の伝統まで、幅広いトピックが議論された。
アカデミアとビジネスの新たな関係性とは? 研究者に求められるパーパスとは? 本記事では、二人の教授の洞察に満ちた対話を通じて、これからの時代における学問と社会の在り方を探る。
イベント登壇者
本郷和人
東京大学史料編纂所教授。1960年東京生まれ。日本中世史を専攻し、1988年に史料編纂所入所。2012年より現職。大日本史料の編纂に従事する傍ら、歴史学の衰退に危機感を抱き、「歴史を好きになってもらう」ことを目指して活動。著書出版やテレビ出演など、一般向けの歴史普及活動にも積極的に取り組む。
松永行子
東京大学生産技術研究所教授。バイオエンジニアリングを専門とし、医学と工学を融合した組織工学研究を行う。細胞から臓器を設計・組み立てる研究や、科学とデザイン・アート分野の融合に取り組む。平成30年度文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。国際色豊かな研究室を主宰し、デザイナーとのコラボレーションを通じて科学の社会実装を目指す新たな試みを展開している。
呉琢磨
NewsPicks Brand Design 編集長。フリー編集者を経て2015年にNewsPicksの広告事業部立ち上げに参画。2018年より現職。若者向けタブロイド「HOPE by NewsPicks」創刊や地域経済特化プロジェクト「NewsPicks Re:gion」開始など、新たなメディアビジネスの開発に取り組む。都市と地域の経済圏をつなぐ活動を展開し、メディアを通じた社会変革を目指している。
ここがポイント
・分野を越境した視点が、新たな研究やビジネスチャンスを生む
・デザイン思考により、研究成果を社会に分かりやすく伝達できる
・複数の専門性を持つ「二刀流」の姿勢が競争力を高める
・知の深化と探索のバランスが、イノベーションを促進する
・社会貢献を目標にすることで長期的な成功につながる
・金銭以外の価値観が産学連携を深化させる鍵となる
・継続的な対話と目標共有が効果的な協業を実現する
INDEX
・デザイン思考から生まれた、『血管の音色』
・日本における偉大な”二刀流”とは?
・文系の知識がもたらす新たな視点
・長期的な成功の鍵は、パーパスにある
・「お金を目的にしない」ことが、研究者のプライド
デザイン思考から生まれた、『血管の音色 Attune』
呉:今、大学発のベンチャーが増えていますね。2023年だけでも500社ほど立ち上がっていて、全体で見ると4000社を超えるとも言われています。そんな中、今日1つ目のテーマになる「ビジネスとアカデミアを”統合”する横断思考とは?」についてディスカッションしていきたいと思います。松永先生はまさにビジネスとアカデミアの統合を体現していると思うのですが、普段どんな活動をされているのですか?
松永:私が所属する生産技術研究所は大学附置研究所の中で国内最大級の規模で、100以上の研究室があります。その中で、「工学・科学技術をもって世の中の課題をどう解決すればいいのか」をテーマに日々各々研究に勤しんでいます。
社会が抱える問題が迅速に変化する現代において、また、世界の人々に真の豊かさを提供するためには、優れた技術だけでなく、そこへデザイン視点を取り込み、新たな価値を創造することが重要です。そこで2017年に当時の所長らが中心となり、どの研究室の人も出入りできて、デザインエンジニアの方が研究の価値を発掘して社会に実装できるデザインラボ(DLX Design Lab)を立ち上げました。ラボには世界中から集まってきたデザインエンジニアの方と社内の課題をどう解決するかディスカッションするアイデアジェネレーションや、アイデアからプロトタイプをつくることができるスペースがあり、素早くアイデアを形にして検証できます。このデザインラボができたことで、研究室同士のつながりも増え、また社会との接点も増えたことを強く実感しています。
そんな中のひとつとして生まれたのが『血管の音色』というプロジェクトです。私は私達のからだの生理機能に重要な毛細血管に関する医工学の研究をしているのですが、2018年にデザインラボから「イスラエルで一緒に何かやりましょう」と声がかかり、エルサレムでデザイナーの学生さんとアイデアジェネレーションをする機会がありました。
そこではまず簡単に自分の研究について説明し、そのあとデザイナーからたくさんの質問をいただきました。多数のアイデアから最終的に絞ったものをプロトタイプ化し、翌年のオープンキャンパスで約300人もの方々に体験してもらったのです。

こちらが実際のプロトタイプです。毛細血管を顕微鏡で観察しても「血液が流れてるな」くらいにしか思えないのですが、このアプリは個人で異なる血管のかたちなどの様子を音楽に変えてくれるんですよね。QRコードで簡単に自分の血管の音が聞こえるUXにもこだわった設計にしたので、私たちの研究や自分の体について多くの人に関心を持っていただけた手応えを感じました。
日本における偉大な”二刀流”とは?
呉:最近はオープンイノベーションに象徴されるようなアカデミアとビジネスのコラボレーションで新規事業を開発する動きも活発化しています。また、日本を代表する経営者の中にも、もともとバイオの研究をしていたところから、乳酸菌に可能性を感じてヤクルトをつくるなど、分野を越境して成功した人がいますよね。もともと得意とする専門領域に、さらに別の強みを組み合わせている方が活躍されるケースが多い印象です。そんな“二刀流”で成功した日本の歴史上の偉人で思い当たる人はいますか?
本郷:後藤新平でしょうね。彼は東京の大震災があった時に街づくりをしたり、台湾の統治や満州鉄道の初代総裁などを務めたりしました。後藤新平はもともと医師で、板垣退助が暴漢に襲われて怪我をした時に診察したことでも知られています。そこから政治家に転身して、さまざまなことを成し遂げました。
もう1人有名なところで言えば、森鴎外ですね。彼は軍医であり文学者でもありました。昔は博士号の取得が今よりずっと大変だったんですよ。そんな中で文学と医学、2つの博士号を持っている偉大な人ですね。
あと東大の大先輩になる山川健次郎先生。この方は工学部の先生なのですが、なんと白虎隊の出身なんですよ。元侍でもちゃんと勉強して成績を残しているんです。日本の侍はすごいと思いますよね。昔風にいうと「国家のために尽くしたい」気持ちがあれば、文系でも理系でもいいし、アメリカにもヨーロッパにも行くという感じなんでしょうね。
妙にインテリが縮こまってしまったのは、むしろ戦後なのかもしれません。そこに人類のためにとか、世界市民としてとか、新しい概念が生まれているわけですから。松永先生のように世界を舞台に大きな仕事をしている方は素晴らしいと思います。

文系の知識がもたらす新たな視点
呉:文系の教養がサイエンスや工学を考える上で役に立つことはあるのでしょうか?
本郷:もちろんあると思います。経営学者で友人でもある入山章栄さんが翻訳した『両利きの経営』には、既存事業を深める「知の深化」と、新規事業を展開する「知の探索」を両輪とした経営の重要性が書かれています。
やはり知はイノベーションを起こすと思うんです。もともと日本は「知の深化」は得意ですが、「知の探索」は苦手です。日本は失われた30年と言われていますが、その要因の一つはイノベーションを起こせなかったからだと思います。
なぜ日本は「知の探索」が苦手か歴史的に考えていくと、日本は島国だからです。かつて世界でペストが流行したとき、日本にペストは上陸しませんでした。日本に攻めてきたモンゴル人の王朝「元」が滅亡した理由とも言われているペストが、日本では猛威を振るっていなかった。これは日本が島国である証拠です。
そんな日本にかつてイノベーションを起こした人物が織田信長です。今では当たり前の感覚ですが、日本は一つの言語を使う、一つの民族がつくった、一つの国家ですよね。しかし、「それは違うのでは?」と思っています。
今や当たり前の概念である関東と関西ですが、もともと日本では北陸道、中山道、東海道の3つの関の東側が関東と言われていました。かつて日本は近畿に都がある西北型の国家で、東北は田舎なんですよ。関東という言葉は昔からあったのですが、関西という言葉はなかったんです。
当時の日本人に自分たちを相対化する視座はなくて、おそらく明治時代になってから関西という言葉が生まれたのではないかと。そう考えると関東に対応する言葉は関西ではなく、九州を意味する「鎮西(チンゼイ)」だと思うんですよね。
つまり、関東や東北は日本とは別の国だったのかもしれません。それを一つの国にしようとしたのが織田信長なんです。信長のイノベーターとしての資質は、「日本は一つであるべき」と考えたことなんです。イギリスはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドが一つになってユナイテッドキングダムですよね。もともと日本もイギリスに近いのではないかと思うんです。それを踏まえた上で信長や家康を考えると、信長が「知の探索」というフレームをつくり、家康が「知を深化」させて日本を一つにした。この功績は大きいと思います。
こうした両利きの経営的な「知の深化」と「知の探索」の二刀流が昔からあったからこそ、今の日本があるのだと思います。ビジネスで「知の探索」につなげるためにも、文系の学問を勉強することは決して無駄になりません。一つのモデルさえできれば、日本人は「知の深化」が得意ですし、それこそサイエンスの独壇場です。
長期的な成功の鍵は、パーパスにある
呉:デザインラボとの協業により『血管の音色』を生み出したのも「知を探索」した結果だと思うのですが、松永先生は何が原動力になっているのでしょうか?
松永:普段一緒に仕事をしているデザイナーさんに目標やモチベーションを聞いたところ、「人々をワクワクさせたい。そのためにいろんな人と協業して、革新的なことに挑戦したい」とおっしゃっていました。私も理系の研究者としてエンジニアリングの探索もするんですけど、まさに「人々を幸せにしたい」気持ちは同じで、誰かを幸せにしたい想いが原動力になっているんだと思います。

本郷:やはりみんなが笑顔になってくれることが一番嬉しいですよね。私も「この子たちがどういうふうに成長していくんだろう」と思いながら授業をするのがすごく楽しいです。子どもたちからは「先生、テレビに出てますけど、共演者で誰が一番綺麗でしたか?」時にはそんな質問も飛んできますけど(笑)。
呉:そうですね。一方で、関わる人が増えるとリスクもあるじゃないですか。特にビジネスだと商売として成立させる必要があるので、科学的に真っ直ぐな研究でいられないとか。あるいは探索として新しいことに挑戦したのに、本来の研究にフィードバックされないこともあると思うんです。アカデミアの方がビジネスに近づく上でのリスクヘッジについては、どうお考えですか?

本郷:やはりみんなでディスカッションして腹落ちさせることが大切だと思います。「そうか、私たちはここを目指しているんだ」とみんなが納得するパーパスがあれば、一時的に赤字になっても続けていくことができるのではないでしょうか。
例えば、明治時代に日本は近代化に向けて「富国強兵」というパーパスを掲げていました。実際、当時の日本は強かったですよね。今は「人間らしくありたい」というパーパスに変わっていきましたが、「人間とは何か」という問いは、文系の諸学問がこれまでずっと探索してきたこと。今を生きる人たちがパーパスを考える上でも、文系の教養にも向けることが重要になると思います。
呉:松永先生はチームを組むときに周囲をドライブさせる目標やパーパスをどう設定しているのでしょうか?
松永:アカデミアだと「論文書きましょう」とか明確なゴールがあるのですが、企業の方と協業するときは「どれくらいの価値を、いつまでに出すのか」は話し合いますね。実は半年ほど前にスタンフォードに行って医療機器やヘルスケアなどバイオデザイン系スタートアップの方々とお話しする機会がありました。普通なら「この10年でいくら利益を出す」といったお金を指標にすると思うのですが、その方々は違いました。売上よりも「何名の患者さんを救ったか」を指標にしていたのです。社会への貢献度を周囲に誇らしげに語っていて、かっこよかったです。
「お金を目的にしない」ことが、研究者のプライド
呉:かつてご自身で起業した大学の教授を取材した際に、80年代、90年代に産学連携ブームの時に「非常に少ない予算で産学連携をやり、知財は企業に持っていかれてこりたので、自分で起業することにした」という話を聞いたことがありました。
今は企業側も「アカデミアの知を利用してやろう」というより、松永先生がおっしゃたように「一緒に課題解決するために頑張りませんか」というアプローチが増えていると思っています。オープンイノベーションという言葉がそれを象徴していると思うのですが、実際そういう場を作るためには東大側もステークホルダーと話し合う場づくりをしているのでしょうか?
松永:そうですね。最近は「東大とどういうふうに協業して、社会に対する価値を創造できるでしょうか?」とラウンドテーブルの場を設定し、何回もディスカッションしながら目標を設定しています。実際に成果も出ているので、引き続き話し合う場を増やしたいですね。
呉:ビジネス側と協業する際に、アカデミア側は企業に何を期待しているのでしょうか?
本郷:アカデミア側が何かを期待するということはないかもしれません。私たちは研究そのものに喜びを感じていますし、ビジネスの最前線で戦っている方の知的な取り組みに触れるだけで嬉しいのです。
正直、「お金はいらない」といえば嘘になりますが、「お金を目的にしない」ことは研究者にとってのプライドなんです。そもそも考えることを楽しいと思っていない人は研究者にはなりません。特に文系の研究者は貧乏になることもある程度は覚悟の上でこの世界に飛び込んでいますから。
それに東大生に授業をすると本当におもしろいんですよ。鋭い質問を飛ばしてくる生徒もいて、双方向の手応えがある。ビジネスをやっている方と話している時も、同じような手応えを感じます。
私は自分の小さなアイデアを汲み取ってくれるだけで、生きがいを感じるんです。それはお金では買えません。戦っている人間同士の一体感が、私たちの現場にはあります。一方通行で知識を提供するだけでなく、「あなたの言っていることはそうだけど、こういう見方もあるんじゃない」という意見などがインタラクティブに出てくると、面白さを感じるんですよね。

編集:BRIGHTLOGG,INC.
文:VALUE WORKS




 アカデミア
アカデミア