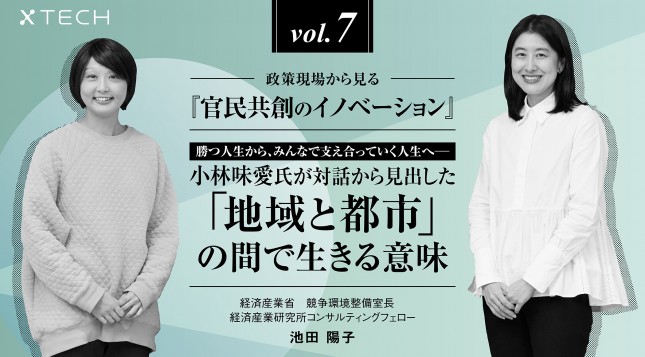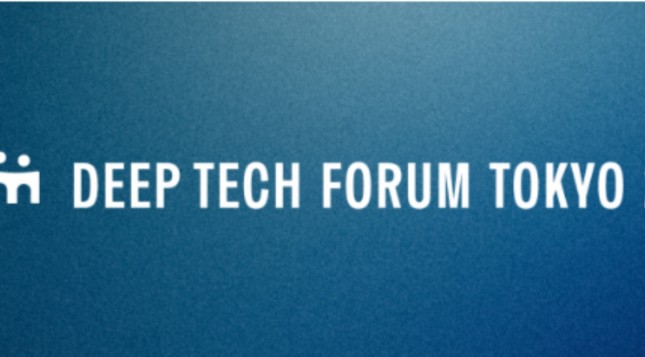2025年1月、日本のクライメートテックの現在地|環境経済学から見るクライメートアクション vol.6
読了時間:約 7 分
This article can be read in 7 minutes
アメリカでのトランプ大統領就任で幕を開けた2025年。振り返れば、2010年から2020年のトレンドとしては欧州が引き続きネットゼロの流れを主導し、中国が太陽光発電やEVへの大規模な投資でコストダウンを実現していました。そして、2021年のバイデン前大統領の就任後、アメリカで勢いよくクライメートテックへの政策と投資が進み、これが世界中で大きな潮流を起こしました。
そしてこの度、トランプ大統領によって、アメリカで進んでいたネットゼロを目指す政策の多くがストップする事態となりました。クライメートテック投資の大きなトレンドが生まれた過去4年間、もっと言えばさらに5年遡った2015年のパリ協定採択後から、気候変動対策に取り組む新たなアクターが急増しました。連載vol.2「世界で始まったカンパニー・クリエーション競争」で紹介した通り、ビル・ゲイツを始めとするIT領域の成功者とベンチャーキャピタル(VC)が続々とクライメートアクションを始めてくれました。
しかし、これらアメリカのVCによるクライメートテック投資は2022年を境に減少傾向です。そして、ここに来てのトランプ大統領就任。アメリカの投資家の「クライメートテックというラベルは2024年で終わりにしよう」という意見も目にします。確かに、過去4年の追い風とは異なり、政権交代後のアメリカでは逆風の時期となるでしょう。
このような時期に、日本のこの領域はどうなるでしょうか?あるいは、クライメートテックへの逆風が強まる世界において、日本のポジションはどうなっていくでしょうか?2025年以降の日本のクライメートテック・エコシステムを占うために、今回のコラムでは過去4年間のそれを振り返ってみたいと思います。
INDEX
・2021年~2024年の日本のクライメートテックシーン
・過去4年で「クライメート」が「事業領域」となった
・過去4年で「政策」が立案された
・2025年は日本のクライメートテックにとって「相対的に順風の年」
2021年~2024年の日本のクライメートテックシーン
・2021年に始まった日本のクライメートテックシーン
・新規参入するVCが増加
・クライメートテック関係のイベントやメディアが勃興
2021年、日本にもクライメートテックのムーブメントが訪れました。私の知る限り、いち早くそのシグナルを発信したのはVCのANRIでした。2021年4月のこちらのnote記事を皮切りに「気候変動」についての対談記事などを掲載されたのです。当時、私は驚きました。髙橋健太郎さんという、私と同じく環境経済・政策学会の会員の方とベンチャーキャピタリストが意見交換をしていたのです(そのブログはこちら)。
環境問題の研究者とベンチャーキャピタリストの議論など、それまでの日本では聞いたことがありませんでした。もちろん、日本でも環境エネルギー投資を筆頭に、環境・エネルギー領域へのVC投資はありました。ただ、脱炭素に関係はあったとしても、エネルギーやEV関連が中心であって、気候変動対策を全面に打ち出した形では無かったと考えています。しかし、2021年を機に「気候変動」や「クライメートテック」に言及するVCが国内で急増したのです。
東京大学FoundXディレクターの馬田隆明さんも同じ頃にアクションを起こしてくれました。まず、2022年初めには、気候変動に関するオンライン勉強会などを開始されています。アントレプレナーシップ教育の専門家でテックの社会実装の著作で知られる馬田さんが、気候変動に関する書籍の輪読会などを始めてくださり、驚いたと共に嬉しくなったのを覚えています。その後、馬田さんたちは2023年6月に東京大学で「Climate Tech Day」というイベントを企画・開催され、およそ500人の参加者で週末の本郷キャンパスが賑わいました。

Climate Tech Day 2023の看板
メディアの方の動きも迅速でした。それまでも宣伝会議の「環境ビジネスオンライン」などが活発に情報発信をしてくれていましたが、新興のメディアが多数登場しました。例えば、2022年4月にはメディアコンサルタントの市川裕康さんがClimate Curationという週刊ニュースレターを開始されました(創刊号はこちら)。また、Climate Tech Japanというコミュニティが立ち上がり、こちらも2022年秋から週刊ニュースレターで資金調達情報などを発信してくれています。その後、2023年にはNewspicksによる「Green Impact」というPodcast配信も始まりました。
関連書籍も多数登場しました。同じくNewspicks・森川潤さんが2021年に欧米のクライメートテックを紹介した「グリーン・ジャイアント 脱炭素ビジネスが世界経済を動かす」を出版。その他にも、「クライメートテック」や「脱炭素産業」と名のつく書籍が次々と出版されました。
2020年以前も気候変動と「産業」は切っても切り離せない関係として論じられてきました。しかしそれは、温室効果ガスの排出源としての「産業界」という意味合いでした。ところが、2021年頃からは、気候変動問題を解決するための「産業の創成」という別の意味合いで語られる様になったのです。そして、そのためのVC投資などの「ファイナンス」がキーワードとして急速に使われ始めたと考えています。
過去4年で「クライメート」が「事業領域」となった
こうして2022年には、VCの投資領域として日本でも「クライメート」というワードがすっかり定着したと言ってよいでしょう。起業家や投資家が領域をリサーチする中でクライメートテックも見てくれるようになりました。その結果、アカデミアに興味を持ってくださるビジネスパーソンも増えたと感じています。メディアの方々の後押しもありました。気候科学やエネルギー工学の研究者だけでなく、私のような社会科学者にもそのニーズは及んでいます。
私が環境学系の学会に初めて参加したのは2004年のことでした。かれこれ20年、環境学のアカデミアにいることになります。その名前とは裏腹に、2015年頃までの環境経済学界は、スタートアップはおろか産業界とも距離がありました。それが2015年のパリ協定採択後、TCFD[*1]の設立を受けて、徐々に機関投資家や上場企業から関心が高まり、その流れがスタートアップ・エコシステムに及んだのが2021年だったと言えます。
VCの投資領域としてカテゴリー化されたことを嬉しく思っています。こうして投資領域として認識されることにより、特化するキャピタリストやファンドが登場し、専門家が増え、投資の量も質も向上すると考えています。ビジョンのある投資が増えることで、効果的なクライメートアクションが増えると信じています。
過去4年で「政策」が立案された
2021年以降で変化があったのはスタートアップ・エコシステムだけではありません。政策立案の世界でも気候変動政策が主流化した4年間でした。バイデン前大統領が当選する直前の2020年10月にカーボンニュートラルを宣言した日本政府。連載vol.1で紹介した通り、各種の戦略や政策パッケージを次々と立案してきました。
クライメートテック・エコシステム構築に向けた、「GXスタートアップ政策」も始まり、さらなる政策の立案も続いています。昨年末に公表された「GX2040ビジョン(案)」によれば、来年度からは新たな投資促進策としての「GX産業立地政策」も予定されています。気候変動政策のアカデミアの歴史は約50年になりますが、ほんの数年前まではスタートアップ政策との融合を議論している人はまずいませんでした。
アメリカと同じく2021年から劇的に増えた「クライメート」×「スタートアップ政策」の議論。しかし、日米で異なるのは2025年からでしょう。過去4年間の政策を否定し、急ブレーキをかけるアメリカに対して、日本では着々と政策立案が進み社会実装される見通しです。風が巻き起こったタイミングこそ2年ほど遅かったかもしれませんが、突如として逆風が吹き出したアメリカに対して、日本は4年間吹いた風が徐々に強まっていく5年目、6年目となるでしょう。
2025年は日本のクライメートテックにとって「相対的に順風の年」
連載vol.3でも書いたのですが、私が気候変動問題を知ったのは京都議定書が採択された1997年の頃でした。その後、環境経済学を知り今に至るわけですが、長い間、環境問題の研究分野はあまり注目される分野ではないなと感じてきました。例えば、「経済学」という比較的大きな分野の中では、環境経済学はメインストリームとは言えませんし、長らく脇役のような存在でした。今でこそ、日本国内の多くの大学で「環境経済学」の講義が開講されていますが、元々はかなりマイナーな新興の分野です。
アカデミアの中ですらこのような状況だったため、アカデミアの外ではもっと認知度の低い学問でした。ましてや、ビジネスパーソンからの関心はほとんど無い分野だったと言っても過言ではありません。エネルギーや廃棄物関連の工学ならともかく、環境学の中でも社会科学系ということで、産業界に貢献できる余地も少なかったのだと思います。
ところが、上述した通り、2015年頃から投資家の方々を始めとした多くのビジネスパーソンの方に関心を持ってもらえるようになりました。これが一過性のものだった、となる可能性もゼロではありません。しかし、政権交代でドラスティックに状況の変わるアメリカとは異なり、日本の場合は着実に政策を組んでいくことが可能であり、ビジネスからの環境問題への関心も「階段状」に高まっていると感じます。
スタートアップ・エコシステムから関心を持ってもらえるようになったことで、私自身の意識も変わりました。それまで、アカデミアの関心であるカーボンプライシングやナッジ・キャンペーン政策ばかりを研究の関心としていました。アカデミアの方々の関心を「自分の関心」としていたのです。正直、産業創成への貢献などほとんど考えていませんでした。しかし、産業創成に取り組む起業家・投資家や政策立案者の方々からの刺激を受けて、そういった方々のニーズに応えられる研究は何か?を考えるようになりました。自分の研究や活動をよりイノベーティブにし、日本全体にインパクトを与える新たな政策や投資のクライメートアクションに貢献できるようになりたいです。
今年は2022年ほどの投資額とはならなくても、そのさらに前のような「無関心」という時代ではないでしょう。どこかで政権交代が起きようと、残念ながら気候変動が進行していることに変わりはありません。着実に政策を導入出来て、投資予見性の高い国々がクライメートテックで相対的に有利になると考えています。引き続き、気候変動問題にビジネスで、イノベーションで取り組む起業家や投資家の方々が日本にはいます。いずれ花開く時を見据えて、未来の成功者たちが着々と種まきをして、テクノロジーとエコシステムに水を与える。そんな一年になると感じています。
[1] 気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の略称。金融機関による気候関連の情報開示及び対応をどのように行うかを検討するために設立された国際的なタスクフォース。
[横尾英史:一橋大学大学院経済学研究科 准教授]
専門は環境経済学。経済学の理論と手法を応用して、環境政策に関係する人々の選択や市場の動向を研究。
京都大学にて博士(経済学)を取得。環境経済・政策学会常務理事、経済産業研究所リサーチアソシエイト、国立環境研究所客員研究員等を兼務。2024年度はスウェーデン・ヨーテボリ大学経済学部に滞在中。




 クライメートテック
クライメートテック