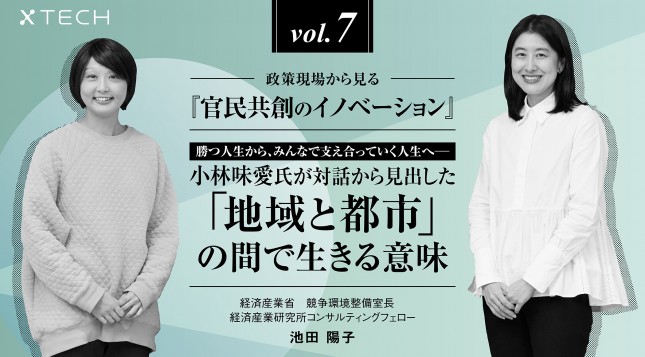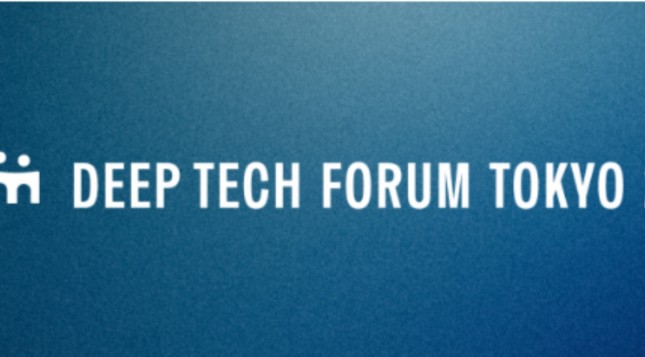クライメートテックの芽となる学界の縮小と希望|環境経済学から見るクライメートアクション vol.7
読了時間:約 8 分
This article can be read in 8 minutes
クライメートテックにはエンジニアが不可欠です。また、革新的でディープな技術の開発に向かえば向かうほど、理学・工学といったアカデミアの人材が必要になると考えられます。今回のコラムでは日本のクライメートテックのシーズとなり芽となるべきアカデミアの現況について、政府統計やスウェーデンで暮らしてみて気づいたことを織り交ぜて、一大学教員の私見を書きます。
INDEX
・日本のクライメートテック・アカデミアを目指す若者の窮状
・クライメートテック・アカデミアの希望
・博士とアカデミアが日本の専門性を高めてゆく
日本のクライメートテック・アカデミアを目指す若者の窮状
最初に、クライメートテックに関係する理工学のアカデミアについて統計を元に共有します。ここでは「研究者の卵」と言える博士課程院生と、新規の博士号取得者について統計を紹介します。結論から書くと、日本の理工学分野における研究者の卵は2003年からの20年間で減っており、さらに「質の低下」が起きていると認識されています。ただ、この縮小トレンドはこの一年二年で底を打った可能性もあります。これらのクライメートテック・アカデミアの希望については後段にまとめます。
まず、理工学に医学薬学やその他も含めた日本の研究者数は2023年に70万人(専従換算)で中国、米国に次ぐ世界3位です(参考資料)。科学技術とイノベーションでの立国を掲げる国として、両大国に次ぐ層の厚さは強みといえます。しかし、この人数はこの四半世紀でほぼ横ばいです。一方、中国を始め、米国、欧州、さらには韓国もこの20年で研究者数を増やしています。ディープテック領域でのスタートアップ創造が進むこれらの国々が研究者数を増やしているのは注目に値します。
このように他国と比べると研究者数が伸び悩んでいる日本ですが、私が問題視するのはその高齢化と理工学系の減少傾向です。例えば、大学教員における40歳未満の割合が過去40年以上も低下し続けており、人数も減少しています(参考資料)。
また、日本で新たに博士課程に入学する人が2003年度をピークに20年間減っていました。2023年度に下げ止まりを見せた可能性がありますが、今後の見通しは不透明です。そして、過去20年でとりわけ減少したのが理工学の博士課程入学者です。2003年度と2018年度を比べると約三割(1500人以上)減少しています(参考資料はこちら)。つまり、世界で増えるPhDホルダーと研究者数のトレンドとは逆で、日本では理工学の研究者、特に若手研究者が急速かつ長期に渡って減っており、博士課程入学者数から予測すると向こう三年ほどはこのトレンドが続くでしょう。
その上でさらに危惧されるのは博士課程に進む研究者の卵の「質」の低下です。文部科学省の研究所による大学教員を対象としたアンケートの結果、「望ましい能力をもつ博士後期課程進学者の数」が減り、「著しく不十分」との認識が強まっています (参考資料)。
驚くべきことにこの認識が大学教員と政府の間で持たれるようになってからすでに15年以上経過していることです。このアンケート調査は20年近く継続して実施されており、2009年調査ですでに「研究や開発に関わる職業が高校生や大学生にとって魅力的で無く、望ましい能力を持つ人材が博士課程後期を目指していないとの認識が増えている。」との文言が登場しています(参考資料)。
これらの統計を見て、「日本の優秀層は海外の博士課程に進学するのでは?」と思う方もいるでしょう。そういう優秀な若者がいるのも確かです。しかし、米国で博士号を取得する日本人の数も2007年を境に大きく減少しています(参考資料)。これもまた中国とは対照的です。
日本の若者にとって「博士」や「研究者」の人気が低下しているのでしょうか。これは複雑な質問になります。研究職に対する人気は下がっていないかもしれません。なぜならば、中学生や高校生を対象とした調査では「将来つきたい職業」の上位に「研究者」が出てきます(参考資料)。その上で残念ながら、「日本に生まれた多くの人にとって、成りたくても成るのを諦めざるを得ない職業」になっていると私は考えています。詳しくは紹介しませんが、中国と欧米諸国と比べると、日本における博士課程の期間の経済状況と博士号を取得してからのキャリアパスの両方において、現状には大きな差があります。
連載vol.1に書いた、日本の政府と投資家がクライメートテックやGX領域で世界的なスタートアップを輩出しようと意気込んでいるところに水を差すようですが、その種や芽となるはずのアカデミアの状況は極めて厳しいという認識です。研究者の数こそさほど減らないかもしれませんが、世界の学界をリードする質の高い若手人材の数が向こう数年は減っていくことが既定路線です。過去20年間の歴史と他国との差の現実を直視して、私たちは今後の政策立案や投資を行っていく必要があります。
クライメートテック・アカデミアの希望
ここまで書いた通り、日本のアカデミア全体が苦境に立たされており、中国や欧米で進むクライメートテック・エコシステムの創造競争に対抗できるレベルとは言い難いのが現状です。それでも、最近の日本のクライメートテック・アカデミアとエコシステムを見渡し、博士課程を出た若い世代を見ると希望もあります。
まず、上でも書きましたが2003年からの博士減少トレンドが下げ止まった可能性があります。十年以上、文部科学省が警鐘を鳴らし続けてきた成果がようやく出てきたのかもしれません。また、科学技術振興機構(JST)が2021年度より「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」という博士課程院生の支援事業を始めており、その効果があった可能性もあります。これらのより正確な効果検証が待たれます。
クライメートテック領域の国立研究所や博士人材を求める企業による新たな取り組みも始まっています。国立の研究所の中で、最もクライメートテックと関係のある産業技術総合研究所では「修士卒研究職」というポストがあり、2024年度からは研究員として働きながら業務内で博士号の取得が出来ます(詳細はこちら)。また、島津製作所や富士通は大学と提携し、博士課程に入学した院生を採用し給与を出す制度を始めています。このように官民のイノベーティブな制度が増え、欧米のように給与をもらいながら博士課程で研究に打ち込める機会が日本にも生まれてきているのは希望です。
この他、私個人が目にして感じたことから、三つの希望を見出しています。
一つ目の希望は、海外で武者修行する若手研究者たちとその人たち向けの新たな機会です。私が子供の頃、日本人がプロ・バスケットボール選手になりたければ海外に行くしかありませんでした。21世紀に生まれた日本人の場合、「職業としての研究者」もそうなりつつあると言えるかもしれません。そして、私はそんな時代に対して残念な気持ちと悲しみがありますが、一方で海外に出て研究の道を志す若者が多少はいて、彼女・彼らを「希望」と感じています。
そんな「日本を出て研究者を目指す若者」を支援する取り組みが複数あることに、スウェーデンで生活するまで、気づいていませんでした。例えば、日本の研究者なら誰もがお世話になっている日本学術振興会(JSPS)の事業が一例です。先日私はJSPSがスウェーデンで開催してくれた日本人研究者交流会に参加し、欧州で研究する次世代と知り合う機会がありました。また、政府のみならずVCもそういった若者にチャンスを用意してくれています。例えば、Beyond Next Venturesでは「日本国籍を有する海外在住の研究者・留学生」を対象としたディープテック・スタートアップでの就業体験プログラムを始めています。関連して先日は、海外MBA生や研究者向けにクライメートテックのオンラインイベントも開催してくれました。私が大学院生だった頃には無かったこの手の機会が官民の両方から出てきているのが希望と感じます。
二つ目の希望は、若き博士号取得者が投資家としてVCや銀行で働く時代が到来したことです。実は私は学部生の頃に「学者の道以外を志すとしたら何がいいだろう?」と自問し、その答えとしてVCで長期インターンをさせてもらったことがありました。ただ、2003年当時は「私は博士課程に進んで研究者になります」と言ってVCでインターンするのは無理がある時代だと感じてしまいました。(当時からすると意味不明な私を面白がってくれたベンチャーキャピタリストさんのことを忘れません。)
しかし、今の日本では博士号取得者が少しずつVCや銀行で働いています。例えば、Beyond Next VenturesやANRIなどが博士号取得者を雇用されています。また、三井住友信託銀行でも環境・エネルギー分野の博士号保有者が複数働くTechnology based Financeチームで脱炭素に取り組んでいます。日本では目新しいこれらのキャリアパスで奮闘されている博士たちを私は希望と考えています。日本ではロールモデルが少なく、私自身も20年前に検討はしたけれど選ばなかった道です。険しく、思い悩むことが多いと思いますが応援しています。今の日本では息苦しいかもしれませんが、海外にはPhDホルダーが同じく研究者の起業家チームと議論し、サイエンス・ベースドなカンパニー・クリエーションを行うVCがいくつもあります。
三つ目の希望は大企業の事業会社でクライメートテックに取り組む若手研究者の皆さんです。こういった方々が積極的に社外との交流を増やしているケースが希望です。スウェーデンに暮らす前は前回コラムvol.5で紹介した様々な勉強会やイベントに参加していました。そこで知り合ったゼネコンや化学系の大手事業者で働く研究者・エンジニアのみなさんも希望です。こういった方々が、出身の研究室や学会との関係も続け、論文も公刊しつつ、VCやスタートアップが参加する勉強会に顔を出す日本の現状に希望を見出しています。博士号取得者が大学や国立研究開発法人だけでなく、事業会社、VC・銀行、そしてスタートアップを行き来する、いわゆる「回転ドア」なエコシステムが日本にも出来てくると、イノベーションに繋がると信じています。
博士とアカデミアが日本の専門性を高めてゆく
私自身はクライメートテックのシーズとなる理工学の博士ではありません。ただ、政策や経済に関する分野ですが、環境・エネルギーに関連する分野の博士の一人ではあります。また、日本の国立大学の教員の一人でもあります。私は2007年4月に日本の大学の博士課程に進学しましたが、その研究科でも先輩院生は多いものの、後輩は減っていく状況でした。まさに上述した「博士院生が減少していく」時代を身を持って知っています。それから時が経ち、2年ほど前からは院生を指導する側になりました。
博士や大学教員が「博士号取得者を増やそう」というのは、どうしてもポジション・トークに聞こえるでしょう。そもそも、院生になる学生をリクルートし、育成する立場の人間が、政府や他の事業者に期待するのも他人任せな話です。スポーツ選手やお笑い芸人、YouTuberが社会で活躍しているの見る機会が増えると、それを目指す次の世代が増えるのだと思います。日本で博士が減っていることを様々な要因で語ることは可能ですが、そもそも現役の博士が社会に貢献し、活躍していればフォロワーが自然と出てくるはずです。
上で引用した文部科学省の報告書をさらにご覧いただくと統計も出ていますが、現代の大学教員の時間的余裕は限られています。それでも、この危機的状況で希望を見出し、他者にとっての希望となれるよう、自分たち博士が研究とその社会実装で社会に貢献していくべきでしょう。それが一番の打開策になることは分かっています。
科学に基づき、研究も出来て、それでいて事業やプロダクトも創る。そういう人材がクライメートテック・エコシステムの発展に必要です。この分野のアカデミアへの投資が官民問わずに増え、そこから育った博士・研究者たちが大学を飛び出し、エコシステムの様々な場所で活躍するこの国の時代を見据えています。
[1] 文部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術指標2024
[2] 文部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2023), NISTEP REPORT No.201.
[横尾英史:一橋大学大学院経済学研究科 准教授]
専門は環境経済学。経済学の理論と手法を応用して、環境政策に関係する人々の選択や市場の動向を研究。
京都大学にて博士(経済学)を取得。環境経済・政策学会常務理事、経済産業研究所リサーチアソシエイト、国立環境研究所客員研究員等を兼務。2024年度はスウェーデン・ヨーテボリ大学経済学部に滞在。




 クライメートテック
クライメートテック