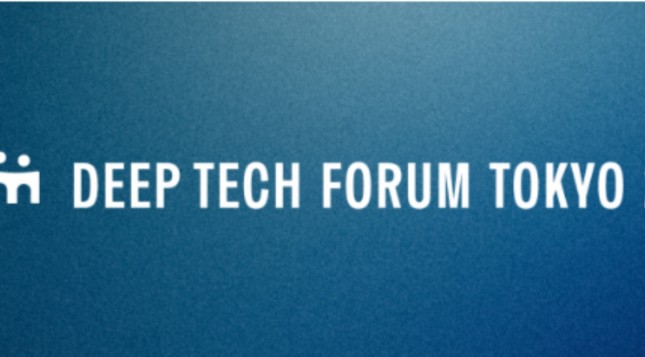IT企業歴37年。ハネウェル・シスコなどでカントリーマネージャーを歴任したOpenLegacy 日本法人 内田氏が語る、ビジネスの“目利き”
読了時間:約 9 分
This article can be read in 9 minutes
IT企業歴37年。ハネウェル・シスコなどの事業体でカントリーマネージャーを歴任したOpenLegacy 日本法人 内田氏が語る、ビジネスの“目利き”
数々の外資系IT企業で日本法人の経営を担い、成功に導いてきた人物がいる。それがOpenLegacy日本代表・ゼネラルマネージャーを務める内田雅彦氏だ。
Oracle、Informatica、AppDynamics(現Cisco)など内田氏が関わってきた企業の多くは、現在では大きな影響力や知名度を誇っている。しかし、内田氏の就任のタイミングは、そのほとんどが拡大前のフェーズ。そこから事業や製品のポテンシャルを引き出し、大きな存在感を持つまでに成長させてきた。
果たして内田氏は、どのようにポテンシャルのある企業や事業、プロダクトの“目利き”を行っているのか、そして見極めた企業・事業・プロダクトをどのように成長させているのか、そしてOpenLegacyにどのようなポテンシャルを見出しているのか……その豊富な経験を語ってもらった。

内田雅彦
イスラエル発のFintechスタートアップ企業 OpenLegacy 日本代表
1985年 國學院大學を卒業後、当時世界第2位のコンピュータメーカー Digital Equipment Corporation(DEC)にセールス・エンジニアとして入社。以後 日本オラクルを経て、コグノス、インフォマティカ、ハネウェル、シスコシステムズの事業体で日本代表を歴任し、2021年5月より現職。ハードウェア・ネットワークからソフトウェア・アプリケーションまで、汎用コンピュータからクラウド・モバイルまでと、幅広い守備範囲で、エンタープライズ企業向けの セールス・マーケティングを確立してきた、自称「外資系ITの立ち上げ屋」。
INDEX
・目を向けるべきは、「製品」よりも、その「用途」。一次情報にこだわり、トレンドを掴め
・シンプルなアーキテクチャと経営者の人格が、企業や製品の未来を創り出す
・レガシーな金融業界を刷新させる「ドリルの刃」を磨いていく
・ここがポイント
目を向けるべきは、「製品」よりも、その「用途」。一次情報にこだわり、トレンドを掴め
――まずは簡単に内田さんの経歴について教えてください。
内田:これまで37年間、外資系IT企業一筋でした。ファーストキャリアは、アメリカのコンピューターメーカーDigital Equipment Corporation(以下、DEC)。私が働いていた1980年代後半〜1990年代前半は、まだ家庭用PCはほとんどなく、企業が使用する業務用のコンピュータを扱っていましたね。DECがCompaq社(後のHP社)に吸収合併された後は、当時はまだ駆け出しだったOracleの日本法人で10年ほどマーケティングなどに従事。その後いくつかの外資系IT企業の日本法人で経営を担い、2021年からOpenLegacy日本法人のゼネラルマネージャーに就任しました。
――Oracleのように、内田さんが経営に携わられた当初は駆け出しだった企業が、現在となっては大きな影響力を持っているケースが多いのではないかと思います。企業や事業、プロダクトのポテンシャルを見極める際に、どのような経験が活きていると思いますか?
内田:まずOracleでの経験が大きいと思います。当時のOracleは、IBMからさまざまな才能を持った人材が集まってきていました。売るものはデータベース1つだけなんですが、仲間たちはそれを幅広いお客様のビジネスに適用させようとしていたんです。そこで学んだのが、製品や道具を売るのではなく、それらを使って「何かを実現させること」を売る、ということでした。
振り返ると、1社目のDECは、プロダクトアウトの会社。現在でも有線ネットワークの標準技術であるイーサネットを最初に商品化した企業のひとつでもあったし、当時世界最速のCPUを開発、さらにはOracleデータベースの冗長化機能やMicrosoftのWindows Serverの原型にも、DECのシステムが使われるほど技術力には相当定評があったんです。ただ、製品を磨くことに注力し過ぎた結果、最終的には吸収合併に至った過程を目の当たりにしました。会社が持っている製品を、「どんな用途に向けて売るのか」という視点があるか、ないかで、企業の未来は変わってくるんだと気づいたんです。

――製品をどんな用途に向ければ市場に受け入れられるのか、という視点を持つことで、企業や事業、プロダクトを見る目が養われてきたということでしょうか。
内田:はい。しかも、既に世の中に広まっているものではなく、製品が時代ごとに必要とされ始めるタイミングを見極めることは心がけていました。例えば、海外ではよく知られているけれど、日本国内にはまだ浸透していない製品によく注目していましたね。ビジネスやIT業界の面白い取り組みは、日本よりもアメリカで生まれることが大半ですから。
――そのように製品の用途について考えたり、海外のIT業界の動向を注視したりしていても、実際に事業や製品の成否を見極めるとなると難しいと感じる人も多い気がします。その精度を高めるために、具体的にどのような行動をされていたんですか?
内田:情報ソースとして、雑誌などのメディアで得られる二次情報よりも、現地の仕事仲間やトップランナーの動向といった一次情報に価値を見出しています。メディアの記事は、すでに物事が盛り上がった段階で、取材があって、記事になって……とトレンドの発生時点から考えるとタイムラグがある。その点、感度の高い現地の人材が取り上げるトピックは情報の鮮度が違います。
私のキャリアが外資系IT企業で一貫しているのは、最先端のトレンドに関する現地の仕事仲間からの良質な一次情報が得られることも大きな理由のひとつです。「アメリカでは、これがビジネスのトレンドなのか」「そんなビジネスを加速させるために、こんな道具が生まれているのか」「その道具の中で一番先鋭的なものって何だろう」……といったように、関心に従って情報収集していくと、自然と人的ネットワークも広がっていきます。今でもLinkedinで繫がったかつての同僚たちがどんな面白い仕事をしているのか見ていますよ。
シンプルなアーキテクチャと経営者の人格が、企業や製品の未来を創り出す
――ビジネスのトレンドについては、感度の高い仲間からの一次情報で推測できたとしても、実際に「どんな製品が、どうして市場に受け入れられるのか」といった眼を養うためには、ビジネスとは異なる知識や技術に関する理解が必要に感じます。その点については、どのように考えればよいでしょうか?
内田:注視すべきはハードウェアではなく、ソフトウェア。歴史を紐解くと、1946年に真空管を使った初めての汎用コンピュータが生まれてから、その根本的な仕組み自体はなんら変わってはいません。ただひとつひとつのテクノロジーが進化して、高速になったり、ネットワーク化して分散化したりしてきただけ。ハードウェア側でのイノベーションは、最近盛んに研究されている量子コンピュータが実用化されるまでは、もうそれほど起きないのではないかと考えています。IT業界で大きく変わり続けていることと言えば、結局ソフトウェアの領域に限られるんです。さらに言えば、「そのソフトウェアを何のために使うのか」という適用技術の広がりとも言えるでしょう。例えば、最初のコンピュータでは科学技術の計算用に使われていたソフトウェアは、現在ではeコマースの商取引や銀行取引など私たちの生活の身近なところに適用されています。

――ソフトウェアの筋の良さを見極めるポイントはありますか?
内田:ソフトウェアにも、OS、ミドルウェア、アプリケーションソフト……と、さまざまなレイヤーがありますが、どのレイヤーを見ても、アーキテクチャがシンプルでわかりやすいものに発展の可能性があると思います。その理由のひとつは、説明がしやすいこと。専門家にだけわかればいいものはニッチに収まりがちですが、専門知識がない人にまで伝えやすい製品は市場に受け入れられる素地があります。結局ビジネスの現場では、相手に「この製品は、こんな動作をする。だから、あなたの仕事のここを助けることができます」とシンプルに伝えないといけません。そのときには、ソフトウェアの仕組みに触れずにはいられない。だからこそ、アーキテクチャを簡単に説明できる表現を持っているかどうかは、とても重要なんです。例えばiPhoneは、ひとつの好例ですよね。実際に中身は複雑で緻密な技術に裏打ちされているけれど、それをシンプルな思想で表現して伝えている。それまでは携帯電話には、分厚い説明書に使用しない機能の説明まで書かれていたり、読み込まないと会得できない操作もあったりしましたが、iPhoneの説明書は数枚のビジュアルで操作説明を完結させるくらい非常にシンプルなアーキテクチャ設計がなされています。
また、アーキテクチャがシンプルだと応用が利きやすい。その製品を取り巻く周辺領域からどんどん適用範囲が拡がり、多種多様なビジネスに影響を与えるエコシステムができあがってきます。かなりつくりこまれた企業独自の技術であるほど、展開の可能性には限界が生まれるはず。iOSは独自技術を堅持していますがこれは例外的ドミナントだからできることであり、事実海外ではAndroidのシェアのほうが高い。かつてのDECのOSが、UNIXそしてLinuxに代替されてきたように、誰でもシンプルに理解でき、改善改良できるオープンソースのソフトウェアに取って代わられてしまうでしょう。
――ほかにも、事業や製品の発展可能性を見極めるポイントはありますか。
内田:もうひとつ、忘れてはいけないのが、創業者あるいは経営者に人間的な魅力があるかどうか。多くの人を惹きつける人間のもとに優秀な人材が集まってきますから。結局、優秀な人材が集まるからいい事業や製品が生まれる、という至極シンプルな結論に行き着くんですよね。私が日本法人の経営を預かるときも、まずは創業者やCEOが掲げるミッションステートメントやメッセージに共感できるかどうかが最初の判断ポイントです。そこに大義がないと、それを日本市場にお届けするモチベーションは湧いてきませんから。
レガシーな金融業界を刷新させる「ドリルの刃」を磨いていく
――これまでさまざまな企業の日本法人の経営に参画してきた内田さんですが、今回は金融業界を主な対象としたAPI統合プラットフォームを提供するOpenLegacyの日本法人カントリーマネージャーに就任されましたよね。どのような観点で金融業界に目を向けられたのでしょうか。
内田:これまでさまざまな業界の企業を担当してきましたけれど、実は金融だけは深掘りしたことがなかったんです。なぜなら、決まったことしかできないビジネスだと思っていたから。ATMと元帳にある残高が繫がっている、そのお金を払い出す、貸し付けする、銀行間送金する……それ以外に変数がないように見えてしまって。でも、低金利が続く中、もう従来型のビジネスモデルでは儲からなくなってしまった。そこにフィンテックの流れが入ってきたことで潮流が変わり始めたと思えるんです。例えば、しばしば日本の投資教育の遅れを象徴する例として挙げられるタンス預金について取り上げましょう。長く現金で持つことが一番安心と考えられてきましたが、現在ではここにフィンテックがアプローチして、スマートフォンを使って気軽にお金を運用してもらおうという流れを生み出すことに成功しつつあります。レガシーな業界と、フィンテックが融合することで行動様式の変化を生み出す、そして国民レベルでの投資や金融に対する考え方に影響を与える……そんな大義のもと、自分のキャリアの集大成に金融業界に身を投じることを決めました。

――OpenLegacyが取り組むAPI統合プラットフォームが市場に求められている背景を教えてください。
内田:現在、特に金融業界では、APIの必要性というのはかつてないほど高まってきているんです。金融業界では、現在ほとんど新規開発に使われてないような言語でつくられたレガシーなシステムが、ずっと使われ続けてきました。これを最新のシステム移行するためには、膨大な工数とリスクを伴うのでなかなか踏み込めない。しかもその言語を使って構築していたエンジニアは、徐々に歳をとって引退するようになってくる。そうなると、レガシーなシステムと最新の活用体験を提供できるフィンテックとをつなげる人がいなくなってしまいます。例えつなぐことができたとしても、かなりの時間を要することになります。ある銀行システムとバーコード決済サービスを連携させるのに1年半以上かかるという事態も珍しくありません。
――そんな背景の中、OpenLegacyは、どのような点に特徴があるのでしょうか
内田:まず、アーキテクチャのシンプルさが、OpenLegacyが非常に優れている点です。一言で言えば、「レガシーなシステムに直接接続して、自動でAPIを生成するツール」。バックエンドのシステムを変更するリスクも、データ移行の手間もなく、外部の新しいデジタルサービスやアプリと接続し、すぐに活用できるようにします。
例えるならば、OpenLegacyは、金融事業者が持つレガシーシステムという山に、APIというトンネルを掘るための、優れたドリルの刃。どんな刃かというと、さまざまな現場に応じて最適な穴を一気に開けることができるいろいろな刃を取り揃えています。しかも、ただ穴を開けるだけではなくて、そこを舗装して、どうやって交通をコントロールした方がいいかまで考えていますし、いくつものトンネルを開通させてもその工事方式はすべて標準化させることができます。要するに、OpenLegacyは、さまざまなレガシーなシステムに対応できて、簡便で、メンテナンスもしやすい良質な連携を生み出すツールなんです。
ただ、あくまでOpenLegacyは「ドリルの刃」でしかない。その道具を使ってお客様は何のためにどんな穴を開けたいのか、といった視点を持ちつつ、ビジネスを創り上げていければと思います。金融業界で、日本が世界と対峙していく際の大きな武器になるはずだと私は信じています。

――最後に読者にメッセージをお願いします。
内田:人にはそれぞれ才能があります。私の場合は、ポテンシャルのある事業、製品を見極めること、またそれらをどうやってマーケットインさせるのか、海外の優れた事業、製品をどうやってローカライズさせるのか、といったことを考える才能があったかもしれません。ただ残念なことに、自分で0から事業を創り出す才能はないようです。現にいくつもの企業で「経営」は経験しましたが、「創業」は経験したことが一度もないんです。だからこそ、スタートアップとして新しいトレンドを生み出そうとしている人たちを尊敬しています。自分の才能を発揮できて、仕事に楽しみや意義を見出すことができる人が増えることを願っています。
ここがポイント
・製品を「どんな用途に向けて売るのか」という視点があるか、ないかで、企業の未来は変わる
・二次情報よりも、現地の仕事仲間やトップランナーの動向といった一次情報に価値を見出す
・IT業界で大きく変わり続けていることと言えば、結局ソフトウェアの領域に限られる
・アーキテクチャがシンプルでわかりやすいものに発展の可能性がある
・創業者あるいは経営者に人間的な魅力があるかどうかも重要
・OpenLegacyを例えると、金融事業者が持つレガシーシステムという山に、APIというトンネルを掘るための、優れたドリルの刃
企画:阿座上陽平
取材・編集:BrightLogg,inc.
文:小林拓水
撮影:戸谷信博




 Fintech
Fintech