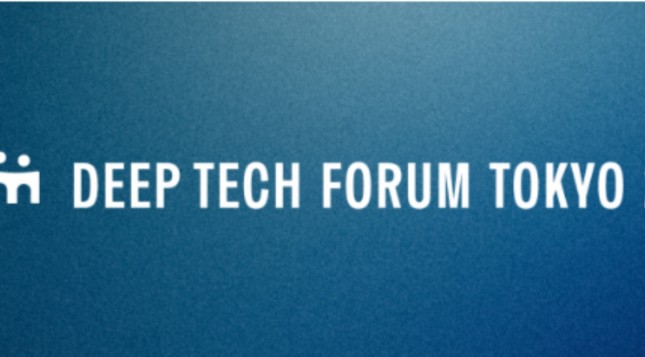インクルーシブな職場づくり、航空交通管理の現状と展望、実体験の拡張技術、DESIGN as a Verb…など、最先端分野の今を知る【東大Week@Marunouchi DAY3】
読了時間:約 11 分
This article can be read in 11 minutes
2022年に産学協創協定を締結した東京大学と三菱地所が、取り組みの一環としてスタートしたトークイベント「東大Week@Marunouchi」。ビジネスの中心地である丸の内にて、東大の教員が各々の専門分野に関する講話を行なった。
昨年に続き第2回目の開催となった今年は、「当事者研究の視点から考える包摂的な職場づくり」「物理素材を活かすインタフェースと実世界体験の創出」「技術と心をつなぐデザイン」「航空輸送と航空交通管理の最新トレンド」など多種多様な講話が繰り広げられた。
有楽町 micro FOOD&IDEA MARKET と丸の内にあるGARB Tokyoの2会場にて3日間にわたって行われた本トークイベント。今回は3日目である2023年8月10日の様子を紹介する。
INDEX
障害を持つ当事者の視点から探求する「包摂的な職場づくり」
食べ頃を自ら報せるリンゴ、硬さが変わる布など……物理素材を活かすインタフェースと実世界体験の創出
デザインエンジニアが心がけるべき、「どうしたら物事がより良くなるか」の追求。
日本の空で発生する“大渋滞”を解消するために。航空交通管理の現状とこれからの挑戦。
障害を持つ当事者の視点から探求する「包摂的な職場づくり」

有楽町 micro FOOD&IDEA MARKETにまず登壇したのは、東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎氏。熊谷氏は生まれつき脳性麻痺という身体障がいを持っており、電動車椅子で生活をしている。東大医学部を卒業後に小児科医となり、2009年より先端研にて研究活動を開始した。熊谷氏の専門は、障がいや障がい以外の困りごとを抱えている当事者ならではの視点から問題の解釈や解決方法を探求する「当事者研究」。また小児科学における自閉症やADHDといった発達障害の研究も行なっている。
講話では、「包摂的な職場つくりについて ~当事者研究の視点から~」をテーマに、インクルーシブな組織を作るための組織文化について語られた。
熊谷「私が生まれた1970年代は、“皆が健常者になれば社会はうまく回る”と考えられていた時代でした。私は1日5〜6時間のリハビリを行なっており、いつも泣いていた記憶があります。しかし80年代になってリハビリには効果がないことが研究によって明らかになり、“科学は嘘をつく”ということをそこで初めて知りました。しかし同時期に世の中もガラリと変わり、障がいは障がい者の体の中ではなく外、つまり社会環境の側にあるのだという考えが世界を席巻したのです。この社会モデルの考え方により、私はこの体のまま堂々と生きていていいのだと励まされたのを覚えています。 これが、今の私に至る原体験となっています。
一方で、外見などでパッと分かりやすい障がいだと社会モデルの考え方が馴染みやすいのですが、自閉症のように周囲から見えづらい障がいを抱えている場合はそうもいきません。自分自身も障がいに気づけないため、“自分が悪い”と社会環境を変える方向に向かいづらいのです。同様に、最近は産後うつやセクシャルハラスメントという言葉がよく使われるようになりましたが、昔はこの言葉がなく、女性たちは“私は母親・女性失格なのだろうか”と自分の問題として解釈せざるを得ませんでした。このように、私たちが日常的に使っている言語というツールも、実は健常者などのマジョリティ向けにデザインされていると言えます。
このような解釈的不正義が起きぬよう、少数派に合った経験を表す言葉を新たに発明しなければなりません。この発明のプロセスを“当事者研究”と呼ぶのです」
そして話題は、インクルーシブな職場をどのように実現していくのかというテーマに移っていく。熊谷氏はまず小児科の研修医だった時代を振り返り、障がいを持ちながら仕事をする大変さ、そして研修医2年目のときに出会った上司の存在の大きさについて語った。
熊谷「当時、私は口に注射器を加えてドラキュラのように血を吸うことで採血を行なっていました。教科書の採血方法とは随分違いますが、上司は『採血の本質は、スピード・相手を泣かせない・血液を傷めないの3つだけだ。その目的さえ達成できれば良く、また達成の手段は多ければ多いほどいい。むしろ教科書どおりにしか採血を行えない医療者・医療施設は患者を救えない』と言ってくれたのです。この言葉で、組織のパフォーマンスを維持することと、ダイバーシティ&インクルージョンな組織づくりは両立できると教わりました。最近は、障がいを持つ患者さんに対しては、障がいを持つ医療者が担当した方が患者満足度が高いという論文も出てきています」

藤川なつこ. (2015). 高信頼性組織研究の理論的展開:ノーマル・アクシデント理論と高信頼性理論の統合の可能性. 組織科学, 48(3), 5-17. の表 1 とテキストをもとに作成
熊谷「最後に、包摂的な職場づくりについて理論的に解釈したいと思います。キーワードは“高信頼性組織(HRO)”です。高信頼性組織とは原子力発電所や潜水艦など緊迫度が高く、ハイパフォーマンスを安定的に維持しなくてはいけない組織のことを指します。HRO研究で分かったのは、HROが安全に運営されるためには、想定外の失敗が起きたときに常に想定をアップデートする文化と、失敗の要因を個人ではなく組織に帰属させる文化が必要だということです。また、HROを社会実装する際には“心理的安全性”も重要になります。そして最近、この2つの文化と心理的安全性が備わっていることで初めて、ダイバーシティ&インクルージョンな組織はパフォーマンスを向上させられるということが報告されました。
私は今後、HROを皆さんの職場で実現できるようお手伝いしていきたいです。そしてこれを実現するためには、リーダーが当事者研究を学ぶということが有効だと考えています」
食べ頃を自ら報せるリンゴ、硬さが変わる布など……物理素材を活かすインタフェースと実世界体験の創出

続いて登壇したのは、東京大学大学院情報学環教授の筧康明氏。実体性を有するインタラクティブメディア技術およびデジタルファブリケーションの研究に従事し、メディアアート作品制作やデザインに携わっている。
今回の講話のテーマは「Material Experience Design〜物理素材を活かすインタフェースと実世界体験の創出〜」。現実世界の体験を拡張する最先端な研究・活動の成果について、筧氏に解説・紹介してもらった。
筧「私は2018年に東大の情報学環・学際情報学府で研究室を立ち上げました。研究室のメンバーは芸大や美大卒の人、工学系や建築系の学生、これまで海外で学んできた人……など分野も国籍も多種多様で、普段は交流しないような人が一緒になって議論を重ねているという環境です。
最初に紹介するのが『Air on Air』というプロジェクト。これはコロナ禍の最中に制作したもので、家から出られない状態でも新しい集う体験を生み出す作品ができないか?と考えました。
『Air on Air』は、スマホとバブルマシーン(シャボン玉を発生する装置)が繋がっていて、スマホやPCのマイクに息を吹きかけると、バブルマシーンが海外などの遠くにあってもその息が届いたかのようにシャボン玉が飛ぶという作品です。このプロジェクトでやりたかったのは、オンライン会議など平面でしか繋がることができない状況に対して、実物のシャボン玉が飛ぶことで画面の向こうの風や空気といった“奥行き”を再確認するということでした。今回の活動ではそれに加えて、シャボン玉という実物の素材が現れることで向こうにいる人が反応を示してくれる、つまり偶発的なコミュニケーションが生まれるという発見もありました」
筧氏は、VRやARなどを探求する研究室からスタートし、その後2000年頃に「カームコンピューティング」という情報技術のビジョンに出会う。これは、コンピュータがある種意識されることなく世の中に配置され、その恩恵をさまざまな場所や形で受けられるというもので、研究者のマーク・ワイザーが提唱した。
筧「当時私は、プロジェクターの技術を使って、何の変哲もない物理世界にデジタルなディスプレイを膜のように重ね合わせることでインタラクティブな場をつくるという、今でいう “プロジェクションマッピング”の研究を行なっていました。そうこうするうちに、メディアアーティストと名乗る人から研究を作品にして美術館に展示しないか?と声をかけられました。それがアートやデザインなど表現領域と関わるきっかけです。
またカームコンピューティングの概念から派生して、私は“コンピュータを意識しなくてよいだけでなく、コンピュータによって人が動きたくなったり物理世界にイキイキとした世界が生まれる”という賑やかなテクノロジーやインタフェースを作ることに興味を持ちはじめました。その結果、プロジェクションではなく、その先にあるオブジェクトやマテリアルをいかに拡張するかという別レイヤーの研究へと関心が広がっていったのです。
その後、2015年にMITメディアラボで1年間滞在研究を行ったのですが、そこでマテリアルに関心のあるデザイナーや、研究者、科学者のコミュニティに出会うことができました。私が取り組んだのは、材料からインタラクションを作ってみるという研究です。たとえばPH(酸性度)によって形や色、匂いが変わるというマテリアルを調合しました。さらに、これは少し将来的な展望でもあるのですが、食べ頃を自ら表してくれる食べ物や、雨のPHを表してくれる傘、あるいは自分の身体が汗の具合を読み取ってタトゥーのように模様ができる機能……なども研究開発を進めていきました。コンピューターを介してその先でマテリアルが反応するのではなく、マテリアルそのものがインタラクションや情報提示のメディアになるという点で、これは大きなチャレンジだったと思います。この経験を皮切りに、色や形、振る舞いなどを動的に変化させる新しいマテリアルや、そのインタフェースとしての活用可能性や新しい表現の探求を進めています」

筧「最後に、先日まで丸の内で展示していた作品をご紹介します。今の私は、これまでの技術を日々の暮らしにどう使われるかということに強い関心を持っています。その一つの取り組みとして、 京都の西陣織の職人さんやファッションテックの企業の方たちと共に、変色や発光、変形など新しい機能を持つテキスタイルを開発しています。緯糸(よこ糸)に金箔や銀箔を塗布して艶を仕込むという西陣の伝統的技法を活かしながら、電気をかけると光る糸や温度によって色が変わる糸などを開発し、西陣織の意匠と共にしなやかで美しい布として織り込んでいったんです。
今後は、身のまわりにあるさまざまな質感を持ったマテリアルやオブジェクトに情報技術を重ねて、我々の体験やインタラクションをもっと豊かにしていきたいなと考えています」
デザインエンジニアが心がけるべき、「どうしたら物事がより良くなるか」の追求。

もう一つの会場「GARB Tokyo」で登壇したのは、デザインエンジニアの吉本英樹氏。東京大学で航空宇宙工学を専攻した後に英国のロイヤル・カレッジ・オブ・アートで博士課程を修めたという、デザイン界ではかなり異色の経歴をたどってきている。2015年にロンドンにデザインスタジオを設立し、デザインとテクノロジーを融合させる手法で、エルメスなどの高級ブランドを顧客に製品開発から展示会ディレクションまで、多方面で活躍している。
近年では、日本の伝統工芸と先端技術を繋ぐ国際的なイニシアティブ「Craft×Tech」を創立し、日本文化の進化・継承にも取り組まれている。東北6県の産地とコラボレーションし、400年〜800年続く伝統工芸という文化の新しいページを作ることにも今まさに挑戦中だ。
今回、デザインエンジニアとして大切にしている考えや「デザインとは何か?」というテーマについて語った。
吉本「私がデザインやプロジェクトを進める上で考えることが2つあります。それは“Narrative(物語)”と“Borrow(借りる)”という言葉です。“Narrative(物語)”の事例をまずご紹介しますと、昨年名古屋のミッドランドスクエアという商業施設のクリスマスツリーをデザインしました。その時に依頼されたテーマが“SGDsなツリー”。私が悩み考えた末につくったのが、ジャングルジムのツリーです。クリスマスツリーのようなジャングルジムといったほうが良いかもしれません。ツリーを12月25日まで展示し、クリスマスが終わった後に解体して廃棄するのではなく、ジャングルジムとして保育園に寄贈するということにしました。破棄をしないというだけでなく、ジャングルジムは10年20年と長い期間残るものですので、これから大勢の子ども達が遊ぶ中で、“このジャングルジムは、2022年に大勢の人を魅了してきたクリスマスツリーだったんだよ”という物語もできますよね。本来であればクリスマスシーズンだけという2〜3ヶ月の短い命だったものが10年・20年と続き、後世に語られるものとなる。そんな点をコンセプトにしました」

吉本「次に“Borrow(借りる)”ですが、日本には『借景』という言葉がありますよね。日本庭園において庭外の風景をも景観として利用することを意味するのですが、まさにデザインも同じことだと考えています。私たちがつくるデザインや作品物は、入り口でしかなくて、観る人の中にあるイメージや記憶を想起させたり思い出させたりすることで、その体験を通して、作品は完成すると考えています。そのような意味で“Borrow”ということなんですね。私がデザインに向き合う上で大事にしていることです」
最後に「デザインとは何か?」という問いに対して、吉本氏は「To Design is… To Make it Better」、と答える。
吉本「たとえば、iPhoneのデザインが良いよねと感じたとき、それが生まれるまでには“To make it better(and better)”のための数多の苦悩があり、もっと良くしたいというプロセスこそがデザインなんです。デザインには正解がなく、人によって良いものが異なりますが、依頼していただいたクライアントにとって一番良いと思うことを考え続けて、何万個というアイデアの種を出すしかありません。デザインとは、おもてなしです。大事なのは、クライアントやクライアントのお客様のために、どこまで考え抜けるのかという点に尽きます」
日本の空で発生する“大渋滞”を解消するために。航空交通管理の現状とこれからの挑戦。

次に登壇したのは、東京大学先端科学技術研究センターで教授を勤める伊藤恵理氏。現在は航空輸送、航空交通管理システムを起点とした「航空宇宙モビリティ」の研究開発に従事している。これまでにオランダ航空宇宙研究所、NASAエイムズ研究所、電子航法研究所、南洋理工大学などでの研究歴を持ち、日本の航空管制や航空輸送、航空交通管理を専門とした科学者だ。
今、世界の航空輸送の分野で大きな関心事になっているのが、航空輸送の需要量増加。COVID-19の影響で一時的には大幅減少していたが、今後20年間で現在の約2倍以上は増加すると予測されている。そんな状況下で、国際線・国内線両方のターミナルを持ち、世界屈指の“busy”な空港として知られている羽田空港では、着陸待ちの航空機が空港の上空を旋回し、目的地まで遠回りをして時間調整をするケースが頻発している。
そんな日本の首都圏空港が抱える渋滞問題に対して、研究者の立場から様々な解決策を提案している伊藤氏が、航空交通管理の現状やテクノロジー導入について語った。
伊藤「まず航空機の歴史からお話しすると、ライトフライヤー1号が初の有人動力飛行に成功したのが1903年。まだ120年の歴史しかなく、航空機を誘導する航空管制官の誕生に至っては、まだ100年も経っていません。飛行機の離陸から着陸までの管制方法は、管制官の経験や勘に委ねられることが非常に多く、意外と旧式な方法を取っています。現代のデータ通信やGPSなどを駆使することで、管制官は要らなくなるように思えるかもしれませんが、そんなことは決してありません。現在の航空交通のインフラに最新テクノロジーやシステムを導入して、安全効率性の向上や環境負荷の低減を目指し、日々取り組んでいます」

伊藤「これまでに様々な挑戦と失敗を繰り返す中で導入したのが『待ち行列モデル』という理論です。その名の通り、航空機も順番に並んで着陸するまで待ちましょうというもの。これは私たちがラーメン屋さんに行く時に『混むかな?』『あとどれくらい待つかな?』と考えるのと同じような仕組みのシステムです。お客さんが団子になって来店するとお店は当然混みますし、早食いのお客さんが多いときは回転率も速いですが、早食いと遅食いのお客さんが混じっていたり、お店のカウンターの数が少なかったりしたら、お客さんの待ち行列ができやすいです。店舗の大きさを広げたり、遅食いのお客さんを制限したり、という対策は難しいですが、現実の制限のもと、待ち時間を最小にする仕組みをつくることができます。航空機の場合もそのような観点で、航空機の待機時間を最小にする”効率的な順番と間隔づけの制御”を実現させるシステムを考えていきました。データやシミュレーション実験で検証する中で、西から羽田に向かう航空機が愛知県や紀伊半島付近で混雑しており、そのエリアで適切に減速させる航空機と速度を管制官に教えてあげるAIシステムを導入することで、遅延時間を大幅に削減できることが分かってきました。空港内でも離陸までの滑走路渋滞が起きないように、航空機がターミナルゲートを出発するアルゴリズムをつくり導入することで、遅延時間と消費燃料の減少へと繋げています。」
他にも伊藤氏は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けてCO2排出量を実質ゼロにするために、温暖化に悪影響のある「ひこうき雲」の発生を抑える飛行計画を実施するなど、様々な挑戦をされている。2023年1月末には、ピーチ・アビエーションとNABLA Mobilityと産学連携し、航空機のFPA(Fixed-flight Path Angle)降下による航空機運航の環境負荷低減と高い実用性を、実機による定期運航便で世界で初めて実証した。今後どのように航空交通管理の分野で最新のテクノロジーが活用されていくのか、大いに期待したい。




 アカデミア
アカデミア